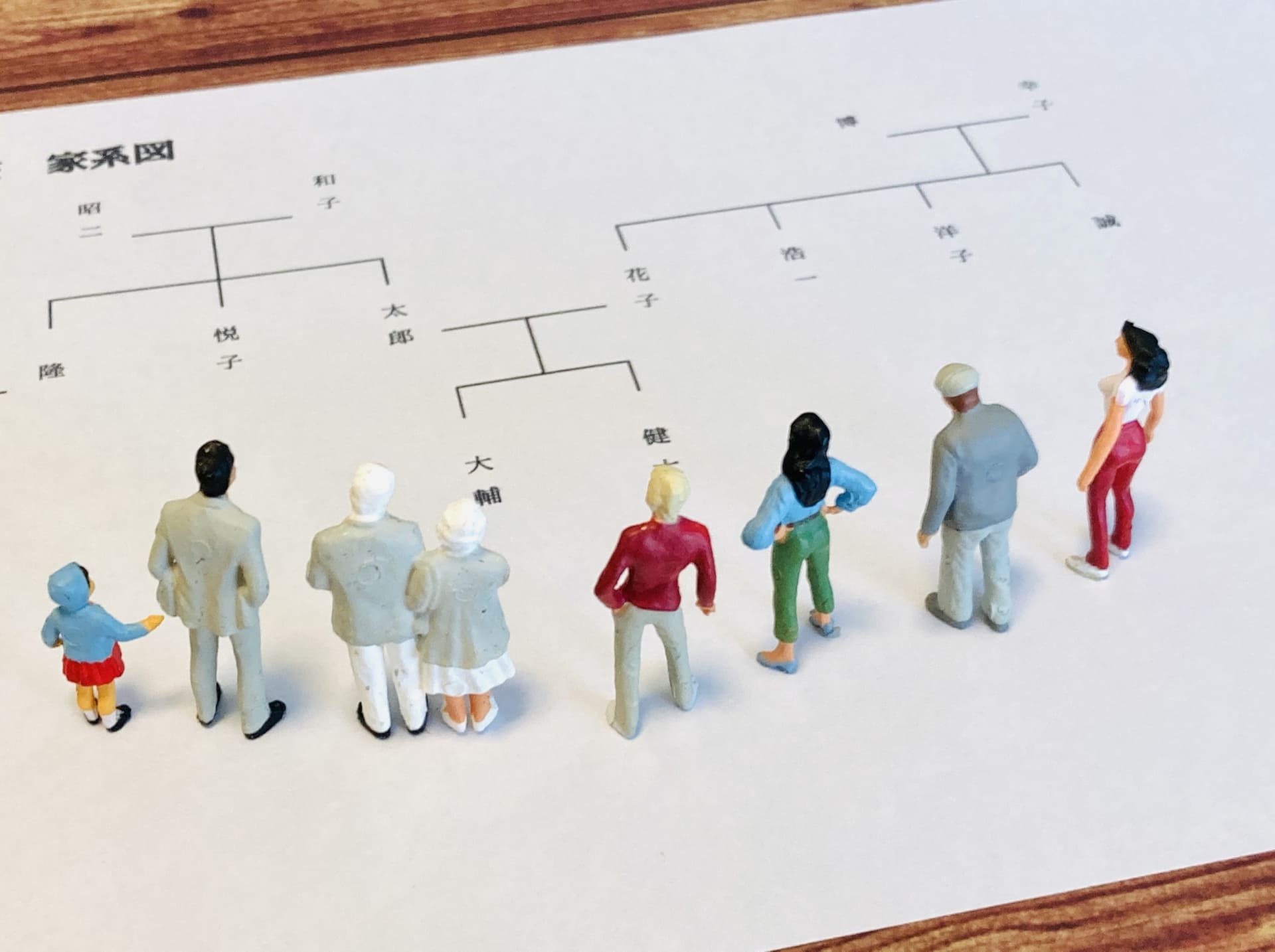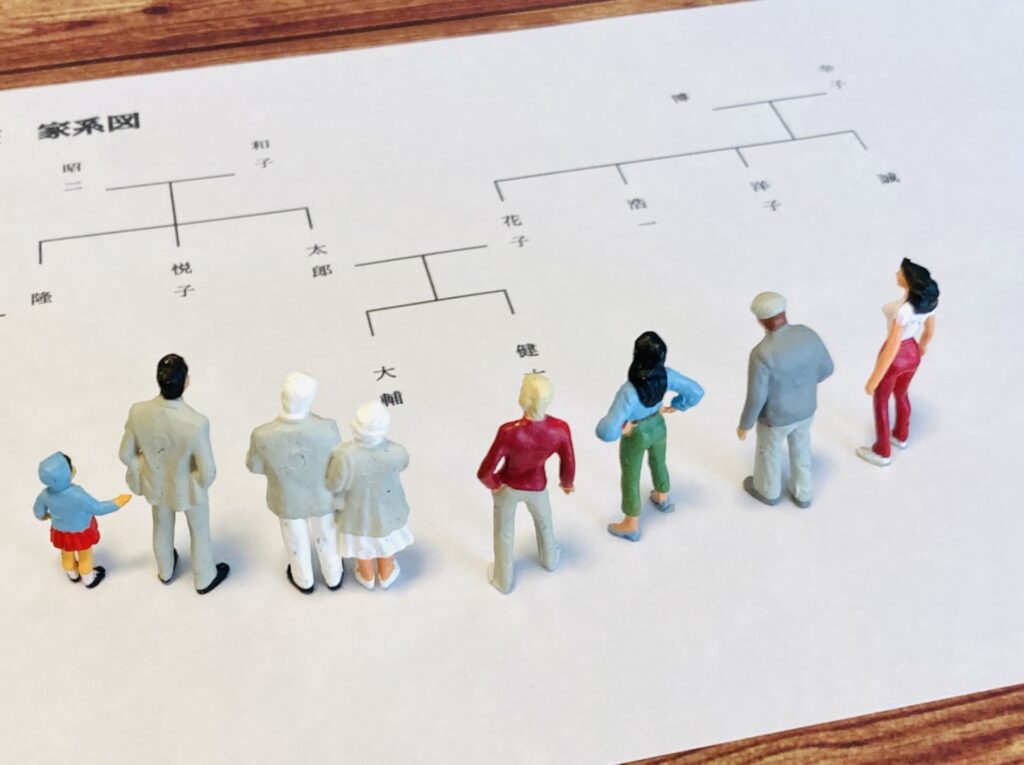
遺言の内容を実現するためには,遺言執行者を指定し,その遺言執行者によって遺言執行を行ってもらわなければならないという場合があります。
この遺言執行者を選任するには,遺言であらかじめ遺言執行者を指定しておく方法と,相続開始後に家庭裁判所の審判によって選任してもらう方法の2つの方法があります。
遺言執行者を指定・選任する方法
遺言の内容を実現するためには,さまざまな法律的な処理をしなければならないことがあります。そのうちでも,一定の事項については,遺言の執行をしなければならない場合があります。
この遺言の執行が必要となるもののうち,遺言認知(民法781条2項)や遺言廃除(民法893条)については,相続人だけでこれを行うことはできず,必ず遺言執行者によって行われなければならないとされています。
したがって,これらの場合には,必ず遺言執行者が選任されていなければならないということになります。
また,上記の遺言認知や遺言廃除の場合以外であっても,相続人間で足並みがそろわず手続が進まない場合などには,遺言執行者に執行してもらった方が良いという場合もあるでしょう。
この遺言執行者をつけるための方法には2つのものがあります。1つは,遺言であらかじめ遺言執行者を指定しておくという方法です。もう1つは,相続開始後に,家庭裁判所の審判によって遺言執行者を選任してもらうという方法です。
遺言による遺言執行者の指定
民法 第1006条
第1項 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
第2項 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
第3項 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
遺言者は,遺言によって,遺言執行者となるべき人を指定することができます。つまり,遺言書に,特定の人を遺言執行者に指定するという条項を記載しておくという方法です(民法1006条1項)。
もちろん,遺言で指定された人は,これを承諾するのか拒否するのかは自由です。しかし,承諾をした場合には,その指定された人が,遺言の効力発生時から,遺言執行者として職務を行わなければなりません。
法定相続人であっても,遺言執行者になることは,原則として可能です。したがって,遺言で,法定相続人を遺言執行者に指定することも可能です。
なお、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます(民法1006条2項)。遺言執行者の指定の委託とは、遺言執行者を誰にするのかを、第三者に選んでもらうということです。
相続開始後に遺言執行者を選任する方法
民法 第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
遺言で遺言執行者を指定していなかった場合でも,相続開始後に遺言執行者を選ぶことが可能です。
具体的には,法定相続人など利害関係人が,家庭裁判所に対して遺言執行者選任を申し立て,家庭裁判所が家事審判によって遺言執行者を選任することになります(民法1010条)。
ただし,この遺言執行者選任の審判は,遺言執行者がいないときか,または遺言執行者が欠けたときにしかできません。
したがって,遺言によって遺言執行者を指定しており、その人が承諾した場合には、遺言執行者選任の審判はできないことになります。
なお,指定または選任された遺言執行者が不適当である場合には、遺言執行者解任の審判の申立てをすることができます(民法1019条1項)。
これにより遺言執行者が解任された場合には,再度遺言執行者選任の審判申立てをすることができます。