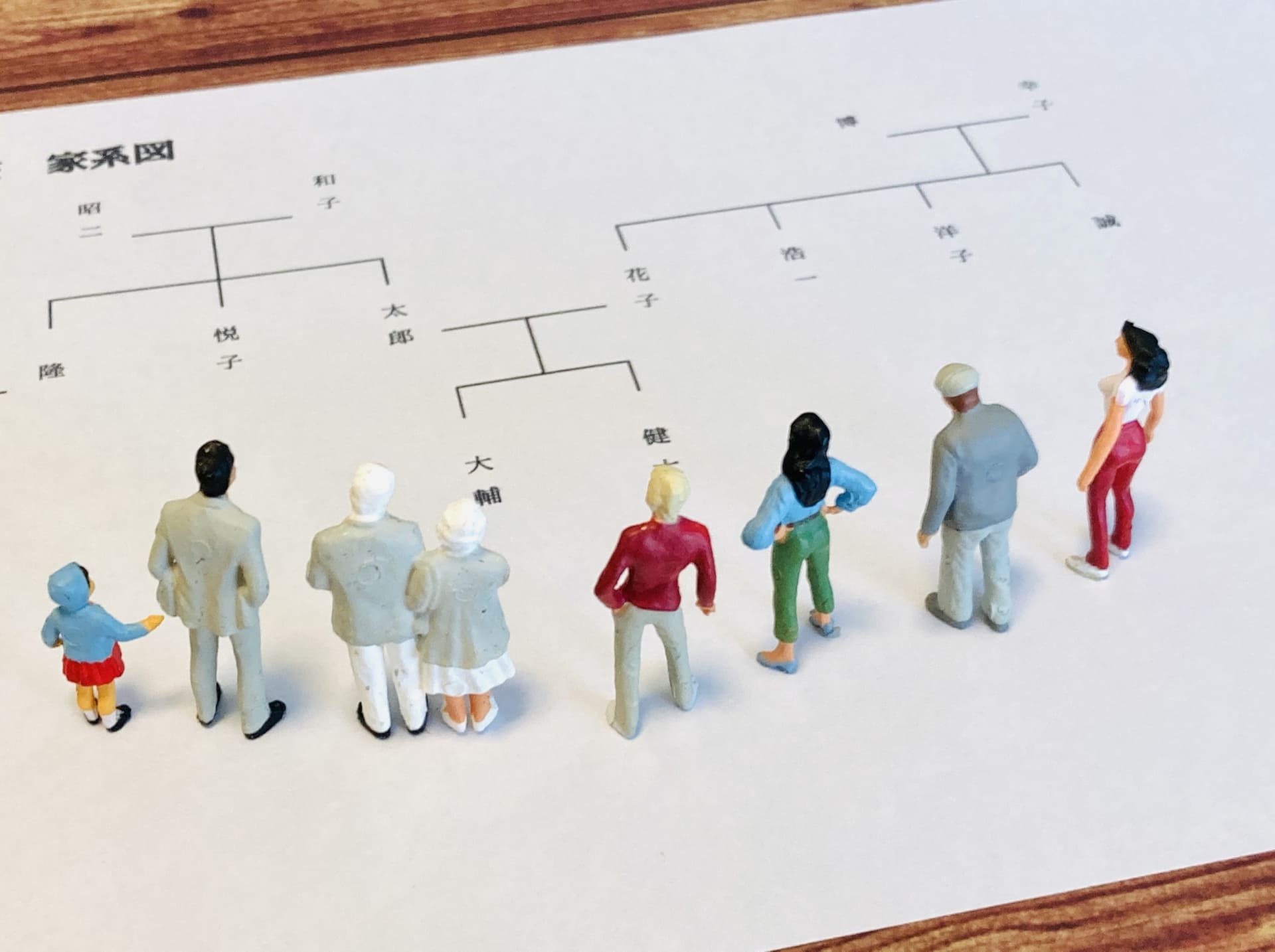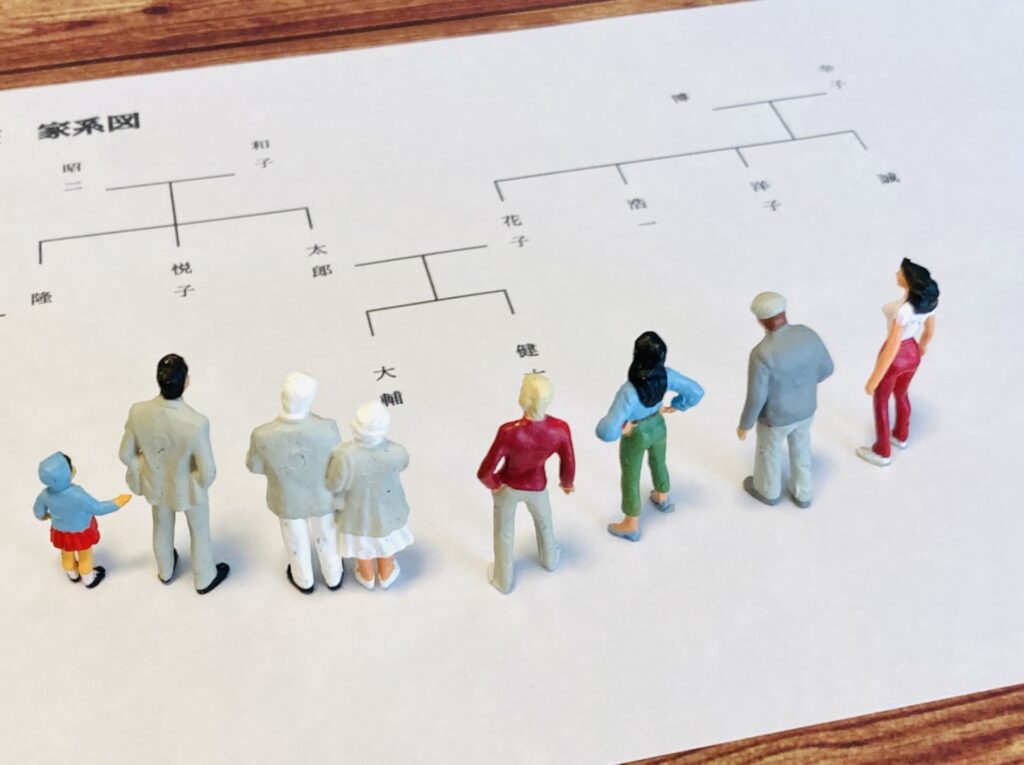
遺言書の検認とは,相続人・受遺者等の利害関係人に対し,遺言の存在およびその内容を知らせるとともに,遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし,その後の遺言書の偽造・変造を防止するための家庭裁判所における家事審判手続のことをいいます。
公正証書遺言を除く方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)の遺言書については,検認の手続を経ていなければ,遺言の執行をすることができません。
相続開始後における遺言書の取扱い
被相続人は,自身の意思を相続における財産の承継に反映させるために,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の方式で遺言を作成しておくことができます。
とはいえ,遺言があれば,自動的に遺言の内容が実現されるわけでもありません。遺言の内容を実現するためには,遺言の執行が必要となることがあります。
公正証書遺言は,公的な強制力があるため,それがあるだけで遺言の内容を実現するための遺言の執行をすることが可能となります。
これに対し,自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には,ただ遺言があるというだけでは,遺言の執行をすることはできません。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は,家庭裁判所で遺言書の「検認」の手続をとった後でなければ,遺言を執行することはできないのです。
したがって,自筆証書遺言や秘密証書遺言の遺言書がある場合には,相続開始後,勝手に封を開けてしまったり,遺言の執行を始めてしまう前に,この検認の手続をとらなければなりません。
※なお、自筆証書遺言について、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、遺言書情報証明書が交付されます。この遺言書情報証明書があると、検認をしなくても、遺言の執行が可能となります。
遺言書の検認とは?
民法 第1004条
第1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。民法 第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
遺言書の検認とは,相続人・受遺者等の利害関係人に対し,遺言の存在およびその内容を知らせるとともに,遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にし,その後の遺言書の偽造・変造を防止するための家庭裁判所における家事審判手続のことをいいます。
公正証書を除く遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は,相続の開始を知った後,遅滞なく,遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとされています(民法1004条1項,2項)。
また,遺言書に封印がされている場合には,家庭裁判所における検認の手続において開封しなければなりません(民法1004条3項)。検認以外の場で開封してしまうと,その遺言は無効になってしまいます。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人には,検認を経ないで遺言を執行し,または家庭裁判所外においてその開封をした者は,5万円以下の過料に処せられる場合があります(民法1005条)。
もちろん,封印がされている遺言書だけではありません。封印がされていない遺言書でも検認が必要です。
家庭裁判所においては,遺言書が偽造文書であることが明瞭な場合またはその記載が単なる子孫に対する訓戒に過ぎない場合でも,検認の申立てを却下すべきではないという方針を採っています(昭和28年5月20日家庭局長電報回答)。
それこそ,ノート1ページに書かれているような場合でも,相続財産の承継に関わる記載であれば,検認をしておいた方がよいでしょう。
検認の審判手続
遺言書の検認をするためには,まず,相続開始地を管轄する家庭裁判所に対し,検認の申立てをする必要があります。
検認の申立ては,遺言書検認申立書と呼ばれる家事審判申立書を提出する方式によって行います(家事事件手続法49条)。
検認の申立てがなされると,家庭裁判所は,検認の期日を定め,これを申立人・相続人・知れたる受遺者に対して通知します(家事事件手続規則115条1項)。
通知をして期日における立会いの機会を与えれば,実際に立ち会わなくても検認手続の期日を行うことができます。
検認の期日においては,家庭裁判所によって,遺言書について遺言の方式に関する一切の事実を調査し(家事事件手続規則113条),その結果を調書に記載します(家事事件手続法211条,同規則114条)。
検認の手続後,検認によってはじめて判明した相続人や受遺者に対しては検認された旨の通知がされます(家事事件手続規則115条2項)。
検認の効力
前記のとおり,検認の手続においては,家庭裁判所によって,検認日における遺言書の記載内容・形状・加除訂正の状態・日付・署名などについて検認調書が作成されます。
この調書には,公の証明力があります。したがって,その後に遺言書が改ざんされたとしても,検認日における遺言書の存在や内容等を証明することができるようになるのです。
ただし,検認は,あくまで遺言書の記載や形状・状態等を保全しておくための手続に過ぎません。したがって,検認によって,遺言書の有効または無効を確定させるものではありません。
遺言の効力について争いがある場合には,別途、遺言無効確認訴訟等によって決する必要があります。