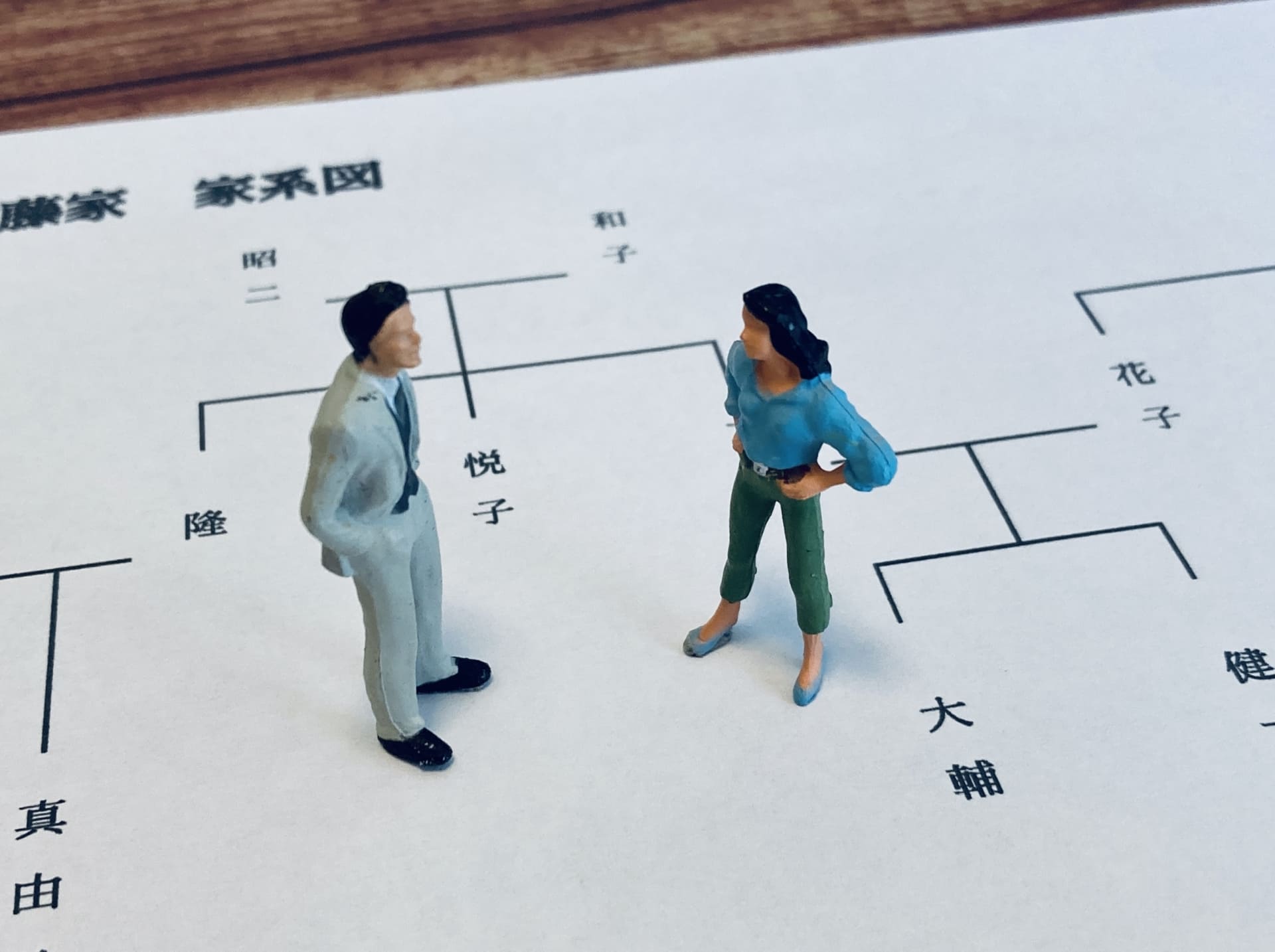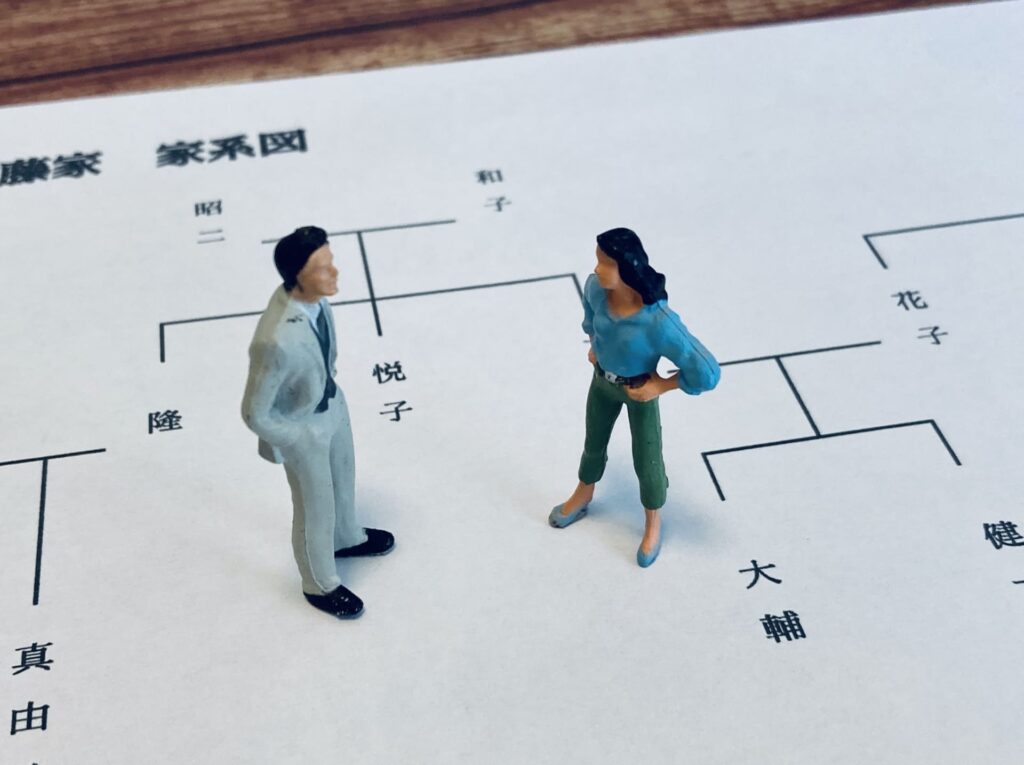
遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするためには,前提として,請求できる「遺留分侵害額」を計算しておく必要があります。
具体的な遺留分侵害額の計算式は,【 遺留分侵害額 = (被相続人が相続開始時に有していた積極財産 + 生前贈与財産 - 相続債務の全額)× 総体的遺留分 × 法定相続分 - 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益に該当する生前贈与の額 - 遺留分権利者が相続によって取得する遺産の額 + 遺留分権利者が負担する相続債務の額】です。
遺留分侵害額の計算手順
兄弟姉妹を除く法定相続人には,相続財産に対する最低限度の取り分として,遺留分(いりゅうぶん)が保障されています(民法1042条)。
遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合,遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は,その遺贈や贈与を受けた受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額の支払いを請求できます。
※2019年(令和元年)7月1日より前に開始した相続についての遺留分の場合は,遺留分侵害額の請求ではなく,遺留分侵害に応じた遺留分減殺請求によって遺留分権を行使することになります。
遺留分侵害額は,以下の手順で計算します。
まとめると,遺留分侵害額の算定式は以下のとおりとなります。
遺留分侵害額 =(被相続人が相続開始時に有していた積極財産 + 生前贈与財産 - 相続債務の全額)× 総体的遺留分 × 法定相続分 - 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益に該当する生前贈与の額 - 遺留分権利者が相続によって取得する遺産の額 + 遺留分権利者が負担する相続債務の額
以下,個別に説明します。
個別的遺留分の算定
民法 第1042条
- 第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
- 第1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
- 第2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
- 第2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
前記のとおり,遺留分侵害額を計算するには,遺留分権利者個々の個別的遺留分を算定する必要があります。個別的遺留分は,以下の計算式で算定します。
個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 法定相続分
「総体的遺留分」とは,相続財産全体に占める遺留分権利者に留保される割合です。総体的遺留分は,民法1042条1項で定められています。
- 直系尊属だけが相続人の場合 → 相続財産の3分の1
- それ以外の場合 → 相続財産の2分の1
この総体的遺留分に,各遺留分権利者の法定相続分を乗じて,「個別的遺留分」を算定します。遺留分権利者が複数人いる場合も同様です(民法1042条2項)。
例えば,相続人として父母A・Bがいる場合,直系尊属のみが相続人であるので総体的遺留分は3分の1となります。
そして,A・Bの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつであるので,総体的遺留分3分の1に法定相続分2分の1を乗じた6分の1が,A・Bそれぞれの個別的遺留分となります。
相続人として妻Cと子D・Eがいる場合,相続人が直系尊属のみではないので総体的遺留分は2分の1となります。
そして,Cの法定相続分は2分の1,D・Eの法定相続分はそれぞれ4分の1ずつであるので,Cの個別的遺留分は相対的遺留分2分の1に法定相続分2分の1を乗じた4分の1,D・Eの個別的遺留分は相対的遺留分2分の1に法定相続分4分の1を乗じた8分の1ずつとなります。
基礎財産の算定
民法 第1043条
第1項 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
第2項 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
遺留分率をもとに相続人各自の遺留分を算定するときの基礎となる財産のことを「基礎財産」と言います。遺留分額は,基礎財産に個別的遺留分の割合を乗じて算定します。
この遺留分算定の基礎財産は,以下の計算式によって算出することになります(民法1043条1項)。
遺留分算定の基礎財産 = 相続開始時において被相続人が有していた積極財産 + 贈与財産の価額 - 相続開始時において被相続人が負っていた相続債務
被相続人が相続開始時に有していた積極財産の加算
基礎財産には,まず,被相続人が相続開始時に有していた積極財産(プラスの財産・資産)が加算されます(民法1043条1項)。
この積極財産には,遺贈された財産も含まれると解されています。
なお,積極財産が条件付権利や存続期間の不確定な権利であった場合は,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を定めることになっています(民法1043条2項)。
贈与した財産価額の加算
民法 第1044条
第1項 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第2項 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
第3項 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については,同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
前記の積極財産に生前贈与した財産の価額を加算します(民法1043条1項)。ここで言う「贈与」には,贈与契約そのものだけでなく,無償での債務免除や担保提供など,すべての無償処分を含むと解されています。
ただし,すべての贈与が基礎財産に含まれるわけではなく,基礎財産に含まれる贈与は以下のものだけに限定されます。
- 相続開始前の1年間にされた贈与(民法1044条1項前段)
- 遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与(民法1044条1項後段)
- 相続開始前の10年間にされた相続人に対する特別受益に該当する(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた)贈与(民法1044条2項,3項)※ただし,令和元年7月1日より前に開始された相続の場合は,相続開始前10年間以内という制限はありません。
なお,相続人に対する贈与は,相続開始前1年間にされたものであっても,それが特別受益に該当するものでなければ,基礎財産には加算されないと解されています。
また,基礎財産に加算される贈与が負担付贈与であった場合,贈与価額から負担の価額を控除した額が,基礎財産に加算されます(民法1045条1項)。
相続債務の控除
前記積極財産と贈与を加算した額から,被相続人が相続開始時に負っていた債務(相続債務)の全額を控除して,基礎財産の額を算定します(民法1043条1項)。
この相続債務には,借金など私法上の債務だけでなく,税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
ただし,保証債務については,主債務者が支払不能で保証人が債務を履行しなければならならず,求償しても返還を受ける見込みがないような特段の事情のない限り,相続債務として控除することはできないと解されています(東京高判平成8年11月7日)。
遺留分額の算定
前記基礎財産に個別的遺留分の割合を乗じて,各遺留分権利者の具体的な「遺留分額」を計算していくことになります(民法1042条)。遺留分額は,以下のとおりです。
遺留分額 = 遺留分算定の基礎財産 × 個別的遺留分(=総体的遺留分の割合 × 法定相続分の割合)
遺留分侵害額の算定
民法 第1046条
- 第1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
- 第2項 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
- 第1号 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
- 第2号 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
- 第3号 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
前記までの手順で算定した遺留分額を侵害された場合,遺留分権利者は,「遺留分侵害額」を受遺者・受贈者に対して請求できます。
ただし,遺留分権利者がいくらかは遺産を相続をしていたり、個別に相続債務を負担したり、または特別受益や遺贈を受けていたりしているというケースもあります。遺留分侵害額を算定するに当たっては,これらの事情も考慮すべき必要があります。
具体的に言うと,遺留分侵害額は,以下の計算式で算定します。
遺留分侵害額 = 遺留分額 - 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益に該当する生前贈与の額 - 遺留分権利者が相続によって取得する遺産の額 + 遺留分権利者が負担する相続債務の額
上記計算によっても,遺留分侵害額が無かった場合には,遺留分侵害額請求ができないということになります。