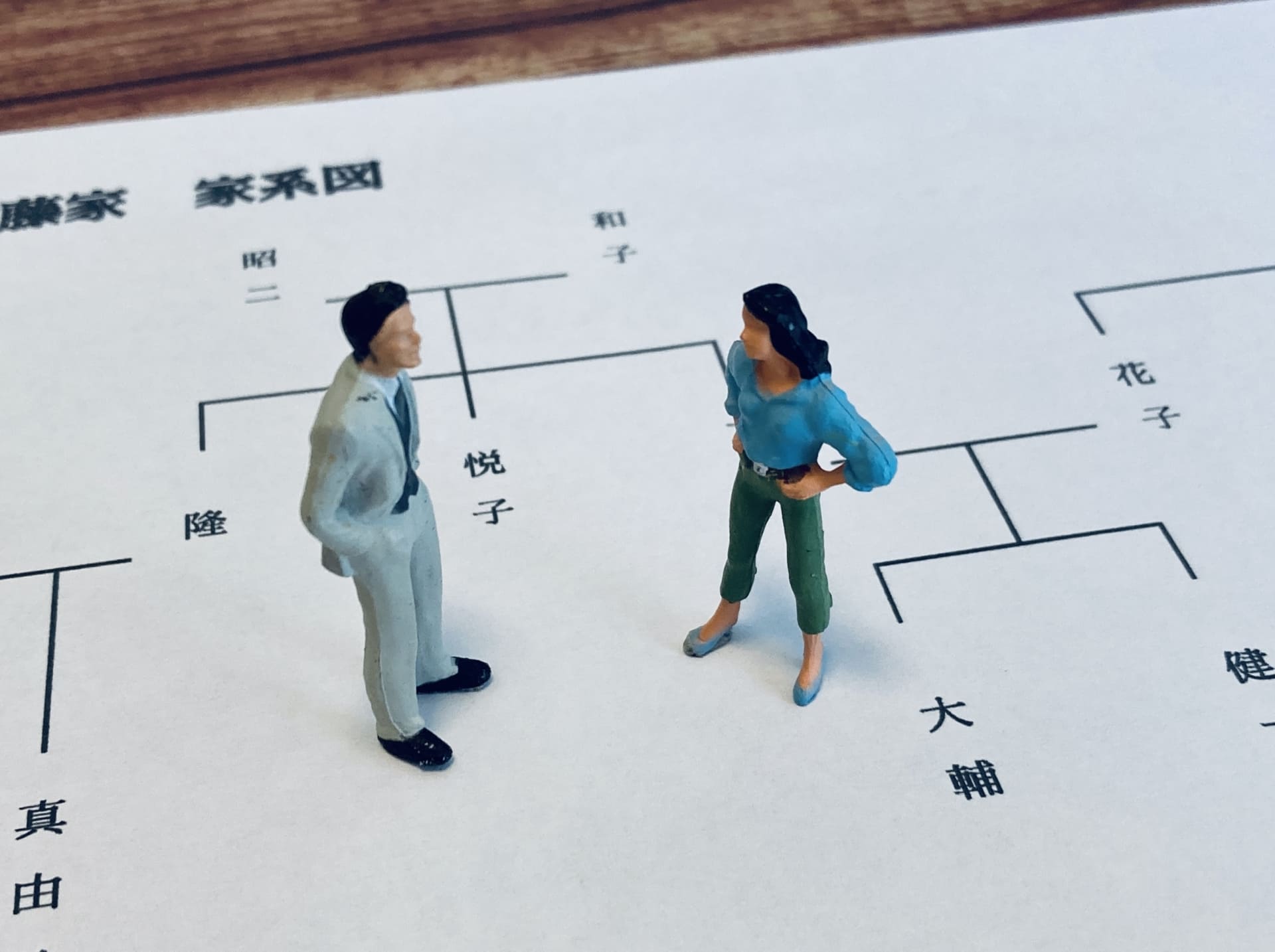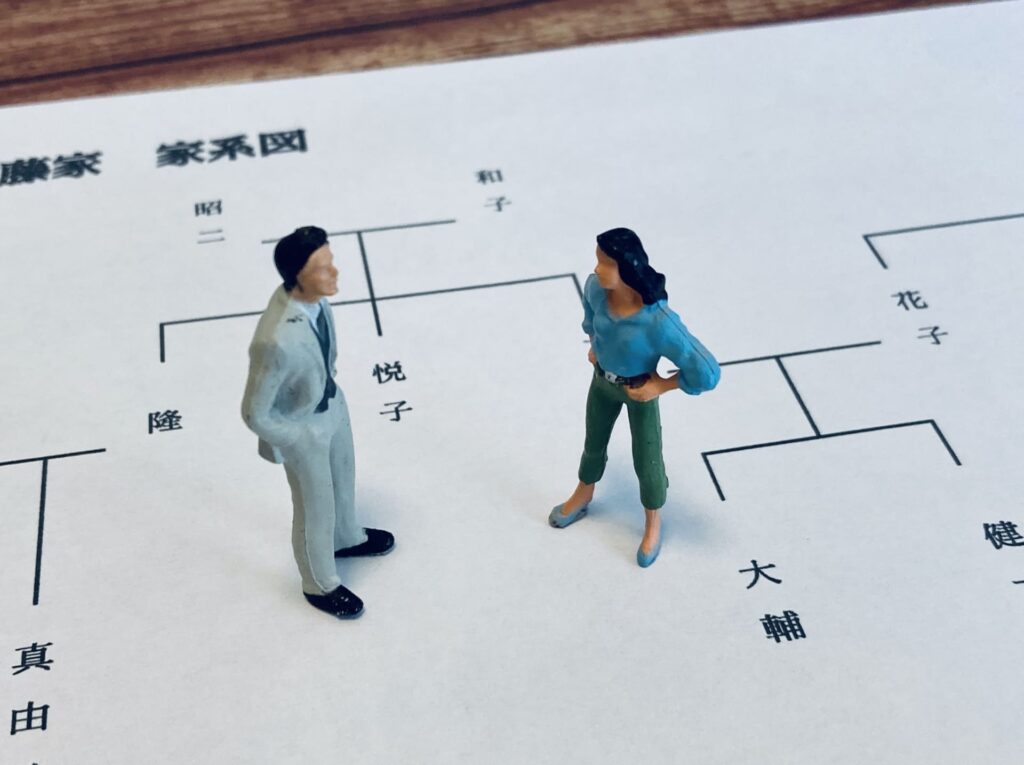
遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間で時効により消滅します(民法1048条前段)。また,相続の開始から10年間経過すると,除斥期間により請求ができなくなります。したがって,これらの期間内に権利を行使しなければなりません。
なお,遺留分侵害額請求により生じる金銭請求権は,遺留分侵害額請求権とは別に消滅時効の対象になります。この金銭請求権は,権利を行使できることを知った時から5年間または権利を行使できる時から10年間のいずれか早い方の期間で時効消滅します(民法166条1項)。
遺留分侵害額請求ができる期間
民法 第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
兄弟姉妹を除く法定相続人は,遺言や贈与によって法定相続分を削られてしまった場合,多くの遺産を受け取った受遺者や受贈者に対して,遺留分侵害額を請求することができる場合があります。
もっとも,この遺留分侵害額請求は,いつまででもできるというわけではありません。遺留分侵害額請求ができる期間は,民法によって決められています。
遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消滅します(民法1048条前段)。
また,相続開始時から10年を経過した場合も,遺留分侵害額請求権ができなくなります(民法1048条後段)。こちらは,消滅時効ではなく,除斥期間であると解されています。
つまり,遺留分侵害額請求権には,以下の2つの期限があるということです。
- 遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈のあったことを知った時から1年間
- 相続開始時から10年間
遺留分侵害額請求権の消滅時効
前記のとおり,遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年が経過すると,時効によって消滅してしまいます(民法1048条前段)。
あくまで,相続の開始と贈与・遺贈があったことを「知った時」からカウントしますから,相続が開始されていたことや,減殺すべき贈与や遺贈があったことを知らなければ,消滅時効期間は進行しません。
たとえ相続開始等から1年以上が経過していようとも,相続開始等を知らないままであれば,遺留分侵害額請求権が時効によって消滅することはないということです(ただし,相続開始から10年経過すると,後述の除斥期間によって消滅します。)。
この遺留分を侵害する贈与または遺贈を「知った時」とは,単にその贈与や遺贈がなされた事実を知ったというだけではなく,その贈与等によって自分の遺留分が侵害されていることまで認識している必要があると解されています。
また,知っていた事柄の対象は,「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈」です。したがって,相続の開始を知っていたとしても,贈与や遺贈があったことを知らなければ,消滅時効期間は進行しません。
なお,遺留分侵害額請求権は形成権ですので,1年間以内に請求や催告などをすれば当然に侵害額請求の効果が生じます。
そのため,時効更新は必要ないと考えられています(遺留分減殺請求の場合について最一小判昭和41年7月14日)。
要するに,時効の更新という形をとらなくても,1年間以内に1回でも遺留分侵害額請求権を行使(催告や請求など)しておけば,それ以降,遺留分侵害額請求の消滅時効は問題とならない(時効によって消滅することはなくなる)ということです。
遺留分侵害額請求権の除斥期間
前記のとおり,遺留分侵害額請求権には,消滅時効のほかに,除斥期間があります。具体的に言えば,相続開始の時から10年を経過すると,遺留分減殺請求ができなくなってしまいます(民法1048条後段)。
これは除斥期間ですので,消滅時効ではありません。したがって,更新もありません。相続開始時から10年が経過してしまうと,更新などもなく,完全に請求ができなくなってしまうのです。
ただし、前記のとおり、遺留分侵害額請求権は形成権です。したがって、この10年の期間内に1回でも遺留分侵害額請求権を行使しておけば権利を行使したことになるので、除斥期間によって権利が消滅することはなくなります。
遺留分侵害額請求による金銭請求権の消滅時効
前記のとおり,遺留分侵害額請求権には,消滅時効や除斥期間といった期間制限があります。したがって,これらの期間内に遺留分侵害額請求権を行使しておかなければなりません。
もっとも,遺留分侵害額請求権は形成権と解されています。そのため,これを1度でも行使すれば,当然に侵害額請求の効果が生じることになるため,消滅時効や除斥期間は問題とならなくなります。
しかし,これは,あくまで「遺留分侵害額請求権」の消滅時効や除斥期間が問題とならなくなるというだけです。遺留分侵害額請求によって生じた金銭請求権については別途,消滅時効が進行していくことになります。
遺留分侵害額請求をすると,受遺者または受贈者に対して,金銭の支払いを請求する権利(金銭債権)を取得します。
この金銭請求権は,遺留分侵害額請求権の行使に基づいて生じるものですが,債権としては,遺留分侵害額請求権とは別個の金銭債権であると考えることになります。
そのため,この金銭請求権は,遺留分侵害額請求権とは別に消滅時効の対象となります。
具体的にいえば,この遺留分侵害額請求の行使によって取得した金銭債権は,民法の一般準則に従って,権利を行使できることを知った時から5年間または権利を行使できる時から10年間のいずれか早い方の期間で時効消滅することになります(民法166条1項)。
このように,遺留分侵害額請求権自体は1回行使すれば時効消滅等がなくなるとしても,それによって生じた金銭請求権については消滅時効がなくなったわけではないので,別途,時効更新措置をとるなどの必要性があることには,注意が必要です。