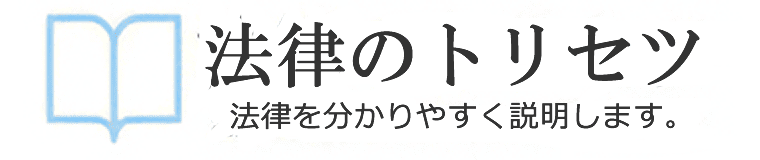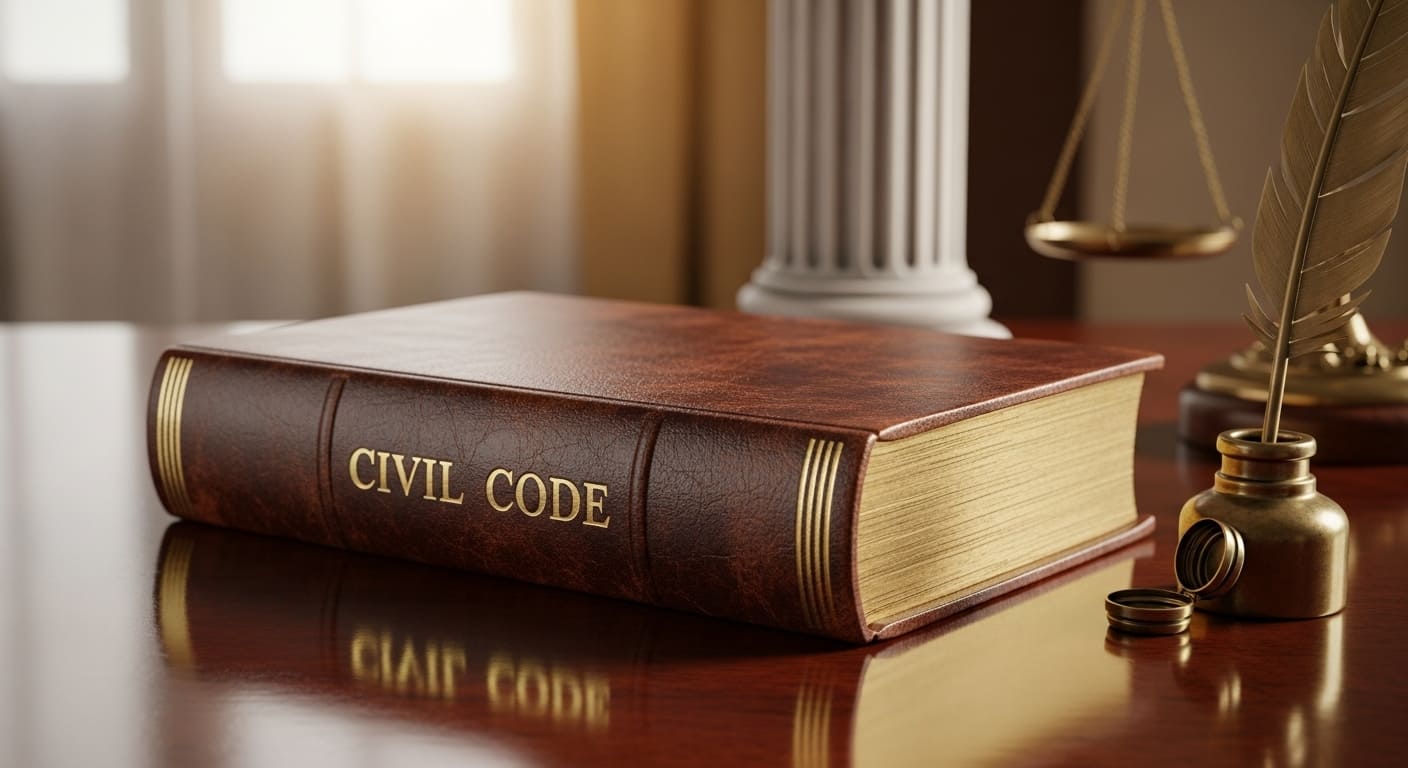この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
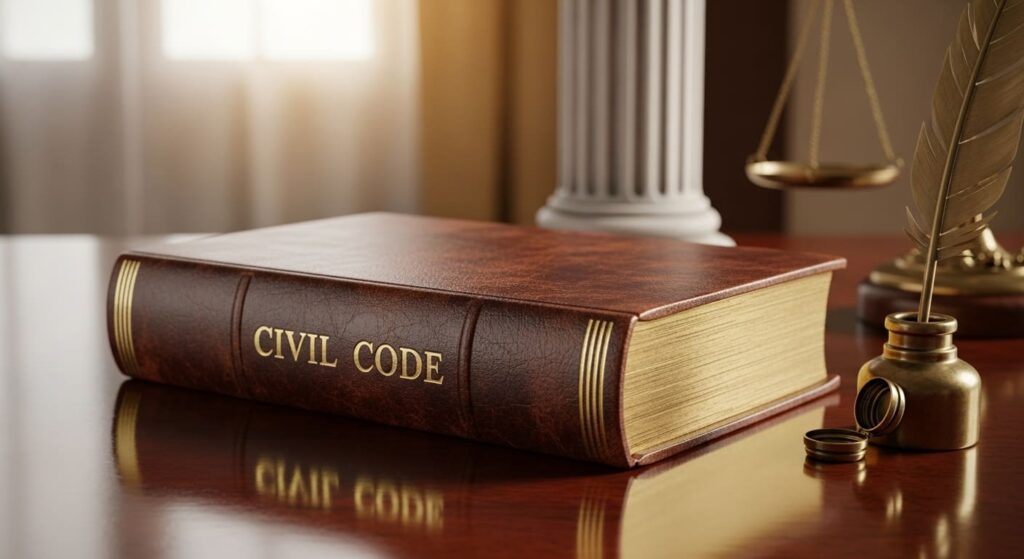
私人間の権利義務関係を規律する法のことを「私法」といいます。その私法の基本となる法律が「民法」です。つまり,民法とは,市民生活や事業などにおける基本的なルールを定めた法律です。
民法とは
民法とは、私法の基本法です。私法の一般法と呼ばれることもあります。
「私法」とは私人(市民)相互間の権利義務関係(法律関係)を規律する法のことをといいます。
私人相互間の法律関係とは,私人(市民)と公権力との間の法律関係ではない(公権力との間の法律関係を規律する法は「公法」と呼ばれます。)ということです。
私人間の権利義務は非常に多種多様で複雑ですから,当然,私法に当たる法令も無数にあります。そのうちで最も基本となるのが、この「民法」です。そのため,民法は,私法の基本法と呼ばれているのです。
また,「一般法」とは,特定の人や事物にだけ適用されるのではなく,広く一般的抽象的に適用される法のことをいいます。
民法は,私法のうちでも特定の私人間法律関係に限定されず,広く私人間の法律関係一般に適用される法律であることから,私法の一般法でもあります。
つまり,民法とは,市民相互間の法律関係の最も基本的なルールを定めている法律です。
個人の生活に関わる法律問題も,法人・事業者の事業に関わる法律問題も,すべてこの民法を基本としているといってもよいでしょう。
それだけに,司法試験も含めた各種の法律系国家資格の資格試験では,必ずといってよいほど,この民法が受験科目とされています。
日本で最初に民法が制定されたのは,明治29年のことです(なお,家族法部分は明治31年)。その後,数度の改正が行われており,近時も,債権法や相続法に大きな改正がありました。
民法の基本原理・原則
何をもって民法の基本原理とするのかについては,さまざまな見解があります。
一般的には,私法の三大原理・原則である「権利能力平等の原則」,「所有権絶対の原則」,「私的自治の原則」の3つが,民法においても基本原理・原則と解されています。
権利能力平等の原則
権利能力平等の原則とは,誰もが平等に権利義務の主体となることができるとする原則です。
民法は本質的平等を旨として解釈しなければいけないとされています(民法2条)。また、何ら制限を付けることなく、人は出生によって権利能力を取得すると規定されています(民法3条1項)。
これらのことから、民法においても、権利能力平等の原則が採用されていることは明らかです。
所有権絶対の原則
所有権絶対の原則とは,個人の有する所有権は,他人はおろか,国家権力によっても侵害することのできない神聖不可侵な権利であるとする原則です。
明文はありませんが,この所有権絶対の原則も,民法上の基本原理であると解されています。
私的自治の原則
私的自治の原則とは,私人間における権利義務関係(法律関係)は,国家権力の介入によってではなく,各個人の自由意思に基づき規律されるべきであるとする原則のことをいいます。
この私的自治の原則からは,さらに法律行為自由の原則(契約関係においては「契約自由の原則」として,相続においては「遺言自由の原則」において,顕れることになります。)と過失責任の原則が派生すると考えられています。
この私的自治の原則も,民法の基本原理とされています。現に,民法においても,契約の締結や遺言の作成について特段の制限が付けられないのが原則とされています。
民法の構成
日本の民法は,ドイツ民法の例にならって,パンデクテン方式と呼ばれる方式で編成されています。
パンデクテン方式とは,共通する一般的・総則的な事柄を最初にまとめて規定し,個別の規定をその後に規定する方式です。
民法は,大きく分けて,2つのカテゴリーに分かれています。1つは,財産関係を規定する「財産法」の部分と,家族関係を規定する「家族法」の部分です。
財産に関する規定(財産法)
民法のうち財産関係についての規定の部分のことを「財産法」と呼んでいます。財産法は,総則,物権,債権に分かれています。
民法総則
民法第一編「総則」には,財産法全体に共通する規定が定められています。総則のうち通則では,信義誠実の原則(信義則)や権利濫用の禁止など私法の基本原則が定められています。
また,総則では,人(自然人)や法人など権利義務の主体・客体に関する規定,意思表示など法律行為に関する規定,時効に関する規定などが定められています。
物権(物権法)
民法第二編は「物権」です。物権とは,物に対する排他的な支配権のことをいいます。
物権には,所有権,占有権のほか,地上権・永小作権・地役権といった用益物権,抵当権・留置権・質権・先取特権といった担保物権があります。
物権に関する規定の部分のことを「物権法」と呼ぶことがあります。
債権(債権法)
民法第三編は「債権」です。債権とは,特定人に対して特定の給付や行為を求める権利のことをいいます。
債権に関する規定は,債権全般に共通する規定を定める債権総論(債権総則)と,債権の発生原因ごとに、契約、事務管理、不当利得、不法行為が定められています。この債権発生原因ごとに定めている部分のことを債権各論と呼ぶことがあります。
債権に関する規定の部分のことを「債権法」と呼ぶことがあります。
債権総則(債権総論)
債権総則(債権総論)では,債権全般に共通するものとして,債権の種類など債権の目的・債務不履行責任や債権者代位権など債権の効力・保証契約など多数当事者の債権債務・債権譲渡・弁済や相殺など債権の消滅に関する規定が置かれています。
債権各論
債権各論では,契約に基づく債権とそれ以外の債権とが規定されています。
契約に関する規定は,契約全般に共通する規定を定める契約総論と個別の契約類型ごとに規定を定める契約各論とがあります。
契約総論では,契約の成立・同時履行の抗弁や危険負担など契約の効力・契約の解除などが定められています。
契約各論では,贈与・売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解の各契約について定められています。契約に関する規定の部分のことを「契約法」と呼ぶことがあります。
また,契約以外の債権の発生原因に関する規定としては,事務管理・不当利得・不法行為が規定されています。
家族に関する規定(家族法)
民法のうち家族関係についての規定の部分のことを「家族法」と呼んでいます。家族法は,さらに,親族関係について定める親族と相続関係について定める相続に分かれています。
親族(親族法)
民法第四編は「親族」です。親族に関する規定の部分を「親族法」と呼ぶことがあります。
親族法では,親族関係についての基本を定める総則,婚姻や離婚,親子関係,養子縁組や離縁,親権,後見,扶養などを規定しています。
相続(相続法)
民法第五編は「相続」です。相続に関する規定の部分を「相続法」と呼ぶことがあります。
相続法では,相続の開始,相続人,遺産分割などの相続の効力,相続の承認・相続放棄,相続人の不存在の場合の処理,遺言などについて規定しています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂民法総則(民法講義Ⅰ)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内1(第二版)」や「ダットサン民法総則・物権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法の基礎1(総則)第5版
著者:佐久間毅 出版:有斐閣
民法総則の基本書。基礎的なところから書かれており、読みやすく情報量も多いので、資格試験の基本書として使うには十分でしょう。
スタートアップ民法・民法総則(伊藤真試験対策講座1)
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。