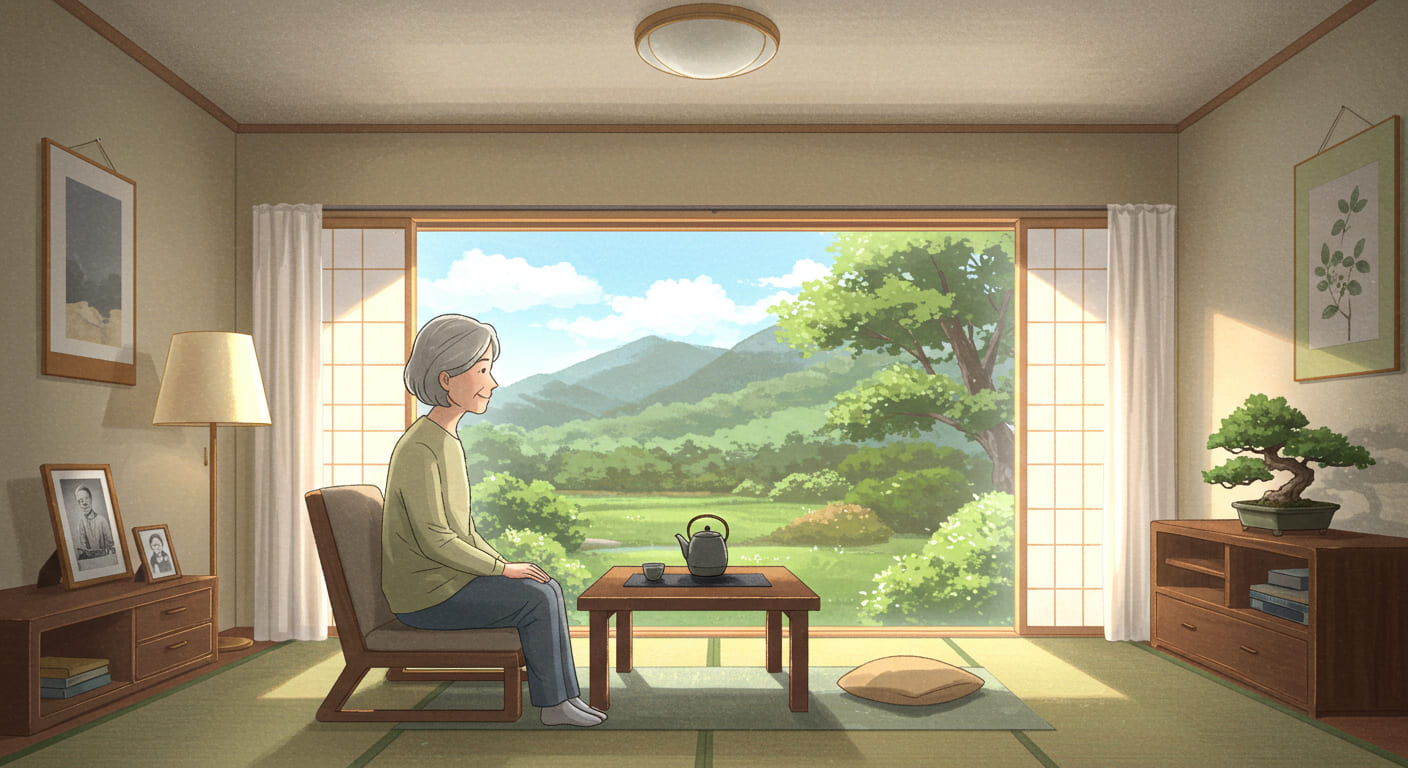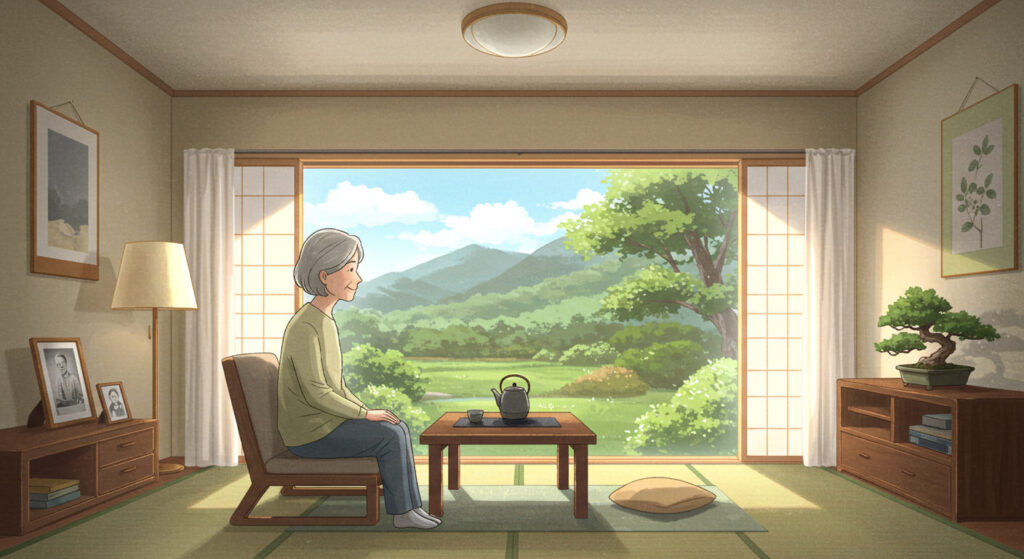
配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,その居住建物所有権を相続または遺贈により取得した者に対して,居住建物について無償で使用することができる権利のことを言います(民法1037条1項柱書本文)。
相続における配偶者短期居住権
- 民法 第1037条
第1項 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。- 第1号 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
- 第2号 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
- 第2項 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
第3項 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
高齢化が進む現代においては,被相続人が死亡した場合,被相続人が所有する建物に居住していた配偶者の居住の権利をどのように保護すべきかという点が重要な課題とされてきました。
そこで,改正民法(令和2年4月1日施行)では,被相続人の配偶者の居住の権利を確保するために,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という制度が設けられました。
このうち配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,一定の期間,その居住建物所有権を相続または遺贈により取得した者に対して,居住建物について無償で使用することができる権利のことを言います(民法1037条1項柱書本文)。
配偶者短期居住権の内容
配偶者短期居住権が認められた場合,配偶者は,民法1037条1項各号に定める期間,相続開始の時に居住していた被相続人の財産に属する建物を,無償で使用することができるようになります。
居住建物について生存配偶者を含む共同相続人が遺産分割をすべき場合には,配偶者短期居住権の存続期間は,遺産分割によって居住建物の帰属が確定した日または相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとなります(民法1037条1項1号。この場合を「1号配偶者短期居住権」と呼ぶことがあります。)。
他方,居住建物について生存配偶者が遺産分割の当事者とならない場合には,居住建物所有権を相続または遺贈により取得した者が配偶者短期居住権消滅の申入れをした日から6か月を経過する日までとなります(民法1037条1項2号。この場合を「2号配偶者短期居住権」と呼ぶことがあります。)。
配偶者短期居住権の場合,配偶者居住権と異なり,居住建物の収益権は認められず,使用権しか認められません。
とはいえ,配偶者短期居住権は無償です。したがって,居住建物の所有者等に対して,使用収益の対価(賃料等)を支払う必要はありません。
配偶者短期居住権の及ぶ範囲は,配偶者居住権と異なり,建物の全部に及ぶわけではなく,配偶者が相続開始時に無償で使用していた部分にしか及びません。
ただし,配偶者短期居住権は,配偶者居住権と異なり,遺産分割,遺贈または家庭裁判所の審判で定めなくても,後述する民法で定める要件を充たしていれば成立します。
配偶者短期居住権の法的性質
配偶者短期居住権の法的性質は,民法上,使用借権に類似する法定債権と捉えられています。配偶者短期居住権の債権者は生存配偶者であり,債務者は居住建物の所有者です。
そのため,使用貸借に近い制度設計になっています。 ただし,配偶者短期居住権はあくまで生存配偶者の居住を確保するための特別な債権ですから,使用貸借そのものでなく,配偶者短期居住権特有の効力もあります。
この配偶者短期居住権は譲渡性を有しません。したがって,他の相続人から同意を得ていたとしても,第三者に譲渡することはできません(民法1041条,1032条2項)。
配偶者短期居住権の成立要件
配偶者短期居住権が認められるためには,以下の要件を充たしている必要があります。
これらの要件を充たしていなければ,配偶者居住権は認められません。
なお,配偶者が相続放棄をした場合,1号配偶者短期居住権は認められませんが,2号配偶者短期居住権は認められます。
配偶者短期居住権の効力
前記のとおり,配偶者短期居住権が認められる場合,生存配偶者は,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物を無償で使用することができます。
ただし,居住の目的または従前の用法に従って,善良な管理者の注意をもって,居住建物を使用しなければいけません(民法1038条1項)。
また,居住建物の取得者の承諾を得なければ,第三者に使用収益させることはできません(民法1038条2項)。
配偶者が善管注意義務や無承諾で使用収益させた場合,居住建物の取得者は,配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができるとされています(民法1038条3項)。
もっとも,配偶者は,居住建物取得者の承諾を得なくても,使用に必要な範囲で居住建物を修繕することはでき,居住建物の修繕が必要であるにもかかわらず配偶者が修繕をしない場合,居住建物取得者自ら修繕することができます(民法1041条,1033条2項,3項)。
さらに,居住建物についての通常の必要費は,配偶者が負担します(民法1041条,1034条1項)。
他方,居住建物の取得者は,第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法で配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない義務を負います(民法1037条2項)。
ただし,居住建物の取得者は,居住建物を使用に適した状態にしなければならない修繕義務までは負いません。
配偶者短期居住権の対抗要件
配偶者短期居住権は,配偶者居住権と異なり,第三者対抗力がありません。したがって,登記もできません。
ただし,配偶者は,居住建物の取得者に対して,居住建物を使用させる義務の不履行を理由として損害賠償を請求することは可能です。
配偶者短期居住権の消滅
配偶者居住権は,以下の場合に消滅します。
- 配偶者が死亡した場合(民法1041条,597条3項)
- 存続期間が満了した場合(民法1037条1項各号)
- 居住建物が全部滅失した場合(民法1041条,616条の2)
- 配偶者が善管注意義務に違反しまたは無承諾で使用収益させたことを理由として,居住建物の取得者が,配偶者に対し,配偶者短期居住権を消滅させる意思表示をした場合(民法1038条3項)
- 配偶者が配偶者居住権を取得した場合(民法1039条)
- 配偶者が配偶者短期居住権を放棄した場合
配偶者短期居住権が消滅した場合,配偶者は,居住建物を返還する義務を負います(民法1040条1項本文)。
この場合,配偶者は,居住建物に附属させたものがあればそれを収去し,通常損耗や経年劣化によるものを除いて,建物を原状回復して返還しなければなりません(民法1040条2項,599条,621条)。
ただし,配偶者が居住建物について共有持分も有している場合には,居住建物の取得者は,配偶者短期居住権が消滅したこと理由として居住建物の返還を求めることはできません(民法1040条1項ただし書き)。
なお,配偶者が亡くなった場合,配偶者短期居住権はその配偶者の相続人には相続されず,権利が消滅します。