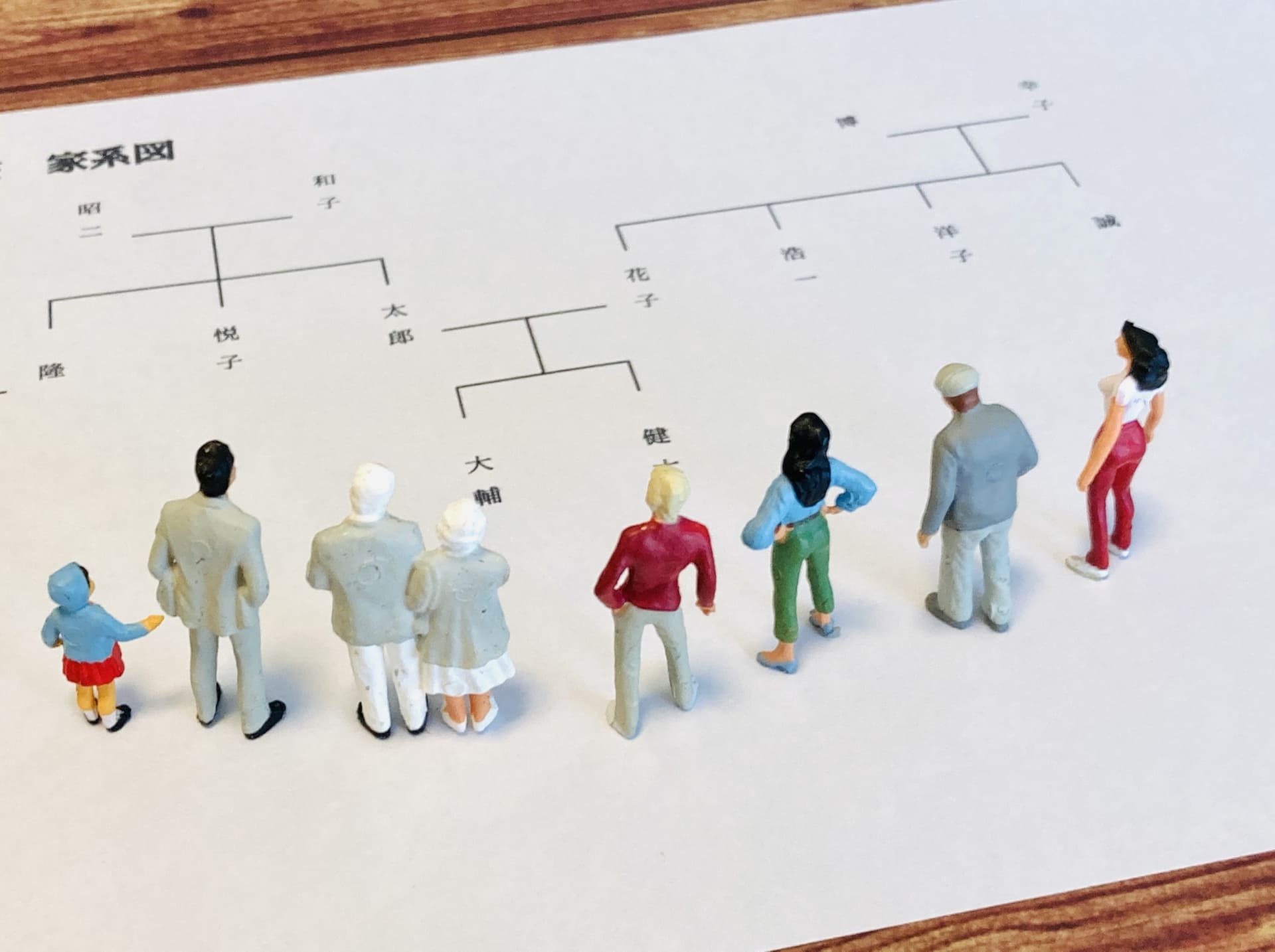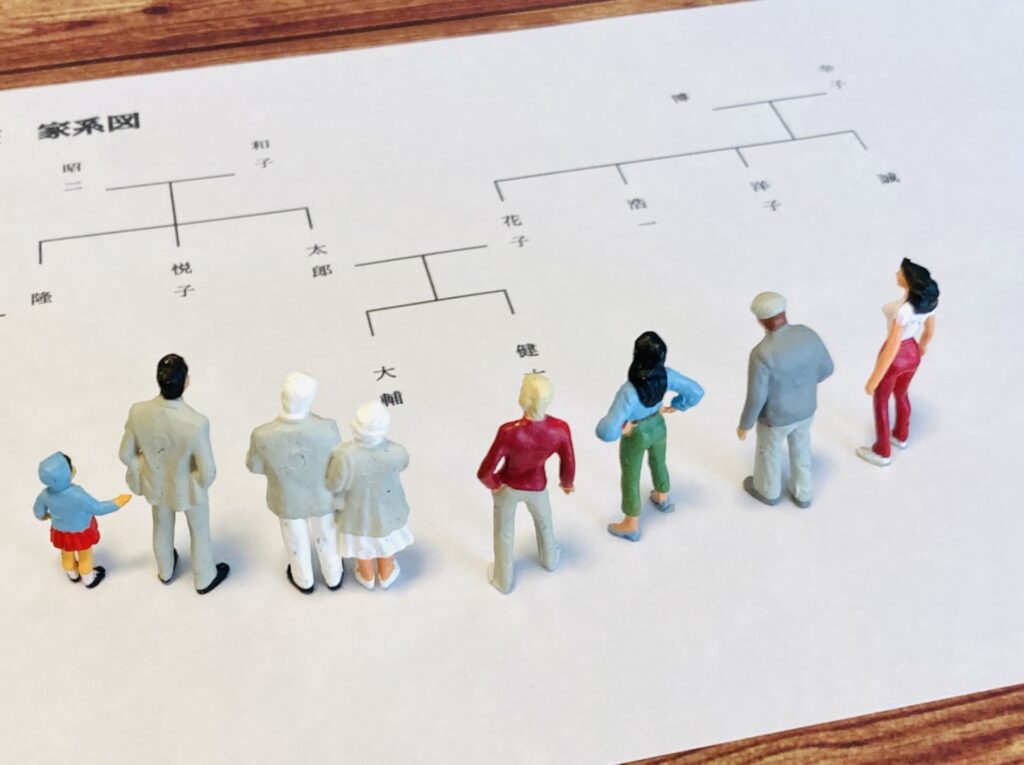
「遺産分割方法の指定」とは,遺言で,遺産分割の方法を定めることをいいます(民法908条)。遺産分割方法の指定は,遺言で,第三者に委託することも可能です。この遺産分割方法の指定および第三者への委託は遺言でしなければ効力を生じません。
遺言による遺産分割方法の指定とは?
民法 第908条
第1項 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
第2項 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
第3項 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
第4項 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
第5項 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。
相続人が複数人いる場合,相続の開始によって共同相続人間で共有または準共有となった遺産(相続財産)の具体的な配分を確定させるためには,遺産分割を行う必要があります。
被相続人は,遺言で,遺産分割の方法を定めることができます。これを「遺産分割方法の指定」といいます(民法908条1項)。
この遺産分割方法の指定は,遺言によってしなければ効力を生じません。
また,遺産分割方法の指定は,被相続人が自らするのが基本ですが,第三者に委託することもできます(民法908条1項)。ただし,第三者に委託することを遺言にしておく必要はあります。
遺産分割方法の指定の効力
遺産分割方法の指定は,法定相続分は変更せずに,法定相続分の範囲内で相続財産をどのように配分するかについての方法を定めるのが,本来的な指定方法です。
遺産分割の方法としては,現物分割,個別分割,換価分割,代償分割といったものがあります。これらのうちどれを選択するのかを指定するのが,本来的な遺産分割方法の指定ということです。
ただし,遺産分割方法の指定がある場合でも,共同相続人全員の協議によって指定と異なる遺産分割をすることは可能であると解されています。
第三者対抗要件の要否
民法 第899条の2
第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
遺産分割方法の指定によって,ある相続財産につき法定相続分の割合を超えて権利を取得した場合,従前は,対抗要件を備えなくても,その取得した権利の全部を第三者に対抗できると解されていました。
もっとも,登記などの対抗要件が具備されていないのに,すべて第三者に対抗できるとしたのでは,登記による公示を信頼して取引をした第三者に不利益をもたらすおそれがあり,取引の安全を害します。
そのため,民法改正(2019年7月1日施行)によって,遺産分割方法の指定によって法定相続分を超える部分を承継した場合,承継した相続人は,その法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされました(民法899条の2)。
なお,法定相続分の範囲内の部分については,従前どおり対抗要件なくして第三者に対抗できます。
もっとも,この民法899条の2の規定が適用されるのは,2019年7月1日以降に相続が開始した場合です。
2019年7月1日より前に開始していた相続については,従前どおり,対抗要件を備えなくても承継した相続分の全部を第三者に対抗できることになります(ただし,債権については例外があります。)。
遺産分割方法の指定と特定財産承継遺言
「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」のことを「特定財産承継遺言」といいます(民法1014条2項参照。かつては「相続させる旨の遺言」と呼ばれていました)。
特定財産承継遺言は,遺贈であるといえるような特段の事情の無い限り,遺産分割方法の指定であると解されています(なお,法定相続分を超える財産の承継がある場合には,相続分の指定も含むと解されます。最二小判平成3年4月19日等)。
ただし,前記の本来的な遺産分割方法の指定と異なり,遺言の効力発生時に,対象となる遺産が特定の相続人に承継されると解されています。
本来的な遺産分割方法の指定よりも,むしろ特定財産承継遺言を用いる場合の方が多いように思われます。