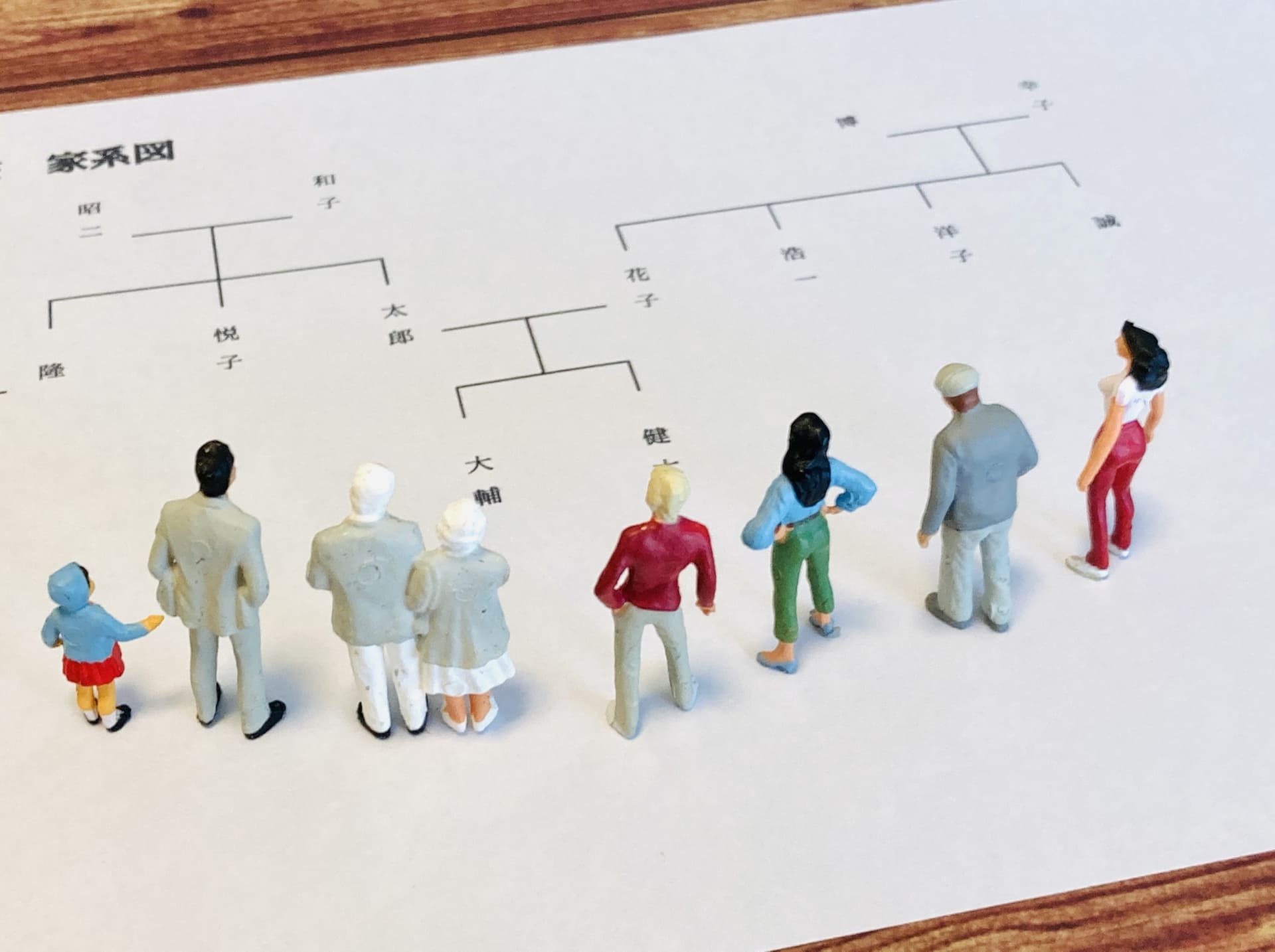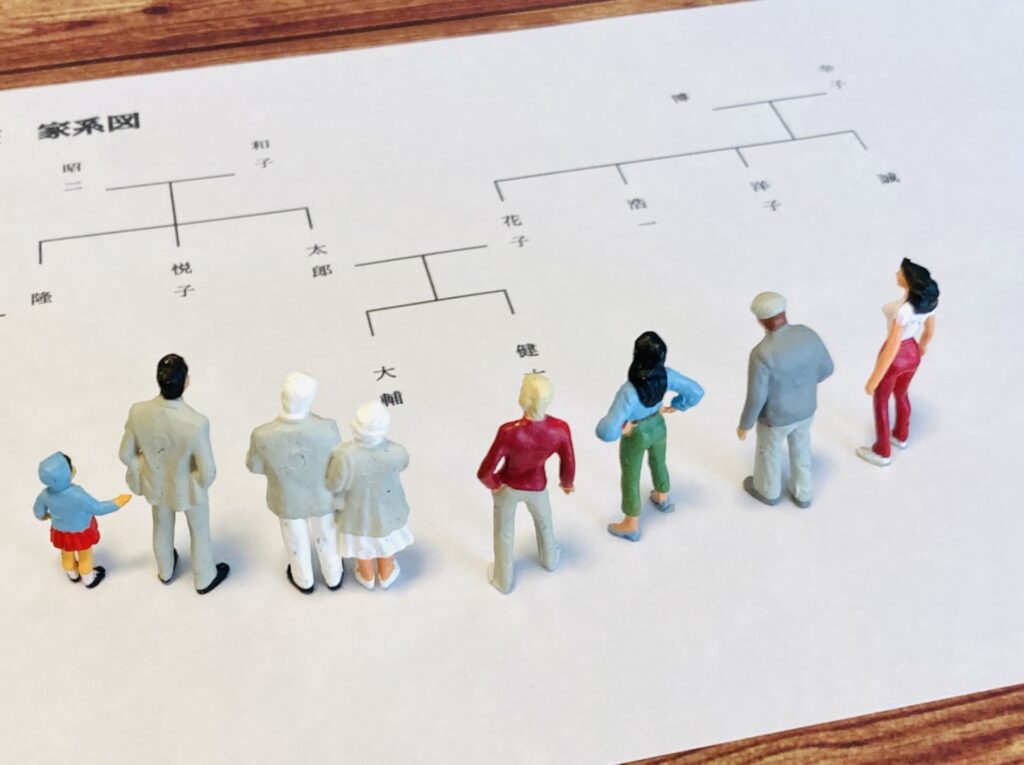
遺言の方式には「普通方式」と「特別方式」があります。
普通方式の遺言としては,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。特別方式の遺言としては,遺言者が死に瀕しているなどの緊急状態にある場合に認められる特別方式と遺言者が交通の遮断された地域にいる場合に認められる特別方式があります。
遺言の要式行為性
民法 第960条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
遺言を作成しておけば,遺言を作成した方(遺言者・被相続人)の意思を,相続開始後に反映してもらうことができます。
もっとも,遺言は「要式行為」です。要式行為とは,単に意思表示をしただけでは足りず,法律で定められた一定の方式を履践しなければ,法的な効果を生じない法律行為のことをいいます。
遺言は,単に口頭で相続の希望を述べたり,ただ紙に書いておいたりしただけでは,遺言としての効力を生じません。
法律で定められた遺言の方式に従って遺言をしなければ,法律上の遺言としての効力を生じないということです。
遺言の作成方式
民法 第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は,この限りでない。
遺言の作成方式として代表的なものは,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの方式です。これらの遺言作成の方式のことを「普通方式」といいます。
もっとも,普通方式以外にも,「特別方式」と呼ばれる遺言作成の方式があります。特別方式は,普通方式による遺言をするのが困難な場合に認められるものです。
例えば,遺言者が死に瀕しているような緊急状態にある場合や,交通が途絶している場所にいるような場合に認められる方式です。
普通方式の遺言
前記のとおり,普通方式の遺言には,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つの方式があります(どの方式を選択すればよいのかについては,個別の状況によって異なってきます。)。
自筆証書遺言
民法 第968条
第1項 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
第2項 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、の目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名し、印を押さなければならない。
第3項 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言は,遺言者が遺言書の全文・氏名・日付を自書して,これに押印するという方式の遺言です(民法968条)。
自筆証書遺言は,他の方式と異なり,公証人や証人の立ち合いなしに作成できる簡便な方式です。公証人に対する費用等もかかりません。そのため,最も多く利用されている遺言の方式です。
もっとも,上記のとおり,自書(要するに手書き)が必要ですので,ワープロやパソコンで作成することはできません。
ただし,遺言書に添付する相続財産目録については,すべてのページに自書による署名および押印をしてあれば,パソコンで作成したり,預貯金通帳のコピーや不動産登記事項証明書をもって代えることができます(民法968条2項)。
また,自筆証書の場合,相続開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となります。
さらに,客観的な立場にある人の立会いがないため,相続後に,遺言内容や有効性が争われ,遺言が覆されることがあり得るというデメリットはあります。
そのため,自筆証書遺言を作成する場合には,後に有効性で相続人間に紛争が起きないように,作成時に医師に立ち会ってもらうとか,作成後に弁護士等や第三者など信頼できる人(または、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する。)に預かっておいてもらうなどの措置をとっておく必要があるでしょう。
公正証書遺言
民法 第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
第1号 証人二人以上の立会いがあること。
第2号 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
第3号 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
第4号 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
第5号 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言とは,2人以上の証人の立会いの下で,遺言者が公証人に遺言の方式を口頭で伝え,公証人はそれを筆記して,筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させ,遺言者と立ち会った証人がその正確性を承認した後に署名・押印をし,公証人が方式に従って作成したものであることを付記して署名・押印するという方式の遺言です(民法969条)。
公正証書遺言は,公正証書として作成されますから,公証役場に赴いて公証人に作成してもらう必要があります。また,2人以上の証人を探すことも必要です。
したがって,費用や手間がかかるというデメリットがあります。
もっとも,自筆証書や秘密証書と異なり,作成に客観的な立場の人が立ち会ってくれる上,法律の専門家である公証人が作成してくれるので,相続開始後も相続の有効性が覆される可能性がかなり小さくなります。
しかも,検認手続が不要で,相続開始後すぐに遺言の執行を開始することができるというメリットもあります。
秘密証書遺言
民法 第970条
- 第1項 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
- 第1号 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
- 第2号 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
- 第3号 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 第4号 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
- 第2項 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密証書遺言とは,遺言者が遺言書に署名・押印して,それを封じ,遺言書に押したのと同じ印章で押印して封印し,その封書を公証人1人と2人以上の証人の前に提出して,自分の遺言書であること等を申述し,公証人が遺言書提出日と申述内容を封書に記載して,遺言者・公証人・証人が署名・押印するという方式の遺言です(民法970条)。
秘密証書遺言を作成しておけば,その遺言の内容を,相続開始後に検認するまで,誰にも知られずに済みます。また,自書は求められていませんから,ワープロやパソコンで作成することもできます。
もっとも,上記のとおり,公証人に署名等をしてもらう必要があります。また,2人以上の証人も必要ですので,手続としては簡便とはいえませんし,それなりの費用もかかります。相続開始後に検認手続も必要です。
しかも,遺言書を作成すること自体には客観的な立会者がいませんので,自筆証書の場合と同様に,相続開始後に遺言内容や有効性が争われ,遺言が覆される可能性があるというデメリットもあります。
秘密証書遺言は,公正証書遺言と同様の手間がかかる割には,自筆証書遺言と同様なデメリットがあるため,実際には,ほとんど利用されていないのが現状のようです。
秘密証書遺言を選択するのは,相続人に知られると生前に紛争が起きる可能性が大きいなど,秘密とする必要性が高い場合に限られてくるでしょう。
特別方式の遺言
前記のとおり,特別方式の遺言としては,遺言者が死に瀕しているなど緊急状態にある場合や交通が遮断された地域にいる場合に認められる例外的な方式です。
遺言者が死に瀕しているなどの緊急状態にある場合に認められる特別方式としては,死亡危急者遺言(民法976条)と船舶遭難者遺言(民法979条)があります。
また,遺言者が交通の遮断された地域にいる場合に認められる特別方式としては,伝染病隔離者の遺言(民法977条)や在船者の遺言(民法978条)があります。