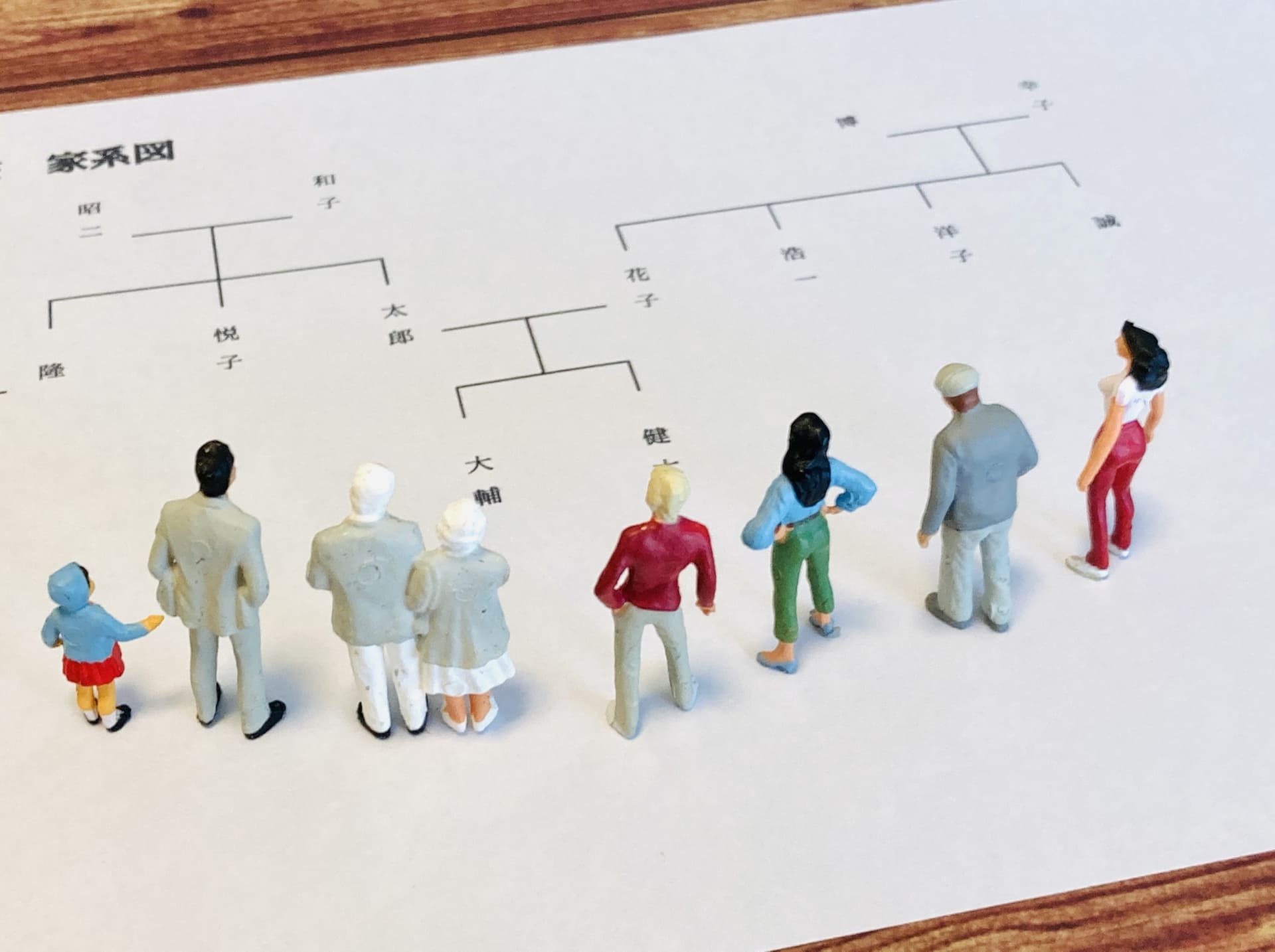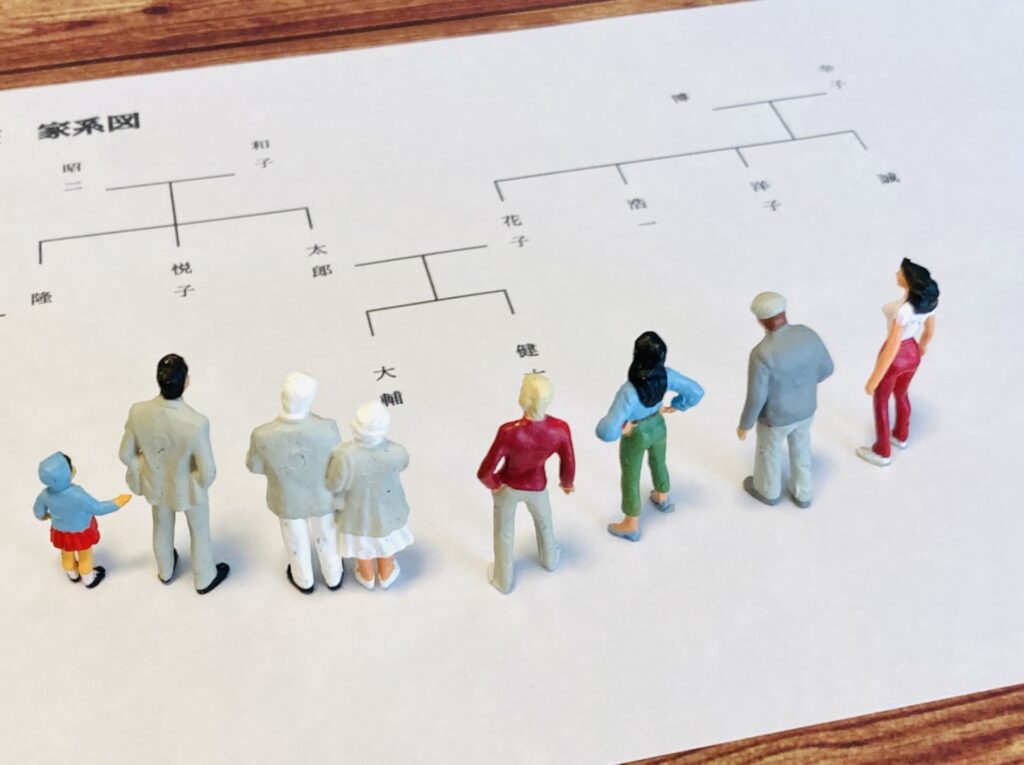
遺言執行者とは,遺言の執行を行う者,つまり,遺言の内容を実現するために必要な事務処理を行う者のことをいいます。遺言執行者には,自然人だけでなく,法人もなることができます。ただし,未成年者および破産者はなることができません(民法1009条)。
遺言執行者は,遺言で指定することができます(同法1006条1項)。遺言執行者がいない場合等には,利害関係人は,家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を請求できます(同法1010条)。
遺言執行者の職務は,遺言の内容を実現することにあります。この職務を遂行するため,遺言執行者は,相続財産の管理,その他遺言の執行に必要となる一切の行為をする権限を有します(同法1012条1項)。
遺言執行者とは?
遺言には,その内容を実現するために,遺言の効力発生後に一定の行為をしなければならない遺言事項があります。例えば,不動産を遺贈する場合の不動産所有権移転登記などです。
この場合に,遺言を実現するために何らかの行為をしなければならない事項について,その行為をすることを遺言の執行と言います。
そして,遺言の執行を行う者,つまり,遺言の内容を実現するために必要な事務処理を行う者のことを「遺言執行者」と言います。
遺言執行者となることができる資格
遺言執行者になることができるのは,自然人に限られません。法人でも遺言執行者になることができます。
この自然人遺言執行者には,第三者だけでなく,公平を害する事情の無い限り,相続人もなることができると解されています。
ただし,未成年者および破産者は,遺言執行者になることはできません(民法1009条)。他方,成年被後見人,被保佐人および被補助人は,遺言執行者になることができます。
遺言執行者の指定・選任
遺言者は,遺言で,遺言執行者を指定できます。また,遺言で,遺言執行者の選任を第三者に委託することも可能です(民法1006条1項)。
ただし,指定されたからと言って,その指定された人は必ず遺言執行者にならなければならないものではありません。当然,遺言執行者になることを承諾するか否かは指定された人の自由です。
遺言執行者がいない場合や辞任等によっていなくなった場合,相続人等の利害関係人は,家庭裁判所に対して遺言執行者を選任するよう請求することができます(民法1010条)。
選任の請求を受けた家庭裁判所は,選任の要否等を判断して,遺言執行者を選任します。不要と判断した場合には,選任の請求は却下されます。
なお,家庭裁判所による選任の場合であっても,選任された人は,遺言執行者になることについて諾否は自由です。
遺言執行者の職務
遺言執行者は,就任を承諾した場合,直ちに任務を開始し(民法1007条1項),任務開始後遅滞なく,相続人に対して遺言の内容を通知しなければなりません(同条2項)。
遺言執行者の任務(職務)とは,遺言の内容を実現することです。
したがって,遺言者の意思に忠実に職務を遂行する必要があります。相続人の利益を図るためだけに職務を遂行するわけではありません(最三小判昭和30年5月10日)。
そのため,遺言執行者は,仮に遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合,相続人の利益を考慮する必要はなく,遺言者の意思を実現するために職務を遂行すれば足りると解されています。
遺言執行者の権限
遺言執行者は,遺言の内容を実現するという職務を遂行するため,相続財産の管理,その他遺言の執行に必要となる一切の行為をする権限を有します(民法1012条1項)。
この遺言執行者の権限には,訴訟追行権も含まれます。遺言執行者は,遺言執行に関する事件について,法定訴訟担当として原告または被告となり,自己の名で訴訟を追行することになります(最二小判昭和51年7月19日)。
また,遺言執行者は,自己の責任で,第三者を復任して職務を行わせることができます 。ただし,第三者に復任するやむを得ない事由がある場合には,選任・監督についてのみ責任を負います(民法1016条)。
なお,無限定に相続財産の管理やその他の行為をすることができるわけではありません。遺言執行者の権限の内容や範囲は,遺言の文言やその解釈によって定められます。
遺贈の場合の権限
遺言執行者がある場合,遺贈を履行できるのは,遺言執行者のみに限られています(民法1012条2項)。
そのため,遺贈の目的物が特定の物や債権である場合,遺言執行者は,受遺者が対抗要件を備えるために必要な行為をする権限を有します。
また,不特定物の場合には,その物を給付するために必要な特定等の行為をして受遺者に引き渡し,受遺者が対抗要件を備えるために必要な行為をする権限を有します。
特定財産承継遺言の場合の権限
特定財産承継遺言の場合,遺言の効力発生時に特定された遺産が特定の相続人(受益相続人)に相続されるので,遺言で特別に職務とする旨の定めがない限り,当該遺産について,遺言執行者が管理したり引き渡しをするなどの職務を遂行する権限はありません。
ただし,遺言に別段の意思表示がある場合を除いて,遺言執行者は,特定財産承継遺言であっても,受益相続人が特定遺産につき対抗要件を備えるために必要な行為はすることができるとされています(民法1014条2項,4項)。
また,遺言に別段の意思表示がある場合を除いて,遺言執行者は,特定財産承継遺言であっても,特定遺産が預金・貯金である場合,その預金・貯金を払い戻したり,その預金・貯金の全部が特定財産承継遺言の目的である場合であれば,さらに解約まですることができるとされています(民法1014条3項,4項)。
遺言執行者の義務
遺言執行者は,その職務遂行について以下のような義務を課せられます。
- 就任承諾後,直ちに任務を開始する義務(民法1007条1項)
- 任務開始後,遅滞なく相続人に対して遺言内容を通知する義務(民法1007条2項)
- 遅滞なく財産目録を作成して相続人に交付する義務(民法1011条)
- 遺言の内容を実現するため,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする義務(民法1012条1項)
- 善管注意義務(民法1012条3項,644条)
- 相続人に対する報告義務(民法1012条3項,645条)
- 金銭その他の物の引渡し・権利の移転義務(民法1012条3項,646条)
- 金銭を自己のために消費した場合の利息の支払い・損害賠償義務(民法1012条3項,647条)
- 職務終了後の緊急処分義務(民法1020条,654条)
遺言執行者がした行為の効力
遺言執行者が,その権限内において遺言執行者であることを示してした行為は,相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015条)。
したがって,例えば,遺言執行者が遺産の土地を売却した場合,その売買契約の効力は相続人に生じることになります。
他方,遺言執行者がある場合,相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず,そのような行為をしても無効となります(民法1013条1項,2項本文)。
ただし,相続人が行為をした相手方が善意である(相続人に権限がないことを知らなかった)場合には,無効であることを相手方に主張することはできません(民法1013条2項ただし書き)。
上記のとおり,遺言執行者がある場合,相続人の財産処分行為等は無効となりますが,相続人の債権者は,相続財産に対して権利を行使することができます(民法1013条3項)。
遺言執行者の辞任・解任
遺言執行者が任務を怠ったとき,またはその他正当な事由があるときは,相続人等の利害関係人は,家庭裁判所に対して遺言執行者の解任を請求することができます(民法1019条1項)。
解任請求を受けた家庭裁判所は,遺言の公正な実現を期待できない程度の任務懈怠や解任するのに正当な事由があると認めた場合には,その遺言執行者を解任する決定をします。
また,遺言執行者は,家庭裁判所に対して自ら辞任を請求することもできます。ただし,正当な事由がなければ,辞任は認められません(民法1019条2項)。