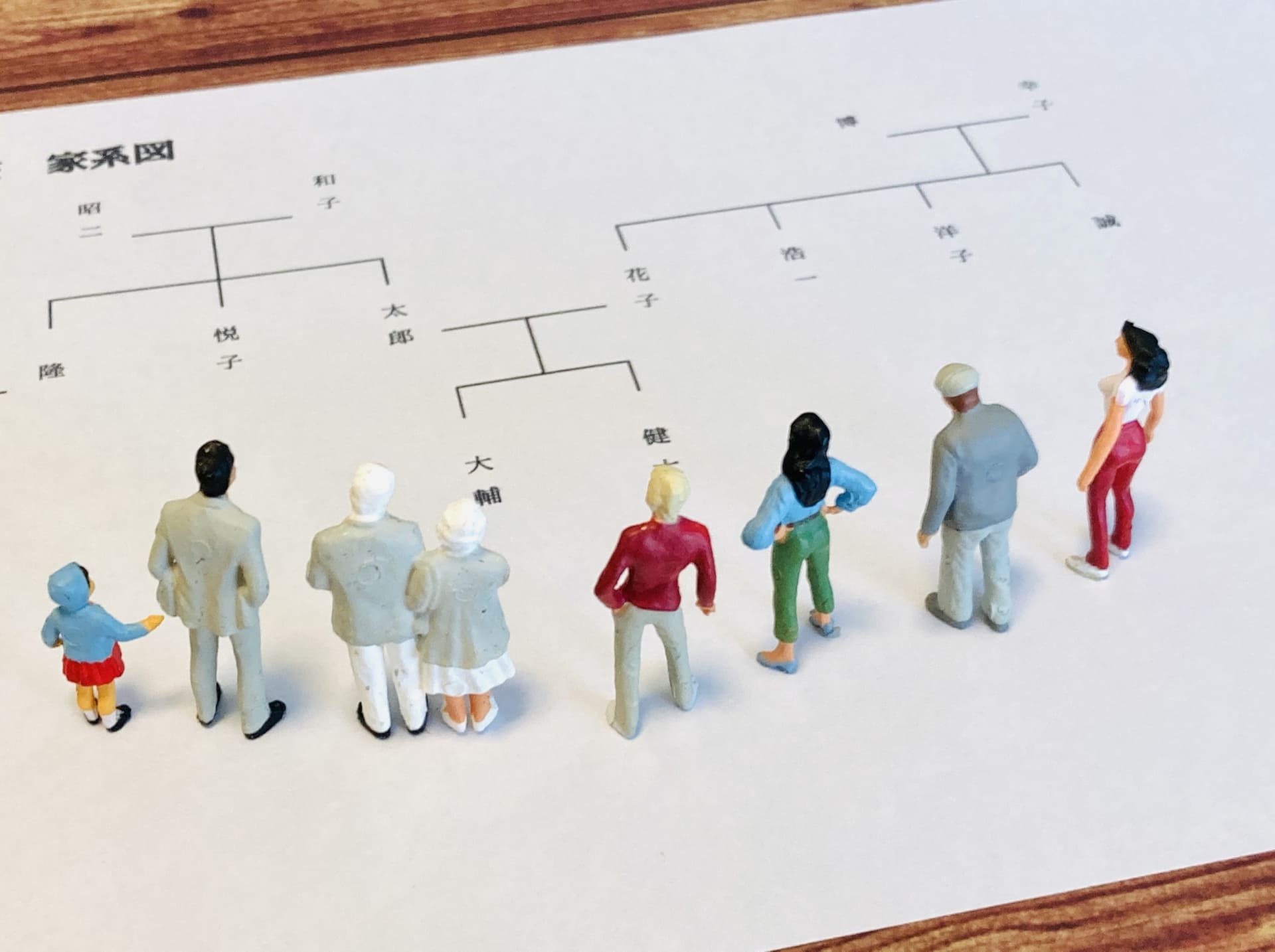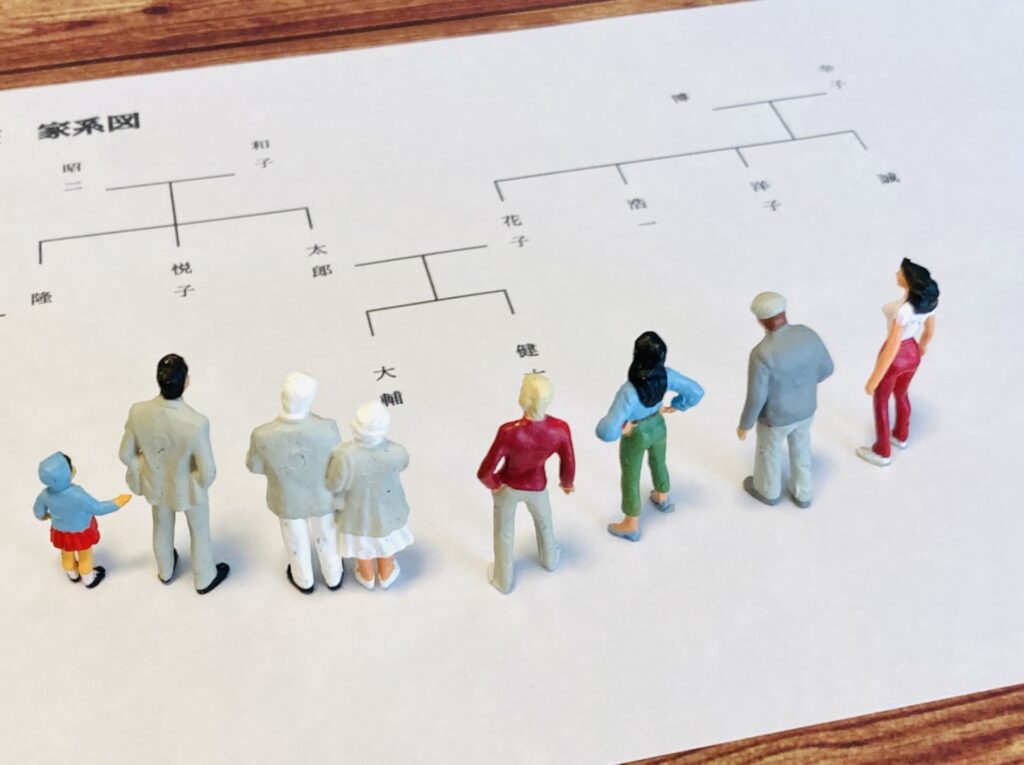
特定財産承継遺言とは,「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」のことをいいます(民法1014条2項参照)。
簡単に言うと,共同相続人のうちのある特定の相続人に対し,特定の相続財産を,遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。
判例・通説(遺産分割効果説)によれば,相続させる旨の遺言は,相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず,遺言の効力発生時に,対象となる相続財産が特定の相続人に承継される効果を生じると解されています。
ただし,民法改正(2019年7月1日施行)により,承継した相続財産のうち法定相続分を超える部分については,登記がなければ第三者に対抗できないものとされました(民法899条の2)。
特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)とは?
遺言の定め方として,共同相続人のうちの特定の相続人に対し,特定の遺産(相続財産)を「相続させる」とするものがあります。一般には「相続させる旨の遺言」と呼ばれています。
改正民法(2019年7月1日施行)では,「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」すなわち「特定財産承継遺言」として規定されています(民法1014条2項参照)。
特定の相続財産を特定の相続人に譲りたいという場合には,この相続させる旨の遺言を用いるのが一般的でしょう。
「相続させる旨の遺言」が生まれた経緯
ある特定の遺産を,ある特定の相続人だけに承継させたいという場合,遺贈をするということが考えられます。すなわち,ある特定の財産を「●●に遺贈する」というように遺言するということです。
ところが,遺贈の場合,承継させたい財産が不動産であると,他の共同相続人とともに不動産の所有権移転登記をしなければなりません。
そのため,他の共同相続人が反対すると,登記を移転させるのが難しくなるという難点があります。
これに対して,相続という形での承継であれば,その特定の不動産を承継した相続人が,他の共同相続人がいなくても単独で登記を移転できます。
また,かつては,相続人に対する遺贈の場合の方が,相続によって承継される場合よりも,かなり不動産登録免許税が高く設定されていました(現在では,相続人に対する遺贈も相続も登録免許税は同額になっています。)。
そのため,遺言者(被相続人)からは,遺贈ではなく,何とか,相続という形で,特定の相続人に対して特定の財産を承継させたいという希望がありました。
そこで実務において生み出された技法が,「相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)」です。
登記実務においても,この相続させる旨の遺言が尊重され,遺贈ではなく相続させる旨の遺言である場合には,その承継を受けた相続人が単独で所有権移転登記をすることができ,しかも,登録免許税も相続として扱われるようになりました(昭和47年4月17日民事甲1442号民事局長通達)。
したがって,現在では,ある特定の相続人に対して,相続財産のうちの特定の財産(特に不動産)を譲り渡したいという場合には,遺贈の方式ではなく,相続させる旨の遺言とするのが通常でしょう。
※相続人でない第三者に相続財産を譲り渡すには,遺贈の方法をとる以外にありません。相続人ではないのですから,相続させる旨の遺言はもちろんできません。
特定財産承継遺言の効力
前記のとおり,登記実務上では,特定財産承継遺言は相続の効力を有するものと同様に扱われていました。
もっとも,法律上の議論においては,特定財産承継遺言をどのように扱うべきかという点について各種の見解がありました。
遺産分割方法指定説
特定財産承継遺言の効力をどのように解するべきかについての考え方の1つに「遺産分割方法指定説」があります。
遺産分割方法指定説は,特定財産承継遺言を,遺産分割方法の指定と考える見解です。
遺産分割方法指定説によれば,特定財産が不動産である場合,その承継を受けた特定の相続人が単独で登記を移転できることになります。
しかし,遺産分割方法の指定と考えると,遺産分割が成立するまでは,確定的な権利を取得できないということになり,遺言の趣旨に反することになる可能性があり得ます。
特定遺贈説
特定財産承継遺言の効力をどのように解するべきかについての考え方の1つに「特定遺贈説」があります。
特定遺贈説は,特定財産承継遺言とは,特定の財産を遺贈するものにすぎないという見解です。要するに,前記の実務的取扱いを認めないという見解です。
特定遺贈説は,遺産分割を経ずに相続開始時に特定の財産が特定の相続人に承継されるというのは,遺産分割手続を定める法の趣旨に沿わず,また,そもそも遺産分割方法の指定とは特定の財産を特定の相続人に承継させるというものではないということなどを根拠としています。
特定遺贈説は,現在でも有力な学説です。
特定遺贈説によれば,受贈者である相続人は,相続開始によってその遺贈財産の所有権を取得できます。ただし,所有権移転登記をするには他の共同相続人の協力が必要となります。
遺産分割効果説(判例・通説)
現在の判例・通説は,「遺産分割効果説」です。判例でいえば,最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決です。
遺産分割効果説は,相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は,遺言で遺贈であるといえるような事情の無い限り,原則として遺産分割方法の指定であるとします。
ただし,遺産分割方法指定説とは異なり,相続人間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず,遺言の効力発生時に,対象となる遺産が特定の相続人に承継されるとする見解です。
現在の実務は,この遺産分割効果説で動いており,改正民法も,遺産分割効果説を採用しています。
したがって,相続させる旨の遺言がなされた場合には,それに反するような遺産分割はできなくなります。
しかも,遺産分割を待つまでもなく,遺言の効力発生時(通常は相続開始時)に,その遺言どおりに特定の財産が特定の相続人に承継されるという効果が発生することになります。
そして,その特定財産の承継を受けた相続人は,その財産が不動産であれば,単独で所有権移転登記ができるということになります。
特定財産承継遺言と第三者対抗要件の要否
民法 第899条の2
- 第1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
- 第2項 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
前記のとおり,遺産分割効果説によれば,特定財産承継遺言をした場合,その遺言の効力発生時に,その遺言どおりに特定の遺産が特定の相続人に承継されるという効果が発生します。
この点,従前は,承継を受けた相続財産が不動産であった場合,承継を受けた特定の相続人は,遺言によって取得した不動産を,登記なくして第三者に対抗できると解されていました(最二小判平成14年6月10日)。
もっとも,登記が具備されていないのに,すべて第三者に対抗できるとしたのでは,登記による公示を信頼して取引をした第三者に不利益をもたらすおそれがあり,取引の安全を害します。
そのため,民法改正によって,特定財産承継遺言によって法定相続分を超える部分を承継した場合であっても,承継した相続人は,その法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないものとされました(民法899条の2)。
なお,法定相続分の範囲内の部分については,従前どおり対抗要件なくして第三者に対抗できます。
もっとも,この民法899条の2の規定が適用されるのは,2019年7月1日以降に相続が開始した場合です。
2019年7月1日より前に開始していた相続については,従前どおり,対抗要件を備えなくても承継した相続分の全部を第三者に対抗できることになります(ただし,債権については例外があります。)。