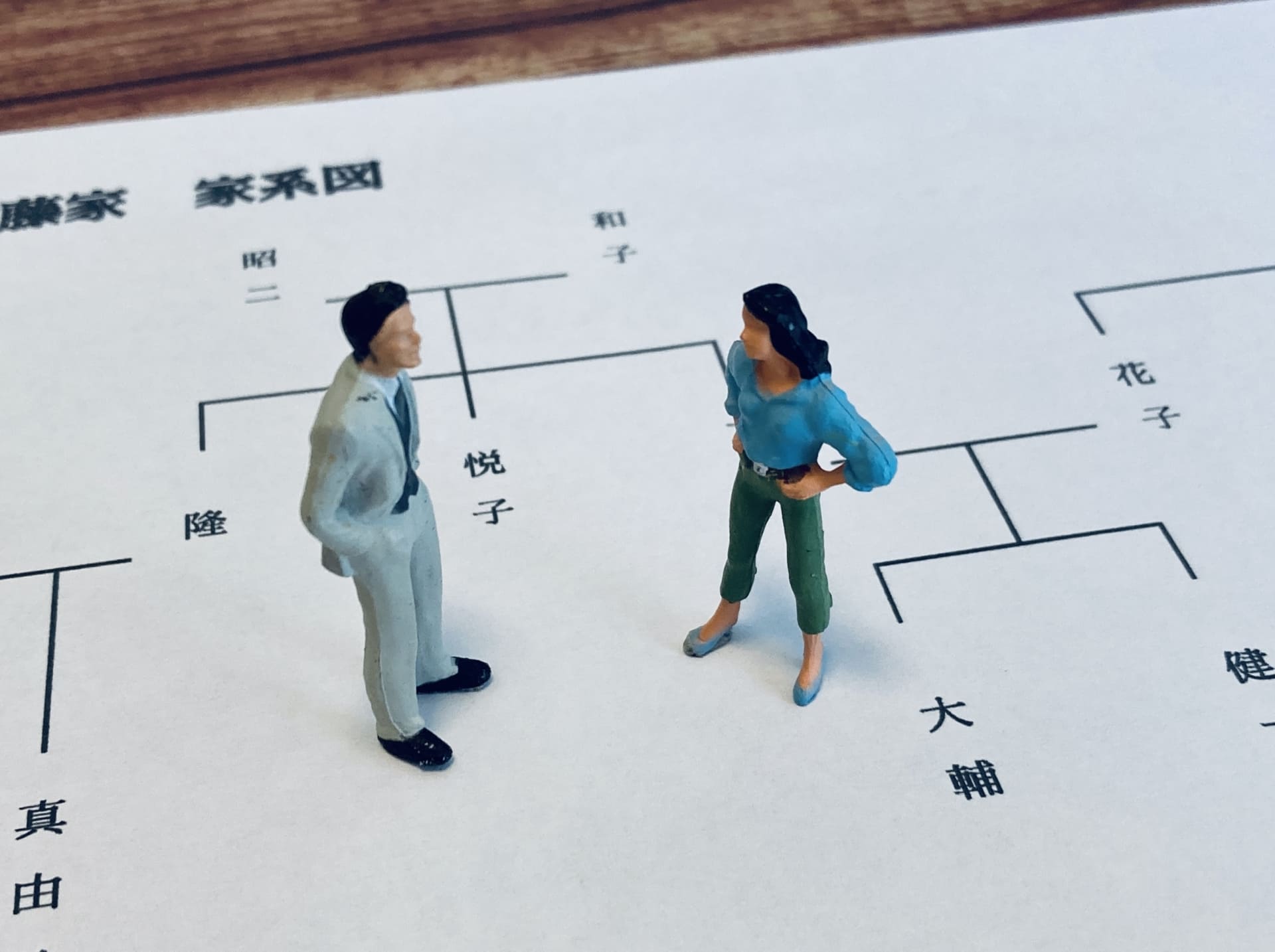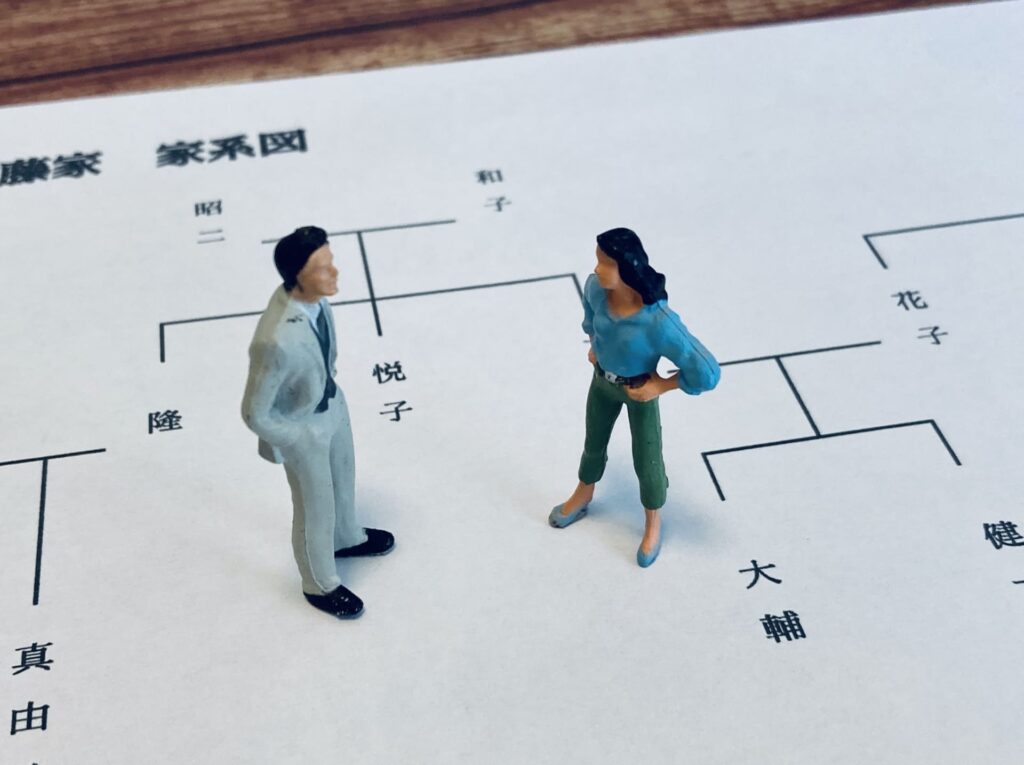
2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について,遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合,遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は,その遺贈や贈与を受けた受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
これを「遺留分侵害請求」といいます(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求とは
民法 第1046条
- 第1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
- 第2項 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
- 第1号 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
- 第2号 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
- 第3号 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
兄弟姉妹を除く法定相続人には,相続財産に対する最低限度の取り分として,遺留分(いりゅうぶん)が保障されています(民法1042条)。
遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合,遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は,その遺贈や贈与を受けた受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と言います。
従前は,遺留分を侵害された場合,遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)によって侵害された分を取り戻すこととされていました。
遺留分減殺請求の場合,減殺請求によって遺留分を侵害する範囲で遺贈や贈与が失効し,その部分の相続財産が遺留分権利者に戻されるという現物移転の形をとっていました。
しかし,減殺請求の方法によると,相続財産が共有となることが多くあり,その後さらに共有物分割の争いが生じてしまい,相続紛争が終結しないという問題がありました。
そこで,改正民法(令和元年7月1日施行)では,現物移転を原則とする遺留分減殺請求から,金銭の支払いによって遺留分侵害額を填補する遺留分侵害額請求へと大幅に変更されました。
要するに,遺留分の問題は,専ら金銭的に解決することになったということです。
この遺留分侵害額請求は,2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について適用されます。
※なお,2019年(令和元年)7月1日より前に開始した相続の場合は,従前どおり,遺留分減殺請求によって遺留分権を行使することになります。
遺留分侵害額請求権の法的性質
遺留分侵害を理由として相手方に遺留分権を主張することができる実体法上の地位を「遺留分侵害額請求権」と言います。
この遺留分侵害額請求権の法的性質は,形成権です。遺留分を侵害された相続人から相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示によって,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを目的とする金銭債権が発生します。
つまり,厳密に言うと,形成権である遺留分侵害額請求権によって,これとは別の権利である金銭債権が発生するという仕組みなのです。
したがって,遺留分を侵害された相続人は,まず遺留分侵害額請求権の意思表示を行い,その意思表示によって発生した金銭債権を行使して,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けることになります。
ただし,実際には,遺留分侵害額請求権の行使と同時に金銭の支払いも請求することになるでしょう。
遺留分侵害額の請求権者
遺留分侵害額請求ができるのは,遺留分権利者とその承継人です(民法1046条1項)。
遺留分権利者となれるのは,「兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条1項柱書)。したがって,相続人であったとしても,兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることはできません。
この兄弟姉妹以外の相続人の承継人も,遺留分侵害額の請求権者となります。例えば,遺留分権利者である相続人を相続した相続人などがこれに当たります。
遺留分侵害額請求の相手方
遺留分侵害額請求の相手方は,遺留分を侵害する遺贈を受けた受遺者または贈与を受けた受贈者です(民法1046条1項)。
相続分の指定を受けた相続人および特定財産承継遺言による受益相続人は,ここで言う受遺者に含まれます(民法1046条1項括弧書き)。
死因贈与については,争いはあるものの,贈与に含まれ,ただし,生前贈与よりも先に遺留分侵害額請求の対象になると解されています(遺留分減殺の場合について,東京高判平成12年3月8日)。
遺留分侵害額を負担する順位
民法 第1047条
- 第1項 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
- 第1号 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
- 第2号 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- 第3号 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
- 第2項 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
- 第3項 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
- 第4項 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
- 第5項 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
受遺者と受贈者があるときは,まず受遺者が負担し,それでも不足する場合に受贈者が負担します(民法1047条1項1号)。遺贈を受けた者から負担をすべきということです。
受遺者が複数人いる場合は,遺贈の目的の価額の割合に応じて各受遺者が負担します(民法1047条1項2号)。
受贈者が複数人いる場合は,後の贈与の受贈者から順次前の贈与の受贈者が負担します(民法1047条1項3号)。つまり,時期的に新しい贈与の受贈者から先に負担していくということです。
贈与の時期が同時期である場合には,贈与の目的の価額の割合に応じて同時期の受贈者が負担します(民法1047条1項2号)。
なお,贈与に生前贈与と死因贈与がある場合には,死因贈与は,遺贈に次いで,生前贈与よりも先に負担することになると解されています。
遺留分侵害額請求を負担する順番は、受遺者(遺贈)→受贈者(死因贈与)→受贈者(生前贈与)の順です。受遺者が複数人いるときは、遺贈目的物の価額の割合に応じて各受遺者が負担し、受贈者が複数人いるときは、新しい贈与の受贈者から先に負担します。贈与の時期が同じ場合は、贈与目的物の価額の割合に応じて各受贈者が負担します。
相手方の利益の保護
遺留分侵害額請求を受けた受遺者や受贈者は,その遺留分侵害額に相当する金銭を支払わなければならないことになります。とはいえ,すぐには金銭を用意できない場合もあるでしょう。
その場合,請求を受けた受遺者または受贈者は,裁判所に対し,金銭の支払いの全部または一部について相当の期限を許与するよう請求できます(民法1047条5項)。
また,遺留分侵害額の請求者と相手方である受遺者または受贈者の間で,金銭の支払いではなく,相続財産の現物を支給するという代物弁済の合意をすることは可能です。
請求できる金額(遺留分侵害額)
遺留分侵害額請求によって請求できる金額は,文字どおり「遺留分侵害額」です。
遺留分侵害額は,以下の手順で計算します。
まとめると,遺留分侵害額の算定式は以下のとおりとなります。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求の方法に,特別な規定はありません。
前記のとおり,遺留分侵害額請求権は形成権ですから,相手方に対して遺留分侵害額を請求するとの意思表示をすれば足ります。この段階では,金額を明示して意思表示する必要はありません。
実務では,意思表示の方法として,配達証明付きの内容証明郵便によって行うの通常でしょう。
遺留分侵害額請求の意思表示をしたことにより発生する金銭債権についても特別な定めはありませんので,他の金銭債権と同じように,裁判外での交渉や調停・訴訟によって請求することになります。
遺留分侵害額請求は,家庭に関する事件であり,家事調停をすることができる事件に該当するため,調停前置主義の適用があると解されています(家事事件手続法257条1項)。
したがって,遺留分侵害額請求をする場合には,まず家事調停を申し立てる必要があります。
調停において話がつかなかった場合には,遺留分侵害額請求の訴訟を提起することになります。この訴訟の管轄は,家庭裁判所ではなく,簡易裁判所または地方裁判所です。
請求する金額が140万円以下である場合は簡易裁判所に,140万円を超える場合には地方裁判所に訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求の期限
民法 第1048条
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
遺留分侵害額請求権は,相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間が経過すると,時効によって消滅してしまいます(民法1048条前段)。
また,相続開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知らなかった場合でも,相続開始時から10年間が経過すると,遺留分侵害額請求をすることができなくなってしまいます(民法1048条後段)。
したがって,遺留分侵害額請求を考えている場合には,これらの期限に注意しなければいけません。
ただし,前記のとおり,遺留分侵害額請求権と,遺留分侵害額請求によって発生する金銭債権は別の債権です。そのため,遺留分侵害額請求の期限と金銭債権の期限は別です。
したがって,相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間ないし相続開始時から10年間の期限内にしなければならないのは遺留分侵害額の請求だけであり,それによって生じる金銭債権までこれらの期限内にしなければならないわけではありません。
遺留分侵害額請求により生じる金銭債権には,一般的な債権の消滅時効が適用されます。
つまり,金銭債権は,「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方が経過したときに,時効により消滅します。
2019年(令和元年)7月1日より前に相続が開始していた場合
前記のとおり,遺留分侵害額請求の適用があるのは,2019年(令和元年)7月1日以降に相続が開始した場合です。
相続の開始が2019年(令和元年)7月1日よりも前である場合には,遺留分侵害額請求ではなく,改正前の民法に規定されていた遺留分減殺請求によって遺留分権を行使することになります。