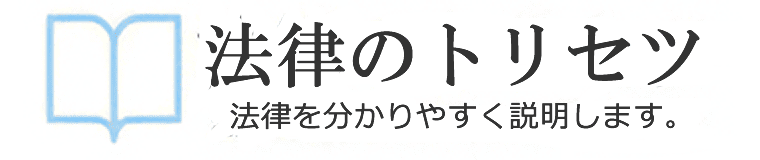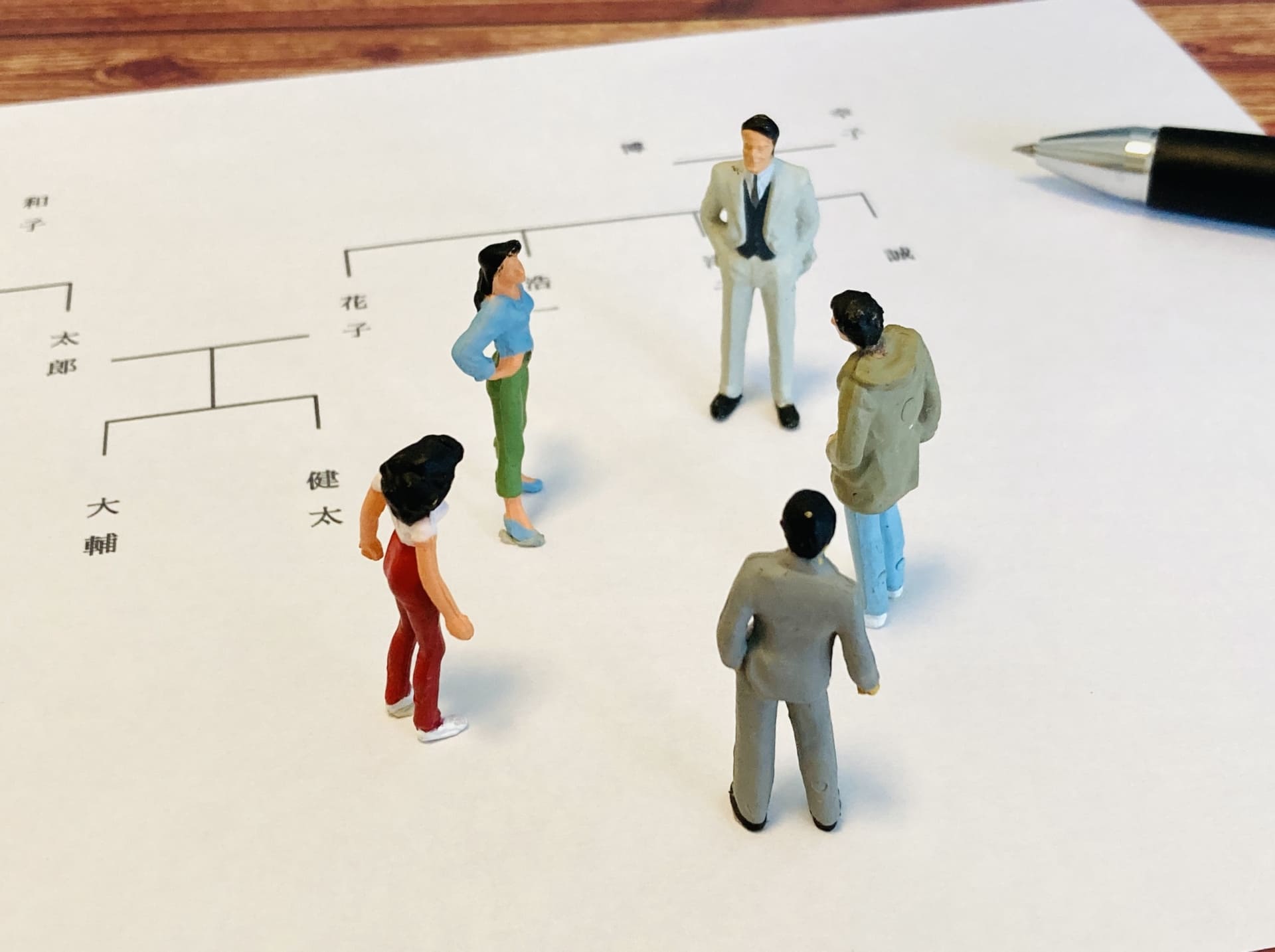この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
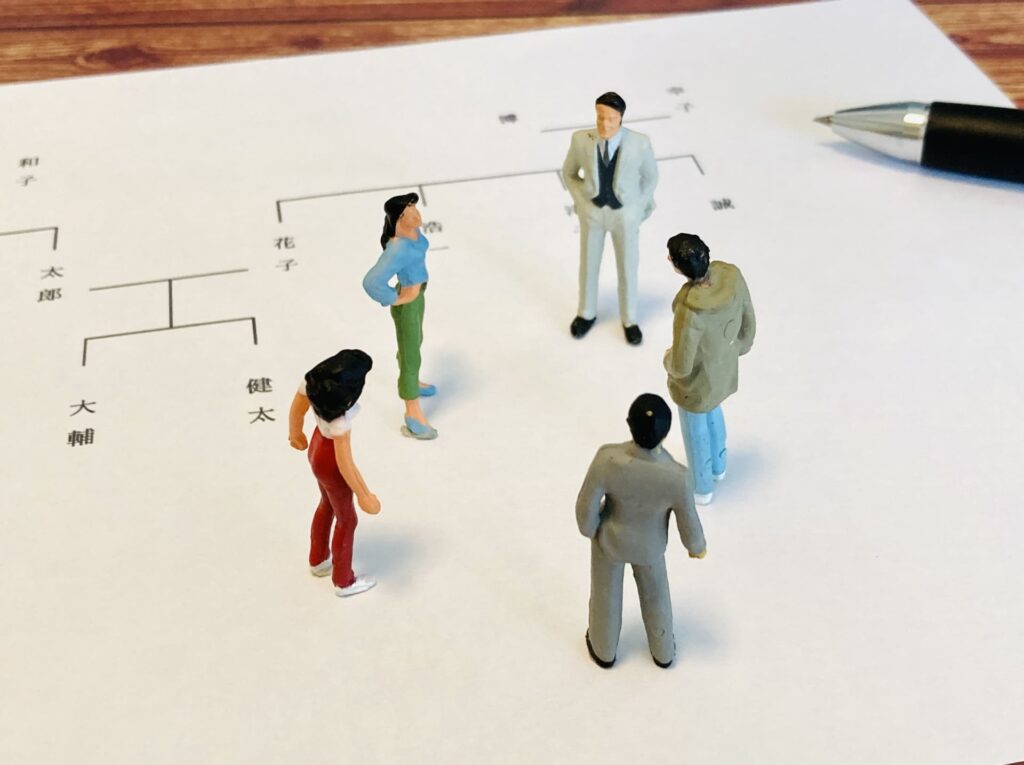
相続人が、相続をしない旨の意思表示をすることを「相続放棄」といいます。相続放棄をすると、放棄をした人は、相続開始のはじめから相続人とならなかったものとみなされます。
相続放棄とは?
民法 第939条
- 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
遺産相続が開始されると,相続人は,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)を包括的に承継することになります(民法896条)。
この相続財産には,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含まれます。そのため、相続によって,相続人は,被相続人が負っていた借金などの負債も受け継がなければならなくなります。
つまり、その借金を相続人が支払っていかなければならないのです。
相続した財産が,プラスの財産の方が大きいのであれば,それを使って返済に充てれば問題はないでしょう。
しかし,マイナスの財産の方がプラスの財産よりも大きかった場合には,相続財産だけでは支払いきれません。
この場合,負債を相続した相続人が,相続財産だけではなく,自分の固有の財産を使ってでも支払う必要があります。
もちろん,相続財産に先祖代々の不動産があって,どうしても相続せざるを得ないなど、やむを得ない事情が存在することもあるでしょう。
しかし、そのような事情がないにもかかわらず,ただ相続しただけで,被相続人の負債を全面的に背負わなければならなくなるのは,相続人に大きな不利益を被らせることになります。
そこで,法は,相続人に,相続しないこともできる選択権を与えています。この,相続人による相続しない旨の意思表示を「相続放棄」といいます。
相続放棄をすると,その放棄をした人は,相続開始のはじめから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。つまり,相続財産を受け継がなくてよくなるのです。
ただし,相続放棄の場合には,すべて相続財産を相続しないことになります。そのため、マイナスの財産(負債)だけでなく、プラスの財産(資産)も承継することはできなくなります。
相続放棄の方法
民法 第938条
- 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄は,単に「相続放棄する」と意思表示をすれば,効果が生じるものではありません。一定の手続を履践する必要があります。
具体的には,家庭裁判所に,相続放棄の申述をする必要があります(民法938条)。申述をする家庭裁判所は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば,被相続人の方が東京都千代田区に住んでいたのであれば,東京家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の熟慮期間
民法 第921条
- 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 第1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 第2号 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 第3号 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法 第915条
- 第1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続放棄をするに当たって、注意しなければならないのは「熟慮期間」です。
相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄(または限定承認)の申述をしなければ,単純承認をしたものとみなされ(法定単純承認),それ以降,相続放棄できなくなってしまいます(民法921条2号、915条1項本文)。この期間のことを熟慮期間といいます。
したがって,相続放棄を検討されている方は,この熟慮期間(相続開始を知った時から3か月以内の期間)には,十分に注意をしておく必要があります。
ただし,相続財産が不明確で相続放棄をすべきかどうか判断が付かない場合には,その調査のために,一定の期間,熟慮期間を伸長してもらえる場合があります(民法915条1項ただし書き)。
この熟慮期間の伸長は、相続開始から3か月以内に,家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述をする必要があります。この場合に申述する家庭裁判所も,相続放棄の申述と同様,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄後の財産管理責任
民法 第940条
- 第1項 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
- 第2項 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
相続放棄をすると、相続のはじめから相続人でなかったことになるため、本来であれば、相続財産について管理する責任は負わないはずです。
もっとも、相続放棄をしたときに相続財産を占有している場合、その相続財産を、相続放棄をしていない相続人または相続財産清算人に引き渡すまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理しなければならないものとされています(民法940条)。
したがって、相続放棄をした場合には、すみやかに、占有している相続財産を他の相続人や相続財産清算人に引き渡す必要があります。