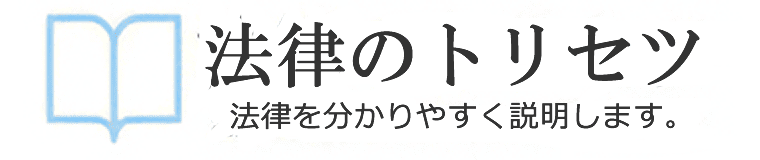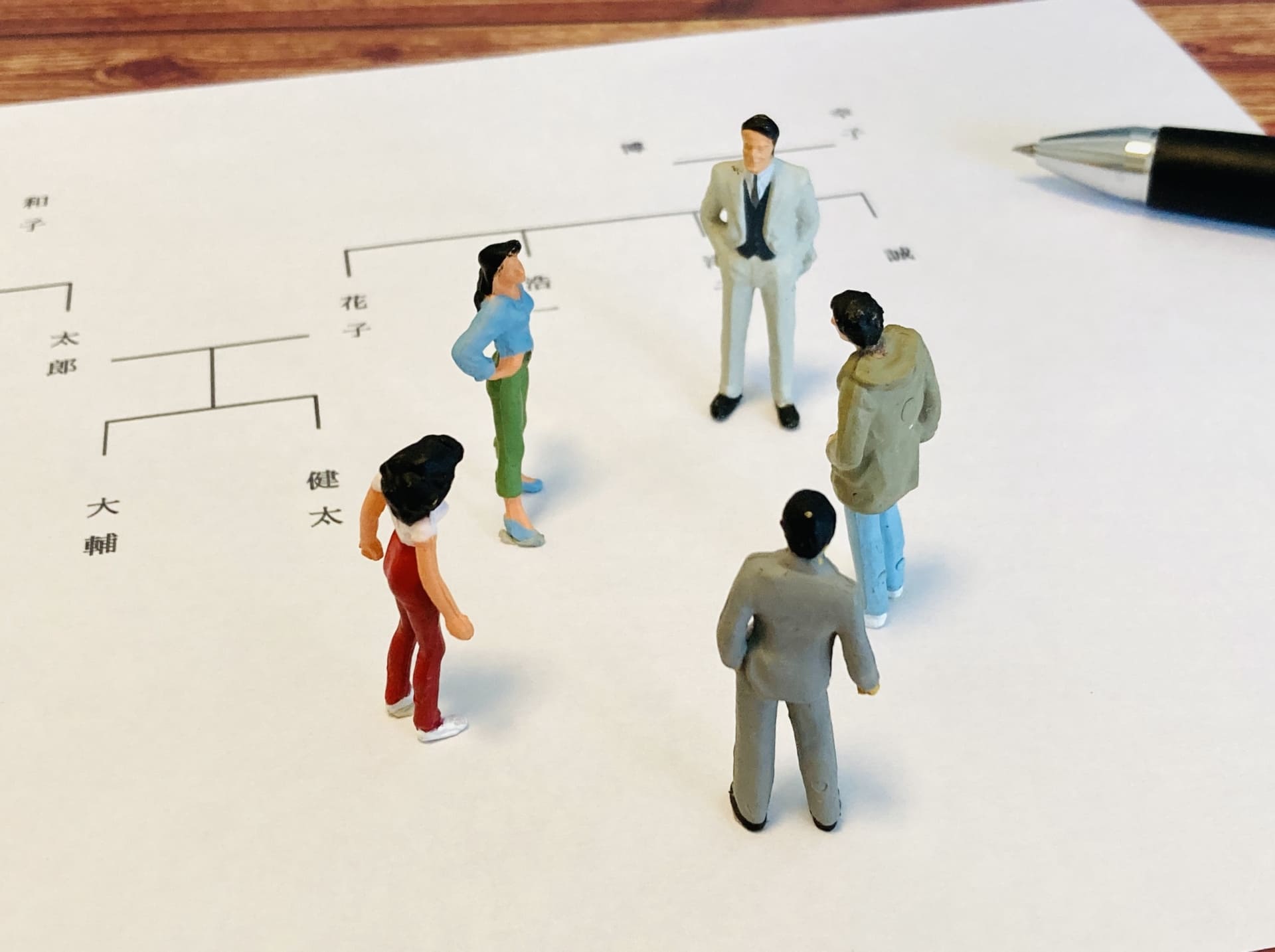この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
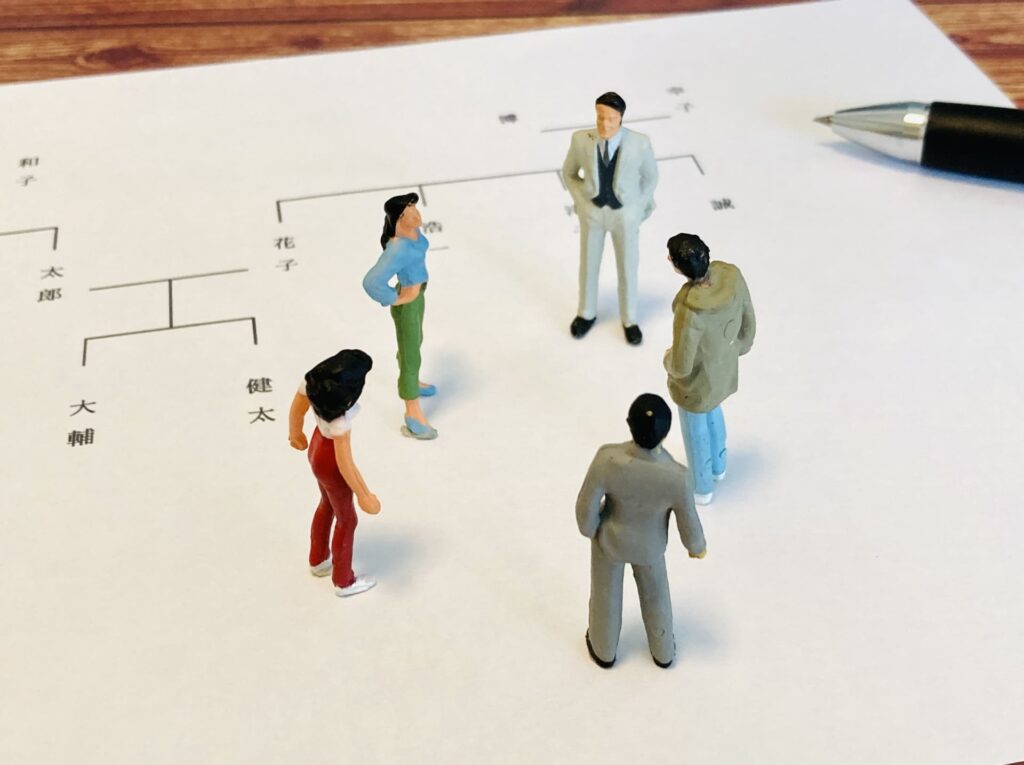
相続財産と相続人固有の財産の混合を防ぐことによって相続債権者または相続人の債権者を保護するため、民法では、「財産分離」制度が設けられています。
財産分離とは?
相続が開始されると,被相続人が有していた財産は,プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も含めて,原則として,すべて相続財産として相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。
包括的に承継するため,相続財産と相続人の固有の財産とが混合してしまう可能性があります。
例えば,相続財産として1000万円があったものの,相続人固有の負債として2000万円の借金があった場合,相続財産と相続人固有の財産が混合してしまうと,負債の方が大きくなってしまいます。
そうなると,被相続人の債権者に不都合が生じます。被相続人の債権者は,相続財産1000万円から債権の回収を目論んでいたにもかかわらず,相続によって相続人固有の財産と混合してしまう結果,債権回収ができなくなってしまうという可能性が生じるからです。
また,逆に,相続人固有の財産として1000万円の資産があったところに,相続財産として2000万円の負債があった場合、相続財産と相続人固有の財産の混合により、負債の方が大きくなってしまいます。
そうなると,この場合には,相続人の債権者が困ることになります。相続さえなければ,相続人固有財産から債権回収ができたはずだからです。
そこで,法は,相続財産と相続人固有の財産の混合を防ぐための制度として「財産分離」制度を用意しています。
財産分離がなされた場合,相続債権者または受遺者は相続財産から優先して引き当てることができ,他方,相続人の債権者は相続人固有の財産から優先して引き当てることができるようになります。
相続債権者または受遺者からの請求による財産分離のことを「第一種財産分離」といい(民法941条),相続人の債権者の請求による財産分離のことを「第二種財産分離」といいます(民法950条)。
相続分離と限定承認の違い
前記のとおり,財産分離制度は,相続財産と相続人固有の財産を分けて取り扱う点で,限定承認制度と似ている面があります。
しかし,限定承認は,相続によって不測の損害を受けるおそれのある相続人を保護する制度ですが,財産分離は,相続によって損害を受けるおそれのある債権者を保護する制度である点に違いがあります。
また,限定承認は,あくまで相続財産にマイナス分がある(またはそのように疑われる)場合に利用する制度です。他方,財産分離の場合には,相続財産が全体としてプラスである場合にも利用されます。
さらに,限定承認の場合には,手続の対象となるのは,あくまで相続財産です。しかし,財産分離の場合には,相続財産だけでなく,相続人固有の財産も手続の対象となります。
なお,財産分離が請求された場合であっても,相続人は,限定承認または相続放棄を申述することができます。
相続分離制度の利用状況
このように,債権者のための制度として財産分離制度が用意されていますが,実際には,ほとんど利用されていないのが現状です。
財産分離をするために無駄なコストがかかること、仮に相続人が債務超過等になってしまった場合には破産手続があるため,むしろそちらが用いられる場合が多いことなどがその原因でしょう。