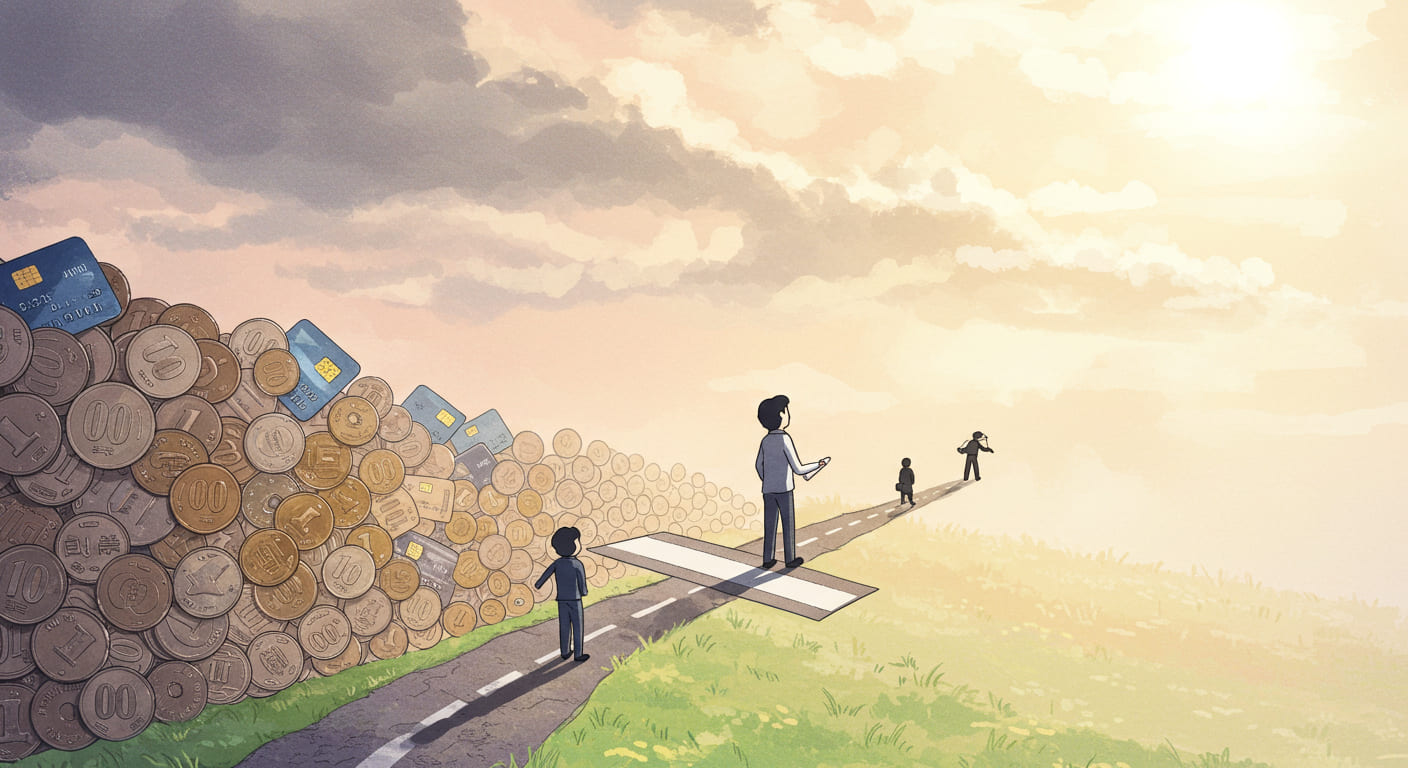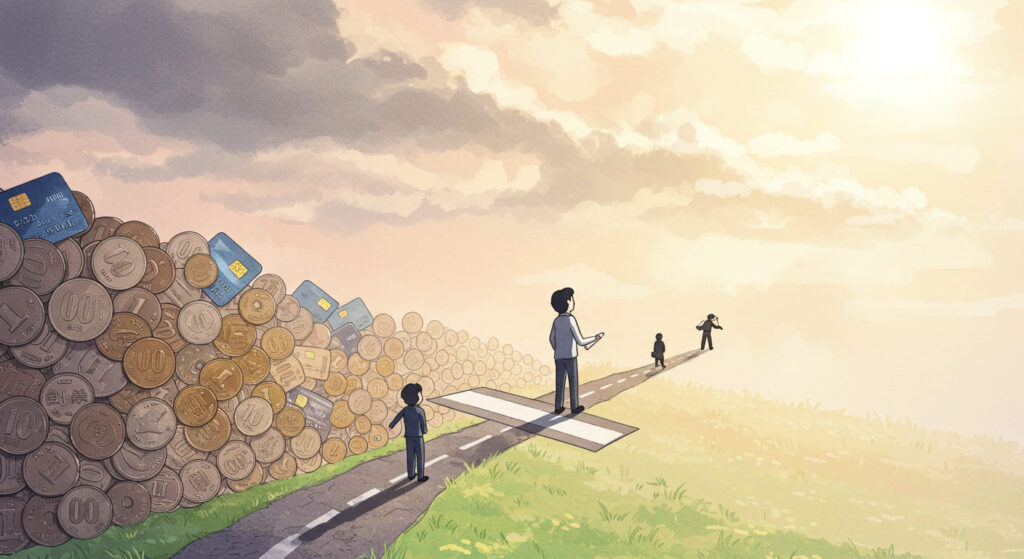
自己破産・免責の手続を経て免責許可決定を受け、それが確定すれば、借金などの債務の支払義務を免れることができます。ただし、税金などの非免責債権は免責されないので、免責許可後も支払いが必要です。
自己破産の手続では財産処分が必要ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいことになっていますので、自由財産に該当する財産は免責許可後も保有していられます。
資格制限は、免責許可決定が確定すれば解除されます。居住制限や郵便物の転送は、自己破産の手続が終われば終了します。免責許可決定がされると、そのことが官報に公告されます。
なお、免責許可決定確定日から7年以内に、再度、自己破産・免責許可を申し立てると、免責不許可事由ありとして扱われてしまいますが、裁判所の裁量により、再度、免責が許可されることもあります。
自己破産における免責
自己破産・免責の手続を経て、裁判所による免責許可決定を得て、その決定が確定すれば、借金などの債務の支払義務を免れることができます。つまり、借金を支払わなくてもよくなるということです。
ただし、自己破産・免責には、借金を免れることができるという強力な効力がある反面、一定のデメリットや制約があるのも事実です。
自己破産の申し立てることによって債務整理をする場合、自己破産をすることによって、どのような制約やデメリットが生じるのかは、非常に気になるところかと思います。
もっとも、自己破産や免責には、債務者の経済的更生を図るという目的もあります(破産法1条)。
したがって、債務者が経済的更生を図ることができなくなるほどに、重大な制約やデメリットが課されるものではありません。
自己破産の選択を不必要に躊躇してしまうようなことにならないように、自己破産において免責を許可された後にどうなるのかについては、正確な知識を得ておく必要があります。
免責許可決定後の手続
免責手続において、裁判所により免責許可決定がされたとしても、ただちに免責の効力が発生するわけではありません。免責の効力は、免責許可決定が確定したときに発生します。
免責許可決定がされると、決定日から概ね2週間後に、官報公告がされます(破産法10条1項)。この官報公告は、官報掲載日の翌日から公告の効力を生じます(破産法10条2項)。
官報公告の効力発生日から起算して2週間は即時抗告期間です。債権者等は、免責許可決定に不服がある場合、この期間中に即時抗告をすることができます(破産法9条前段)。
債権者等による不服申し立てがされずに2週間が経過した場合、免責許可決定が確定することになります(破産法9条後段)。
なお、個人(自然人)の破産では、免責許可決定に対して債権者等による即時抗告がされることは、ほとんど無いと言ってよいでしょう。
借金・債務の免責
破産法 第253条
- 第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
- 第1号 租税等の請求権
- 第2号 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 第3号 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 第4号 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの- 第5号 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 第6号 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
- 第7号 罰金等の請求権
裁判所による免責許可決定が確定すると、「破産債権について、その責任を免れる」ことができます(破産法253条1項本文)。
「責任を免れる」とは、借金など債務の支払義務を免除されるということです。つまり、免責許可確定後は、借金の支払いをしなくてもよくなります。
仮に、免責許可確定後に債権者から請求が来たとしても、免責許可が確定していることを理由に、支払いを拒絶することができます。
なお、免責は、あくまで支払義務の免除であり、債務自体は消滅していないと解されています(自然債務説)。
したがって、債権者から請求されてもこれに応じる必要はありませんが、債務者が任意に返済をすることは可能であると解されています。
免責されない債権
破産法253条1項本文のとおり、免責されるのは「破産債権」です。したがって、財団債権は、免責許可決定が確定しても免責されません。
また、破産債権であっても「非免責債権」に該当する債権については、免責許可決定が確定しても免責の効力が及ばず、支払いをしなければなりません(破産法253条1項ただし書き各号)。
したがって、免責許可確定後でも、財団債権と非免責債権に該当する債券に対しては支払いを免れることができないのです。
一般的な借金や立替金などは、破産債権です。非免責債権にも該当しません。したがって、免責されると考えておいて間違いないでしょう。
財団債権や非免責債権には、例えば、以下のようなものがあります。
これらの債権は免責されても支払いをしなければならないということは、あらかじめ知っておく必要があります。
財産・資産の変動
自己破産の手続においては、自由財産を除く財産・資産は、破産管財人によって換価処分されます。
したがって、換価処分すべき財産がある場合には、自己破産の前と免責許可後では、当然、財産は変動することになります。
なお、免責許可確定の時点では、すでに自由財産を除く財産・資産は処分されていますが、自由財産は、免責許可確定後も有しておくことができます。
自由財産には、以下のものがあります。
- 破産手続開始後に取得した財産(新得財産。破産法34条1項)
- 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
- 99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
- 裁判所によって自由財産の拡張が認められた財産(破産法34条3項4号)
- 破産管財人によって破産財団から放棄された財産(破産法78条2項12号)
自由財産には、破産手続開始後に取得した財産(新得財産)も含まれます。したがって、免責許可後に取得した財産も、当然、処分は不要です。
新たな借入れ等の可否
自己破産をすると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。自己破産の場合、破産手続開始決定から7年間(または免責が許可されてから5年間)ほどブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されている間は、新たに借入れをしたり、クレジットカードで買い物をしたり、ローンを組んだり、または保証人になることは難しくなります。
免責許可が確定したとしても、期間が経過するまでは、破産した事実の記載をブラックリストから外してもらうことはできません(ただし、債務残高をゼロ円にしてもらうことはできるようです。)。
資格制限の解除
自己破産の手続が開始されると、破産者には資格制限が課せられます。この資格制限は、復権されるまで解除されません。
免責許可決定が確定すると、当然に復権されます。つまり、免責許可が確定すれば、資格制限も完全に解除されます。したがって、免責許可確定後は、資格制限を気にする必要はなくなります。
居住制限の終了
自己破産の手続きが開始されると、破産者は、裁判所の許可なく住居を移転したり、宿泊を伴う旅行や出張ができなくなります(破産法37条1項。ただし、連絡がつく場所であれば、基本的に許可されます。)
この居住制限は、破産手続の間だけです。したがって、破産手続が終了すれば、居住制限は解かれます。
免責許可確定の時点で、すでに破産手続が終了していれば、免責許可確定後は、自由に住居を移したり、旅行や出張をすることができます。
なお、免責許可確定時にまだ破産手続が終了していない場合(例えば、まだ配当手続が終了していない場合など)には、破産手続が終了するまでは居住制限は解かれません。
郵便物転送の終了
自己破産の手続きが開始されると、破産者宛ての郵便物は、破産管財人に転送され、破産管財人がその郵便物を開披して財産の調査などを行うことになるのが通常です。
この郵便物の転送措置も、破産手続が終了すれば終了します(事案によっては、第1回の債権者集会の日に終了することもあります。)。
したがって、免責許可確定の時点で、すでに破産手続が終了していれば、免責許可確定後は、郵便物の転送はされず、ご自身のところに通常どおり郵送されるようになります。
官報公告
自己破産・免責の手続を経て免責許可決定がされた場合、免責許可決定がされたことが官報に掲載されます。官報には、氏名・住所とともに、免責が許可されたことなどが掲載されます。
官報は、信用情報と異なり、期間が経過しても消去はされません(ただし、過去の官報は容易には検索できません。)。
破産者名簿への掲載の有無
自己破産の手続が開始されると、そのことが破産者の本籍地の市町村役場に通知され、その市町村役場の破産者名簿に記載されることになっています。
しかし、裁判所から市町村役場への通知は、免責が不許可または免責がされなかった場合に限られるというのが現在の運用です(最高裁民三第000113号平成16年11月30日最高裁判所事務総局民事局長通達)。
したがって、免責許可が確定すれば、市町村役場への通知はされず、破産者名簿に登録されることもありません。
再度の自己破産申立ての可否
免責許可を受けた後に、何らかの事情で再度自己破産をすることになるというのは、良いことではありませんが、実際にはあり得ることです。
もっとも、自己破産・免責許可を申し立てれば、必ず免責が許可されるわけではありません。免責不許可事由がある場合には、免責が許可されないこともあります。
自己破産・免責許可の申立てからさかのぼって7年以内に免責許可決定を受けたことも免責不許可事由の1つとされています。
つまり、1回免責許可決定を受けると、その後7年間は、もう1度、自己破産・免責許可の申立てをしても免責不許可事由ありとされてしまうということです。
7年以内の再度の自己破産・免責許可申立てであっても、事情によっては、裁判所の裁量によって、再度、免責が許可されることもあります。
せっかく免責を許可してもらっているのですから、2度目はないように生活していきましょう。