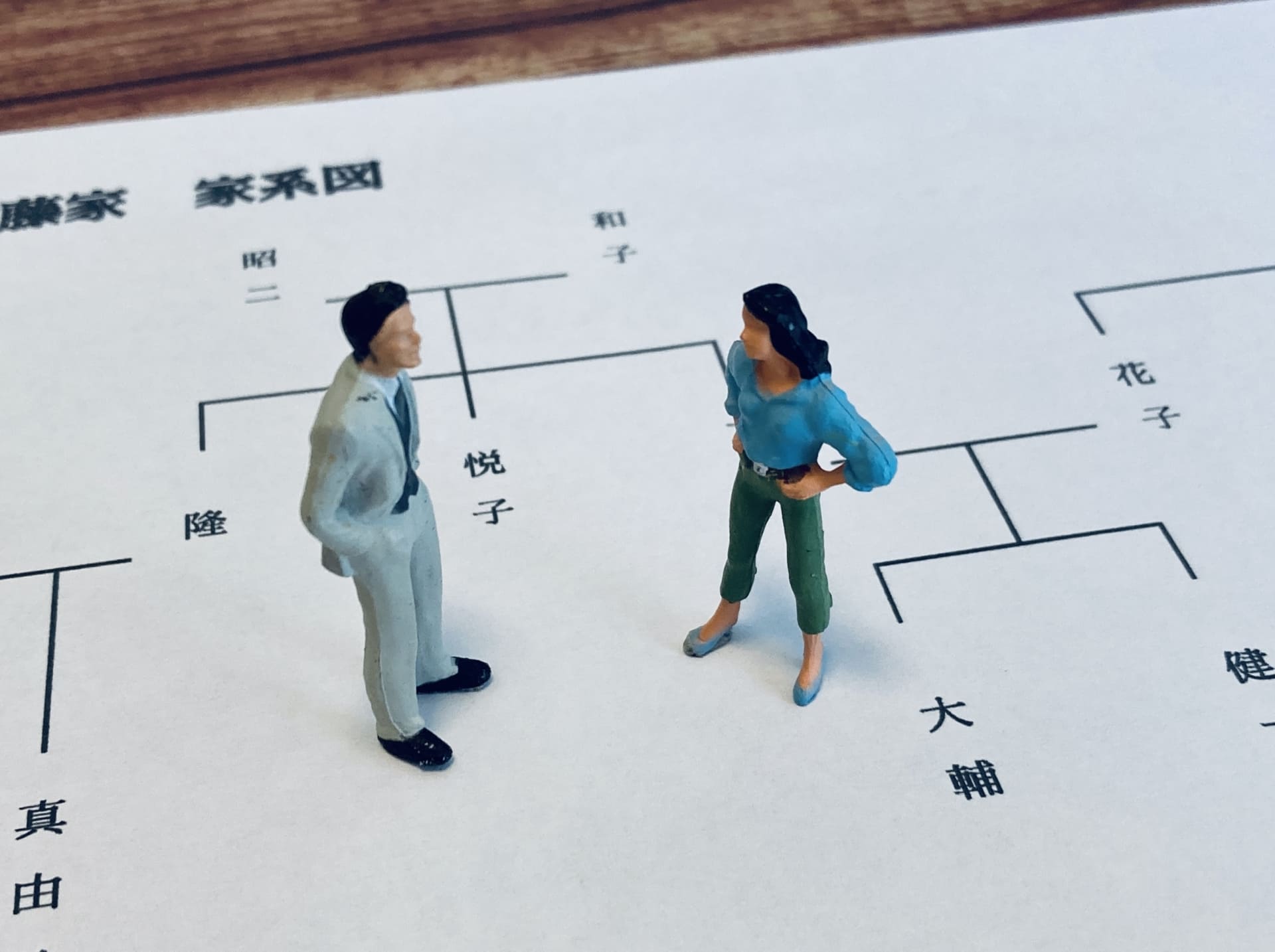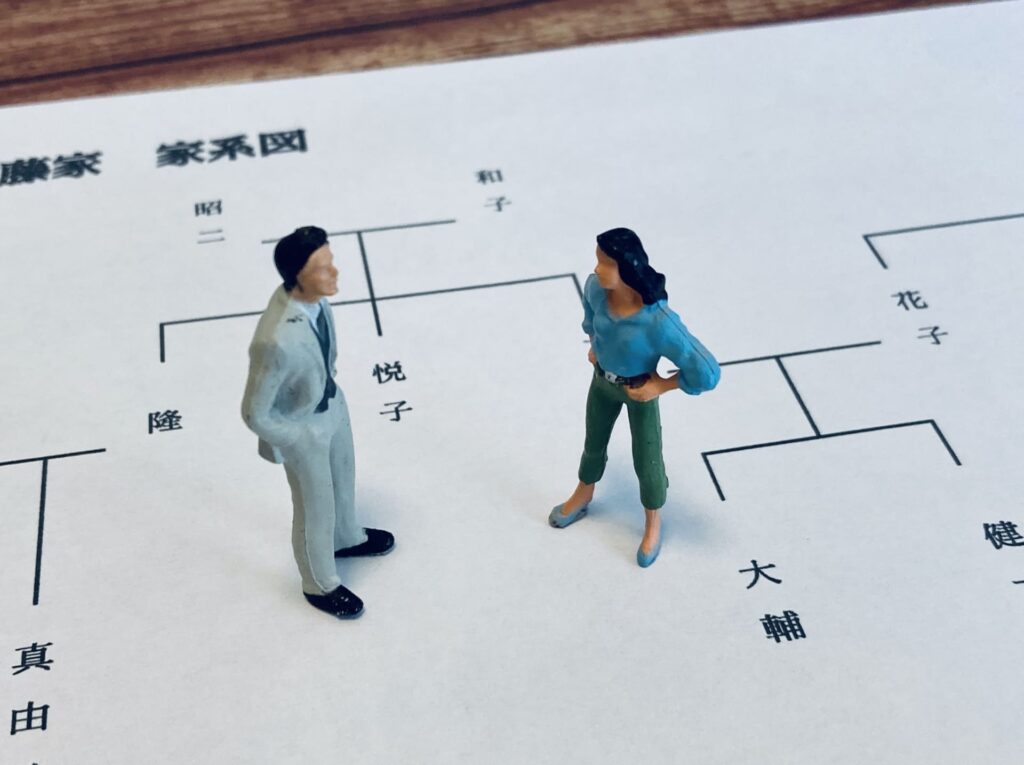
相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。これに対し、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。
相続開始「前」の遺留分放棄の可否
民法 第1049条
第1項 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
第2項 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
兄弟姉妹を除く法定相続人には,最低限度の取り分ともいうべきものとして「遺留分」が保障されています。遺留分を有する権利者は,遺留分を侵害する相続人や受遺者に対して,遺留分侵害額を請求することができます。
この遺留分は,遺留分権利者に認められた権利です。したがって,原則論をいえば,自らこの権利を放棄することもできるはずです。
しかし,遺留分の放棄を無制限に認めてしまうと,被相続人が,遺留分権利者に対して,遺留分放棄を強要するというような事態が濫発してしまうおそれがあります。
そこで,民法では,相続開始前(被相続人の生存中)における遺留分の放棄は,家庭裁判所の許可を得なければできないとし,遺留分権利者であっても相続開始前には自由に遺留分の放棄は行えないことにしています(民法1049条1項)。
そのため,遺留分放棄は,遺留分権利者の被相続人に対する単独行為としての意思表示であるだけでなく,家庭裁判所の許可を要する要式行為でもあるということになります。
相続開始前の遺留分放棄許可の審判
相続開始前に遺留分を放棄するためにとるべき手続は,具体的にいえば,遺留分権利者となるべき人が,被相続人となるべき人の住所地を管轄する家庭裁判所に,遺留分放棄許可審判の申立てをすることです。
申立てを受けた家庭裁判所は,その遺留分放棄が本当に遺留分権利者となる人の自由な意思に基づくものなのか(強要などを受けていないか),遺留分放棄をする必要性があるのかなどを考慮して,許可・不許可を決定することになります。
なお,許可審判の後に事情が変動し,遺留分放棄を許可することが相当でないというような状態になった場合には,家庭裁判所は,職権で放棄許可審判を取り消すことができるとされています。
相続開始前の遺留分放棄の効果
前記のとおり,家庭裁判所によって遺留分放棄が許可された場合には,相続開始前に遺留分を放棄することが認められます。
つまり,後に相続が開始したとしても,もはや遺留分減殺請求権を行使することはできなくなるということです。
もっとも,遺留分の放棄はあくまで遺留分を放棄しただけであって,相続放棄をしたわけではありません。
したがって,相続が開始すれば,遺留分を放棄していたとしても,その放棄者は法定相続人となります。つまり,相続を受けることはできるということです。もちろん,他の相続人の相続分が増えるわけでもありません。
また、仮に遺留分を侵害する遺贈等があったとしても、その遺言と異なる遺産分割をすることは可能です。したがって、遺留分を放棄していた場合であっても、遺留分減殺請求ができないというだけであって,遺産分割によってその遺留分侵害部分の遺産を取得することは可能です。
なお,遺留分放棄者が被代襲者である場合,その代襲相続人も,やはり遺留分減殺請求をすることはできなくなります。
相続開始「後」の遺留分放棄の可否
前記のとおり,相続開始「前」に遺留分を放棄するためには,家庭裁判所の許可が必要です。
しかし,相続開始「後」であれば,もはや被相続人による遺留分放棄の強要等のおそれがありません。そのため,遺留分放棄を制限する理由はないといえます。
そこで,相続開始後については,遺留分権利者は,家庭裁判所の許可は不要で,自由に遺留分を放棄できます。
相続開始後に遺留分放棄をする場合には,遺留分減殺請求の相手方にその旨の意思表示をすることになります。もっとも,あえて何もしなくても遺留分侵害額請求権は1年で時効により消滅します。