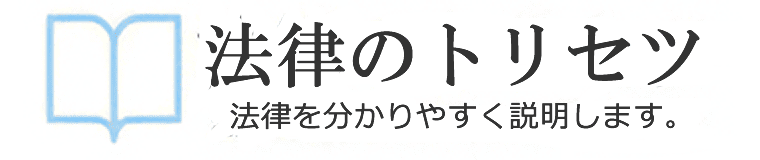この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

裁判所によって破産手続開始の決定と同時にされる処分のことを、破産手続開始の同時処分といいます(破産法31条)。
破産手続開始の同時処分には、①破産管財人の選任、②破産債権届出期間の決定、③財産状況報告集会の期日の決定、④破産債権の一般調査期間または一般調査期日の決定があります。
破産手続開始に伴う同時処分
破産法 第31条
- 第1項 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、1人又は数人の破産管財人を選任し、かつ、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 第1号 破産債権の届出をすべき期間
- 第2号 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(第4項、第136条第2項及び第3項並びに第158条において「財産状況報告集会」という。)の期日
- 第3号 破産債権の調査をするための期間(第116条第2項の場合にあっては、破産債権の調査をするための期日)
- 第2項 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるときは、同項第1号の期間並びに同項第3号の期間及び期日を定めないことができる。
- 第3項 前項の場合において、裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、第1項第1号の期間及び同項第3号の期間又は期日を定めなければならない。
- 第4項 第1項第2号の規定にかかわらず、裁判所は、知れている破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、同号の期日を定めないことができる。
- 第5項 第1項の場合において、知れている破産債権者の数が1000人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第4項本文及び第5項本文において準用する同条第3項第1号、第33条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者(同項本文の場合にあっては、同項本文に規定する議決権者。次条第2項において同じ。)に対する通知をせず、かつ、第111条、第112条又は第114条の規定により破産債権の届出をした破産債権者(以下「届出をした破産債権者」という。)を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。
破産手続開始の申立てがされ、その申立てが破産手続開始の要件を満たしている場合、裁判所は破産手続開始の決定をします。
破産手続開始の時点ですでに「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足するおそれがあると認めるとき」は、裁判所は、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定をします(破産同時廃止決定。破産法216条1項)。
同時廃止決定をしない場合、裁判所は、破産手続開始決定と同時に、以下の各処分をしなければなりません。この処分のことを「同時処分」といいます(破産法31条1項)。
- 破産管財人の選任
- 破産債権届出期間の決定
- 財産状況報告集会の期日の決定
- 破産債権一般調査期日または期間の決定
破産管財人の選任
破産手続開始の同時処分として、裁判所は、1人または数人の破産管財人を選任します(破産法31条1項柱書)。
ただし、実務では、1人の破産管財人を選任するのが通常です。複数人の破産管財人を選任することはほとんどないでしょう。
大規模事件などで複数人による対応が必要となる場合には、1人の破産管財人を選任し、その破産管財人が、裁判所の許可を得て、破産管財人代理を選任して対応することになります(破産法77条)。
また、破産管財人に選任されるために特段の資格を要するという法律上の規定はありませんが、実際に破産管財人に選任されるのは、弁護士だけとなっています。
なお、東京地方裁判所本庁では、破産手続開始申立て後すぐに破産管財人候補者が選任され、破産者との打ち合わせを行い、開始決定と同時に正式に選任される運用がとられています。
破産債権届出期間の決定
破産規則 第20条
- 第1項 法第31条第1項の規定により同項各号の期間又は期日を定める場合には、特別の事情がある場合を除き、第1号及び第3号の期間はそれぞれ当該各号に定める範囲内で定め、第2号及び第4号の期日はそれぞれ当該各号に定める日とするものとする。
- 第1号 破産債権の届出をすべき期間 破産手続開始の決定の日から2週間以上4月以下(知れている破産債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、4週間以上4月以下)
破産手続開始の同時処分として、裁判所は、破産債権届出期間を決定します(破産法31条1項1号)。
破産手続においては、裁判所および破産管財人によって破産債権の調査が行われます。
破産債権調査では、まず最初に、裁判所または破産管財人が、破産手続開始の申立てにおいて提出された債権者一覧表に記載された各債権者に対して、破産手続の開始を通知し、それとともに、破産債権を届け出るよう催告します。
破産債権届出期間とは、債権者が裁判所または破産管財人に対して破産債権を届け出る期間です。
破産債権届出期間は、原則として、破産手続開始決定の日から2週間以上4か月以下の期間に設定されます(破産規則20条1項1号)。
財産状況報告集会期日の決定
破産規則 第20条
- 第1項 法第31条第1項の規定により同項各号の期間又は期日を定める場合には、特別の事情がある場合を除き、第1号及び第3号の期間はそれぞれ当該各号に定める範囲内で定め、第2号及び第4号の期日はそれぞれ当該各号に定める日とするものとする。
- 第2号 財産状況報告集会(法第31条第1項第2号に規定する財産状況報告集会をいう。第54条第1項において同じ。)の期日 破産手続開始の決定の日から3月以内の日
破産手続開始の同時処分として、裁判所は、財産状況報告集会の期日を決定します(破産法31条1項2号)。
破産手続においては、財産状況報告集会が行われます。
財産状況報告集会とは、破産管財人が、破産者が破産手続開始に至った経緯や事情、破産者や破産財団の状況などを報告する債権者集会のことをいいます(破産法31条1項2号、158条)。
財産状況報告集会の期日は、原則として、破産手続開始決定の日から3か月以内の日に設定されます(破産規則20条1項2号)。
破産債権一般調査期間または期日の決定
破産法 第116条
- 第1項 裁判所による破産債権の調査は、次款の規定により、破産管財人が作成した認否書並びに破産債権者及び破産者の書面による異議に基づいてする。
- 第2項 前項の規定にかかわらず、裁判所は、必要があると認めるときは、第3款の規定により、破産債権の調査を、そのための期日における破産管財人の認否並びに破産債権者及び破産者の異議に基づいてすることができる。
- 第3項 裁判所は、第121条の規定による一般調査期日における破産債権の調査の後であっても、第119条の規定による特別調査期間における書面による破産債権の調査をすることができ、必要があると認めるときは、第118条の規定による一般調査期間における書面による破産債権の調査の後であっても、第122条の規定による特別調査期日における破産債権の調査をすることができる。
破産規則 第20条
- 第1項 法第31条第1項の規定により同項各号の期間又は期日を定める場合には、特別の事情がある場合を除き、第1号及び第3号の期間はそれぞれ当該各号に定める範囲内で定め、第2号及び第4号の期日はそれぞれ当該各号に定める日とするものとする。
- 第3号 破産債権の調査をするための期間 その期間の初日と第1号の期間の末日との間には1週間以上2月以下の期間を置き、1週間以上3週間以下
- 第4号 破産債権の調査をするための期日 第1号の期間の末日から1週間以上2月以内の日
破産手続開始の同時処分として、裁判所は、破産債権の一般調査期間また期日を決定します(破産法31条1項3号)。
破産債権の調査は、書面による調査が原則とされています(破産法116条1項)。書面による調査の場合には、一般調査期間が設定されることになります。
一般調査期間は、原則として、1週間以上3週間以下の期間に定められます(破産規則20条1項3号)。
他方、裁判所は、必要と認めるときは、書面による調査ではなく、期日における調査にすることもできます(破産法116条2項)。期日における調査の場合には、一般調査期日が設定されます。
一般調査期日は、原則として、前記破産債権届出期間の末日から1週間以上2か月以内の日に設定されます(破産規則20条1項4号)。