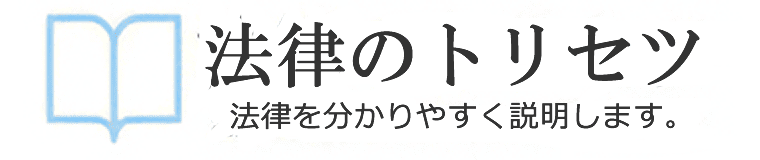この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産手続開始決定がされた場合、裁判所は、破産法31条に定める同時処分のほかに、破産手続開始決定に付随する処分を行います。これらの処分は、同時処分と区別して、「付随処分」と呼ばれています。
具体的には、①破産手続開始決定の主文等の公告(破産法32条1項、2項)、②一定の関係者および監督官庁に対する破産手続開始決定の通知(同条3項、4項)、③登記所に対する破産登記または登録の嘱託(破産法257条1項)、④信書送達事業者に対する郵便物等の回送嘱託(破産法81条1項)があります。
破産手続開始決定の付随処分とは
破産法 第32条
- 第1項 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 第1号 破産手続開始の決定の主文
- 第2号 破産管財人の氏名又は名称
- 第3号 前条第1項の規定により定めた期間又は期日
- 第4号 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第3項第2号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
- 第5号 第204条第1項第2号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第1項第3号の期間の満了時又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
- 第2項 前条第5項の決定があったときは、裁判所は、前項各号に掲げる事項のほか、第4項本文及び第5項本文において準用する次項第1号、次条第3項本文並びに第139条第3項本文の規定による破産債権者に対する通知をせず、かつ、届出をした破産債権者を債権者集会の期日に呼び出さない旨をも公告しなければならない。
- 第3項 次に掲げる者には、前2項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。
- 第1号 破産管財人、破産者及び知れている破産債権者
- 第2号 知れている財産所持者等
- 第3号 第91条第2項に規定する保全管理命令があった場合における保全管理人
- 第4号 労働組合等(破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、破産者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。第78条第4項及び第136条第3項において同じ。)
- 第4項 第1項第3号及び前項第1号の規定は、前条第3項の規定により同条第1項第1号の期間及び同項第3号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
- 第5項 第1項第2号並びに第3項第1号及び第2号の規定は第1項第2号に掲げる事項に変更を生じた場合について、第1項第3号及び第3項第1号の規定は第1項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合(前条第1項第1号の期間又は同項第2号の期日に変更を生じた場合に限る。)について準用する。ただし、同条第5項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、当該通知をすることを要しない。
破産手続開始の申立てがされ、その申立てが破産手続開始の要件を満たしている場合、裁判所は破産手続開始の決定をします。
破産手続開始決定をした場合、裁判所は、破産法32条に定める各処分をしなければなりません。
この破産法32条に定める処分のことを、破産法31条に定める破産手続開始決定の同時処分と区別して、破産手続開始決定の「付随処分」と呼ぶことがあります。
破産手続開始決定の公告
破産手続開始の付随処分として、裁判所は、破産手続開始後、一定の事項を公告しなければならないとされています。
具体的には、破産手続開始後ただちに、以下の事項を公告しなければなりません(破産法32条1項、2項)。
- 破産管財人の氏名または名称
- 破産法31条1項により定めた破産債権届出期間、財産状況報告集会の期日、破産債権の一般調査期間または期日
- 破産財団に属する財産の所持者に対する破産者への財産交付の禁止、および、破産者の債務者に対する破産者への弁済の禁止
- 簡易配当に異議のある破産債権者は、裁判所に対し、破産債権の調査期間満了時または調査期日の終了時までに異議を述べるべき旨
- 大規模事件の場合において破産債権者に対する個別の通知や期日呼出を省略等することを決定したときは、その決定の内容
この公告は、破産手続開始決定後ただちに行われます。
公告は、官報掲載の方法により行われ(破産法10条1項)、官報掲載された日の翌日に効力を生じ(同条2項)、個別通知がなされたか否かにかかわらず、一切の関係人に破産手続開始決定の告知があったものとみなされます(同条4項)。
公告事務は、裁判所書記官により取り扱われます(破産規則6条)。
破産手続開始の通知
破産手続開始の付随処分として、裁判所書記官は、破産手続開始後、前記の公告事項を一定の関係者に通知しなければならないとされています。
公告事項を通知をしなければならない関係者は、以下のとおりです(破産法32条3項)。
- 破産管財人
- 破産者
- 知れている破産債権者
- 破産財団に属する財産の所持者または破産者に対して債務を負担する者のうちで知れている者
- 保全管理命令がされている場合の保全管理人
- 破産者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合(労働組合がないときは、破産者の使用人その他の従業員の過半数を代表する者)
これらの通知は、裁判所書記官が相当と認める方法によって行います(破産規則12条、民事訴訟規則4条1項)。
また、上記のほか、官庁その他の機関の許可・免許・登録その他の許可に類する行政処分がなければ開始することができない事業を営む法人・会社または設立できない法人・会社について破産手続開始の決定があった場合、裁判所書記官は、その監督官庁その他の機関に対しても、破産手続開始の通知をしなければならないとされています(破産規則9条1項)。
金融機関などについて破産手続開始決定がなされた場合も、裁判所書記官は、内閣総理大臣等の監督官庁に通知しなければならないとされています(預金保険法137条の2第1項)。
破産登記・登録の嘱託
法人破産の場合、破産手続開始の付随処分として、裁判所書記官は、破産手続開始後遅滞なく、破産手続開始の登記を登記所に嘱託しなければならないとされています(破産法257条1項)。
この嘱託により、登記所において、破産者である法人・会社の登記に、破産手続が開始されている旨が記載されるようになります。ただし、破産手続開始の登記には、事実上の警告的効力しかないと解されています。
なお、個人破産の場合においても、登記されている財産(不動産)を所有しているときなどには、破産登記がされることがあります(破産法258条1項)。
郵送物の回送嘱託
破産手続開始の付随処分として、裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達事業者に対し、破産者宛ての郵便物や信書郵便を破産管財人に送達するよう嘱託することができるとされています(破産法81条1項)。
破産者宛てに送られる郵便物や信書郵便を、破産管財人に転送するよう、信書送達事業者(郵便局など)に嘱託できるのです。
条文上、嘱託することが「できる」とされていますが、実務上はむしろ、郵便物の回送嘱託がされるのが一般的でしょう。
ただし、信書郵便の回送嘱託は行われないのが通常です。
破産管財人は、転送されてきた郵便物を開披して、内容を確認することができます(破産法82条1項)。これにより、破産者の財産や負債などを調査しています。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。