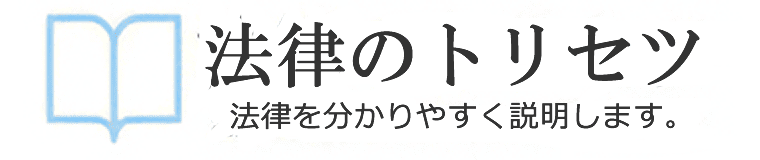この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産手続は、破産裁判所による「破産手続開始決定」という裁判によって開始されます(破産法30条1項)。かつて「破産宣告」と呼ばれていた決定です。
破産手続開始の決定をしたもらうためには、形式的(手続的)内容および実体的要件の両方を充たしていなければなりません。
破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任され、破産者の有する財産の管理処分権は破産管財人に移行します。また、破産債権者は、原則として、個別の権利行使をすることが制限されます。
破産手続開始決定(旧「破産宣告」)とは
破産法 第30条
- 第1項 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
- 第1号 破産手続の費用の予納がないとき(第23条第1項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
- 第2号 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
- 第2項 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。
裁判所において破産手続を開始してもらうためには、まず、裁判管轄のある地方裁判所に対して破産手続開始の申立てをしなければなりません。
とはいえ、破産手続開始の申立てをしたからといって、当然に破産手続を開始してもらえるわけではありません。
破産手続も裁判所における裁判手続ですから、法律で定める要件を満たしていなければ破産手続を開始できません。
そのため、破産手続開始の申立てがなされると、裁判所において、破産手続開始の法律要件を満たしているかどうかの審査がされます。
そして、裁判所において、法律要件を満たしてるため破産手続を開始してもよいと判断されると「破産手続開始決定」という決定がされます(破産法30条1項)。
この破産手続開始決定が発令されることによってはじめて、破産手続が開始されることになるのです。
この破産手続開始決定は、かつては「破産宣告」と呼ばれていましたが、平成16年の破産法改正の際に「破産手続開始決定」という名称に変更されました。
破産手続開始決定の要件
前記のとおり、破産手続開始を申立てれば当然に破産手続が開始されるわけではなく、破産法で定められている破産手続開始の要件を満たしている必要があります。
この破産手続開始決定の要件には、形式的要件(手続的要件)と実体的要件があります。
形式的・手続的要件(申立ての適法性)
破産手続を開始してもらうためには、破産手続開始の形式的・手続的要件が満たされている必要があります。
形式的・手続的要件が満たされていない場合には、後述の実質的要件を審査するまでもなく、申立ては却下されることになります。具体的には、以下の形式的要件が必要です。
- 申立ての方式に不備がないこと(破産法20条)
- 申立人に申立権があること(同法18条、19条等)
- 債務者に破産能力があること
- 管轄違いを除き裁判所の管轄が正しいこと(同法4条、5条)
- 手数料を納付したこと(同法21条)
実体的要件
破産手続開始の申立ての手続自体が適法であっても、破産手続が開始されるためには、さらに、実体的要件を満たしている必要があります。
破産手続開始の実体的要件とは、以下の要件です。
債務者に破産手続開始原因があること
破産手続を開始してもらうためには、債務者に「破産手続開始原因」があることが必要です。破産手続開始原因には「支払不能」と「債務超過」があります。
会社など法人の破産の場合は、支払不能か債務超過のどちらか一方があれば足ります(破産法15条1項、16条1項)。他方、個人(自然人)破産の場合は、支払不能のみが破産手続開始原因です。
支払不能とは「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」にあることをいいます(破産法2条11項)。
債務超過とは「債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態」にあることをいいます(破産法16条1項)。
債務者に破産障害事由がないこと
破産手続開始原因がある場合でも、破産手続の障害となる事由(破産障害事由)がある場合には、破産手続開始決定はされません。
破産障害事由としては、以下のものがあります(破産法30条)。
- 破産手続の費用の予納がないこと
- 不当目的・不誠実な破産手続開始申立てがされたこと
- 民事再生・会社更生・特別清算手続が開始されていること
破産手続開始決定の効力
前記の要件を満たしている場合、裁判所は、破産手続開始決定をすることになります。
破産手続開始決定がなされると、破産手続が開始され、その決定のときから各種の法的効力が生じることになります(破産法30条2項)。
破産管財人による破産財団に属する財産の管理処分権の専属
破産手続開始決定と同時に、裁判所によって破産管財人が選任されます(破産法31条1項柱書)。
そして、破産手続開始時において破産者が有していた財産は「破産財団」として扱われ(破産法34条)、その管理処分権は破産管財人に専属することになります。
そのため、破産手続が開始されると、破産者は、勝手に財産を処分することができなくなります。
個人破産の場合には、換価処分の対象にならない自由財産が認められています。この自由財産については、破産管財人に管理処分権は移らず、破産者が自由に利用・処分できます。
他方、法人破産・会社破産の場合は、自由財産制度はありません。したがって、その法人・会社のすべての財産の管理処分が破産管財人に委ねられることになります。
破産者に課せられる制限・義務
上記のとおり、破産手続が開始されると、破産者は、勝手に財産を処分することができなくなり、各種の制限を受け、または義務を課されることになります。
例えば、破産管財人による調査のため、破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送されます(破産法81条、82条)。
さらに、個人の破産者、破産者である法人・会社の理事・取締役等は、裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができない居住制限を課せられます(破産法37条1項、39条)。
その他、破産者に対しては、重要財産開示義務(破産法41条)が債権者集会への出頭・意見陳述義務(破産法121条3項、5項、122条2項)、理事・取締役等に対しては、説明義務(破産法40条1項)などが課せられます。
破産債権者による個別の権利行使の制限
破産手続開始決定がされると、破産債権者は、原則として、破産手続における配当以外の方法で、債権回収を図ることはできなくなります(破産法100条1項)。
そのため、破産債権者は、破産手続開始後に破産債権を回収するための訴訟や強制執行などの手続をすることはできません。
法人の解散
法人破産の場合、破産手続開始決定により、破産者である法人は解散するのが通常です。ただし、破産手続中は清算法人となりますので、その限度で法人格は残っており、破産手続の終了によって完全に消滅することになります。
とはいえ、あくまで清算のために法人格が残されているだけですので、法人・会社の事業を継続できるわけではありません。
同時処分と付随処分
破産手続開始の効果そのものではありませんが、破産手続開始決定がされると、それと同時に、破産管財人が選任されるほか、債権届出期間の指定、財産状況報告集会等の期日指定などがされます(同時処分)。
さらに、破産手続開始決定に付随するものとして、各債権者への破産手続開始の通知、官報公告、監督庁等への通知、破産登記などの処分(付随処分)も行われます。


この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
破産法と資格試験
倒産法の基本法が破産法です。破産以外の民事再生法などの倒産法を理解するためにも、破産法を理解しておく必要があります。
この破産法は、司法試験(本試験)や司法試験予備試験の試験科目になっています。分量が多い上に、かなり実務的な科目であるため、イメージも持ちにくい部分があります。
ただし、出題範囲は限られています。そのため、出題範囲に絞って効率的に勉強することが必要です。そのために、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
破産法を深く知りたい方やもっと詳しく勉強したい方のために、破産法の参考書籍を紹介します。
破産法・民事再生法(第6版)
著者:伊藤 眞 出版:有斐閣
倒産法研究の第一人者による定番の体系書。民事再生法と一体になっているので分量は多めですが、読みやすいです。難易度は高めですが、第一人者の著書であるため、信頼性は保証されています。
条解破産法(第3版)
著者:伊藤 眞ほか 出版:弘文堂
条文ごとに詳細な解説を掲載する逐条の注釈書。破産法の辞書と言ってよいでしょう。破産法の条文解釈に関して知りたいことは、ほとんどカバーできます。持っていて損はありません。金額面を除けば、誰にでもおすすめです。
破産・民事再生の実務(第4版)民事再生・個人再生編
編集:永谷典雄ほか 出版:きんざい
東京地裁民事20部(倒産部)の現役裁判官による破産実務の解説書。東京地裁の破産事件を扱う実務家必携の本。実務家でなくても、実際の手続運用を知っておくと、破産法をイメージしやすくなるでしょう。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
倒産法(LEGAL QUEST)
著者:杉本和士ほか 出版:有斐閣
法科大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた基本書・概説書。破産法だけでなく、倒産法全般について分かりやすくまとめられています。
倒産法講義
著者:野村剛司ほか 出版:日本加除出版
こちらも法学大学院生や司法試験・予備試験受験生向けに書かれた教科書。著者が実務家であるため、実務的な観点が多く含まれていて、手続をイメージしやすいメリットがあります。
倒産法(第3版)伊藤真試験対策講座15
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。