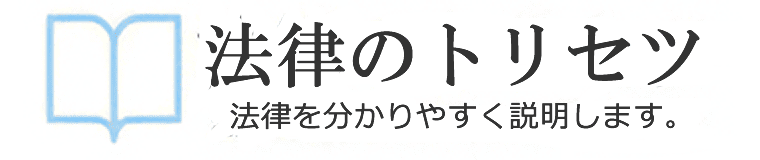この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

破産手続開始の申立ては、裁判管轄のある裁判所に対し、最高裁判所規則(破産規則)で定める事項を記載した破産手続開始の申立書を提出する方式で行う必要があります。
破産手続開始申立ての方式
破産法 第20条
- 第1項 破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければならない。
- 第2項 債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出することができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる。
破産手続は、裁判所の破産手続開始決定によって開始されます(破産法30条1項)。
もっとも、債務者が支払不能または債務超過になると自動的に破産手続が開始されるわけではありません。
また、裁判所が独自に調査して破産手続を開始させるわけでもありません(ただし、破産法等で定められた例外的な場合に、裁判所が職権で破産手続開始決定をすることはあります。)。
裁判所に破産手続開始決定を出してもらうためには、破産法で定められている破産申立権者が、管轄の裁判所に対して、破産手続開始の申立てをする必要があります。
この破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則(破産規則)で定める事項を記載した書面でしなければなりません(破産法20条1項)。この書面は「破産手続開始の申立書」と呼ばれます。
この破産手続開始の申立書を裁判所に提出する方式で、破産手続開始の申立てをしなければならず、口頭で申立てをすることはできません。
また、単に破産手続開始の申立書を裁判所に提出するだけでよいわけではなく、これに債権者一覧表や財産目録などの各種書類や疎明資料も添付して提出する必要があります。
破産手続開始の申立書
前記のとおり、破産手続開始の申立ては、最高裁判所規則(破産規則)で定める事項を記載した書面(破産手続開始の申立書)を提出する方式でしなければならないとされています(破産法20条1項)。
したがって、破産手続開始の申立てをするための準備として、この破産手続開始の申立書を作成する必要があります。
破産手続開始の申立書の記載事項
破産手続開始の申立書に記載しなければならない事項としては、以下のものがあります(破産規則13条1項)。
上記のほか、以下の事項も申立書への記載が望ましいとされています(破産規則13条2項)。
- 債務者の収入・支出の状況、資産・負債の状況
- 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
- 債務者の財産に関してされている他の手続・処分で申立人に知れているもの
- 債務者について現に係属する破産事件・再生事件・更生事件があるときは、当該事件が係属する裁判所・当該事件の表示
- 関連債務者について破産事件・再生事件・更生事件があるときは、当該事件が係属する裁判所、当該事件の表示、関連債務者の氏名・住所
- 債務者について外国倒産処理手続があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
- 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の名称・主たる事務所の所在地・組合員の数・代表者の氏名
- 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者がいるときは、当該者の氏名・住所
- 債務者について営業許可機関があるときは、その機関の名称・所在地
- 申立人・申立代理人の郵便番号・電話番号・FAX番号
破産手続開始の申立書に添付する書類・資料
破産手続開始の申立書に破産規則で定める事項を記載しただけではまだ足りません。
破産手続開始の申立書には、最高裁判所規則(破産規則)で定める事項を記載した債権者一覧表を添付する必要があります(破産法20条2項、破産規則14条1項)。
また、債権者一覧表のほか、以下の書類を添付しなければならないとされています(破産規則14条3項)。
- 法人の登記事項証明書
- 破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表・損益計算書
- 債務者の財産目録
- 住民票の写し(本籍の記載が省略されていないもの)
- 破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表・損益計算書
- 債務者の破産手続開始の申立て前1か月間の収入・支出を記載した書面
- 確定申告書、源泉徴収票写しその他の債務者の収入の額を明らかにする書面
- 債務者の財産目録
さらに、裁判所は、申立てに際して、「破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権及び破産財団に属すべき財産の状況に関する資料その他破産手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる」とされています(破産規則15条)。
そのため、債権者一覧表や破産規則14条3項で定める書類のほか、破産債権や財産に関する疎明資料、破産に至った事情等を記載した報告書などの添付を求められることもあります。
どのような追加書類・資料が必要となるのかは裁判所によって若干運用が異なります。したがって、申立て前に、あらかじめ必要書類を確認しておく必要があるでしょう。
破産手続開始の申立ての管轄
破産手続開始の申立ては、破産手続開始の申立書を、裁判管轄のある裁判所に申し立てる方式で行わなければなりません。
要するに、申立てをしなければならない裁判所は、破産法で決められているのです。どこの裁判所に申立てをしてもよいわけではありません。
破産法上、破産事件の職分管轄は、簡易裁判所でも家庭裁判所でも高等裁判所でも最高裁判所でもなく、地方裁判所にあるとされています。
破産事件の土地管轄は、原則として、当該法人の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所とされています(破産法5条1項)。
例えば、東京都千代田区に主たる営業所がある法人や個人事業者が破産手続開始を申し立てる場合には、東京地方裁判所に申し立てる必要があるということです。
ただし、外国に主たる営業所がある場合には、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に管轄があります。
また、営業所が無い場合には、その普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄することになっています。普通裁判籍は、個人の場合はその住所地、法人の場合は代表者の住所地を管轄する地方裁判所です。
なお、上記のいずれにも該当しない場合は、債務者の財産の所在地または債権については裁判上の請求をすることができる地を管轄する地方裁判所が管轄することになります(破産法5条2項)。
破産手続開始の申立手数料等の納付
破産手続開始の申立てに際しては、申立ての手数料等の費用や郵券を裁判所に納付する必要があります。
申立てに際して必要となる費用としては、申立ての手数料と予納金(官報公告費)があります。
自己破産・準自己破産申立ての手数料は1000円です。債権者申立ての場合には、2万0000円となります。これらは、収入印紙によって納付します。手数料は、全国一律です。
なお、個人破産の場合は、破産申立てだけでなく免責許可の申立ても必要です。免責許可の申立ての手数料は500円です。したがって、個人の自己破産では、合計で1500円の手数料がかかります。
官報公告費は、破産手続の場合、1万5000円前後です。こちらは、現金または銀行振込等の方法によって支払います。裁判所によって金額が異なる場合があります。
上記費用のほか、申立てに際しては、郵券(郵便切手)を納付する必要があります。どの種類の切手を何枚納付するかは裁判所によって異なるので、あらかじめ確認しておく必要があります。
東京地方裁判所における破産手続開始の申立ての方式(即日面接)
東京地方裁判所本庁では、破産手続開始の申立てについて、即日面接という独特の運用をとっています。
即日面接とは、破産手続開始の申立てをした即日(または申立日から3日以内)に、申立代理人が裁判官と面接を行い、破産手続開始の要件を充たしているか、充たしているとしてどのように破産手続を進めるか等について協議する申立て手続です。
即日面接を行うことによって、申立てから速やかに破産手続開始決定が出されることになり、非常にスピーディに手続が進むことになります。
ただし、即日面接は、申立代理人弁護士が就いている場合しか利用できません。
また、特定管財事件となるような大規模事件の場合には、即日面接ではなく、事前に裁判所と協議して進行を協議することがあります。
なお、即日面接は東京地方裁判所本庁独特の運用です。東京地方裁判所立川支部も含め他の裁判所では行われていません(ただし、横浜地方裁判所本庁では、即日面接と類似する運用として、早期面接が行われることがあります。)。