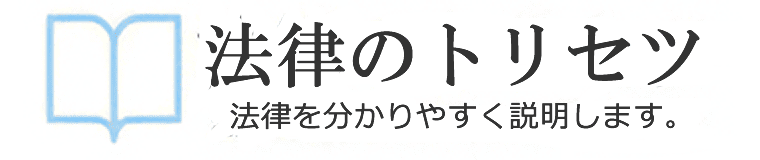この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。

貸金業法とは、「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資すること」を目的とする法律です。
具体的には、貸金業の登録制度、業務内容の適正化、貸金業者の組織する団体の認可制度などを定めています。
貸金業法とは
貸金業法とは,貸金業の登録制度、業務内容の適正化、貸金業者の組織する団体の認可制度などについて定める法律です。
かつては「貸金業の規制等に関する法律(略称として貸金業規制法)」という名称でしたが,平成18年の改正により,名称も貸金業法に改められました。
その目的は,「貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ,貸金業を営む者について登録制度を実施し,その事業に対し必要な規制を行うとともに,貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け,その適正な活動を促進することにより,貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し,もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに,国民経済の適切な運営に資すること」にあります(貸金業法第1条)。
この貸金業法は、「利息制限法」「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」とともに「貸金三法」と呼ばれています。借金の債務整理をする際にも、重要な意味を持つ法律です。
貸金業法の改正
旧貸金業規制法には,いくつかの問題点が指摘されていました。その最たるものが,いわゆる「みなし弁済」と呼ばれる制度です。
みなし弁済とは,利息制限法所定の制限利率を超える利息の支払いがあった場合でも,一定の要件を満たせば,有効な利息の弁済があったものとみなす制度です。
本来,利息制限法に違反する利息は無効のはずですが,これを有効なものとしてしまうため、みなし弁済が認められると利息制限法の消費者保護の趣旨を骨抜きにしてしまいます。その結果,グレーゾーン金利の弊害が助長されていました。
これに対しては,消費者団体や弁護士・司法書士らから批判がなされていました。
最高裁判所はこの批判に応え,みなし弁済の適用を実質的に否定する判決(最二小判平成18年1月13日)を出しました。
そして、この判決を受けて、さらに,平成18年12月には,みなし弁済の撤廃を含む貸金業規制法の抜本的な改正がなされることになりました。
また、上記みなし弁済の撤廃のほか,年収の3分の1を超える個人への貸付けを原則として禁止する総量規制がとりいれられ,生命保険金による返済の禁止や行政処分の対象となる行為の拡大などが設けられた「貸金業法」が成立しました。
取立ての停止
前記のとおり,貸金業法は債務整理に大きな影響を及ぼす法律ですが,そのうちでも特に典型的な規制は,弁護士等の受任通知によって直接の取立てが禁止されることでしょう。
つまり,弁護士等が,貸金業者に対して,債務整理を開始したことを通知し,債務者本人への訪問・電話・FAX等による取立て行為をしないように要求した後は,貸金業者は,そのような直接の取立てをすることができなくなるという規制です(貸金業法21条1項9号)。
裁判所による特定調停の場合も同様です。裁判所から特定調停を開始する旨の書面が送達されると,やはり訪問・電話・FAX等による債務者本人への直接の取立て行為をすることが禁止されるようになります。
クレサラ事件が大きな問題となっていたことの要因の1つは,貸金業者による厳しい取り立てです。これにより,債務者が追い込まれ,自殺が多発するなどの問題が生じていました。
貸金業法による直接の取立ての禁止は,上記のような取立てによる問題を防止するための方策として設けられたのです。
これにより,債務者は,生活の平穏を取り戻すことができるとともに,債務整理をする準備ができるようになります。