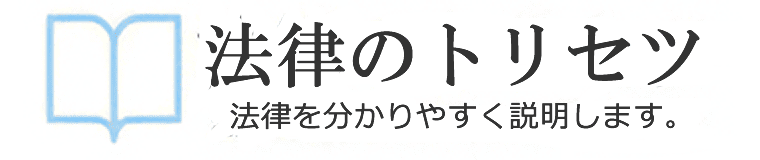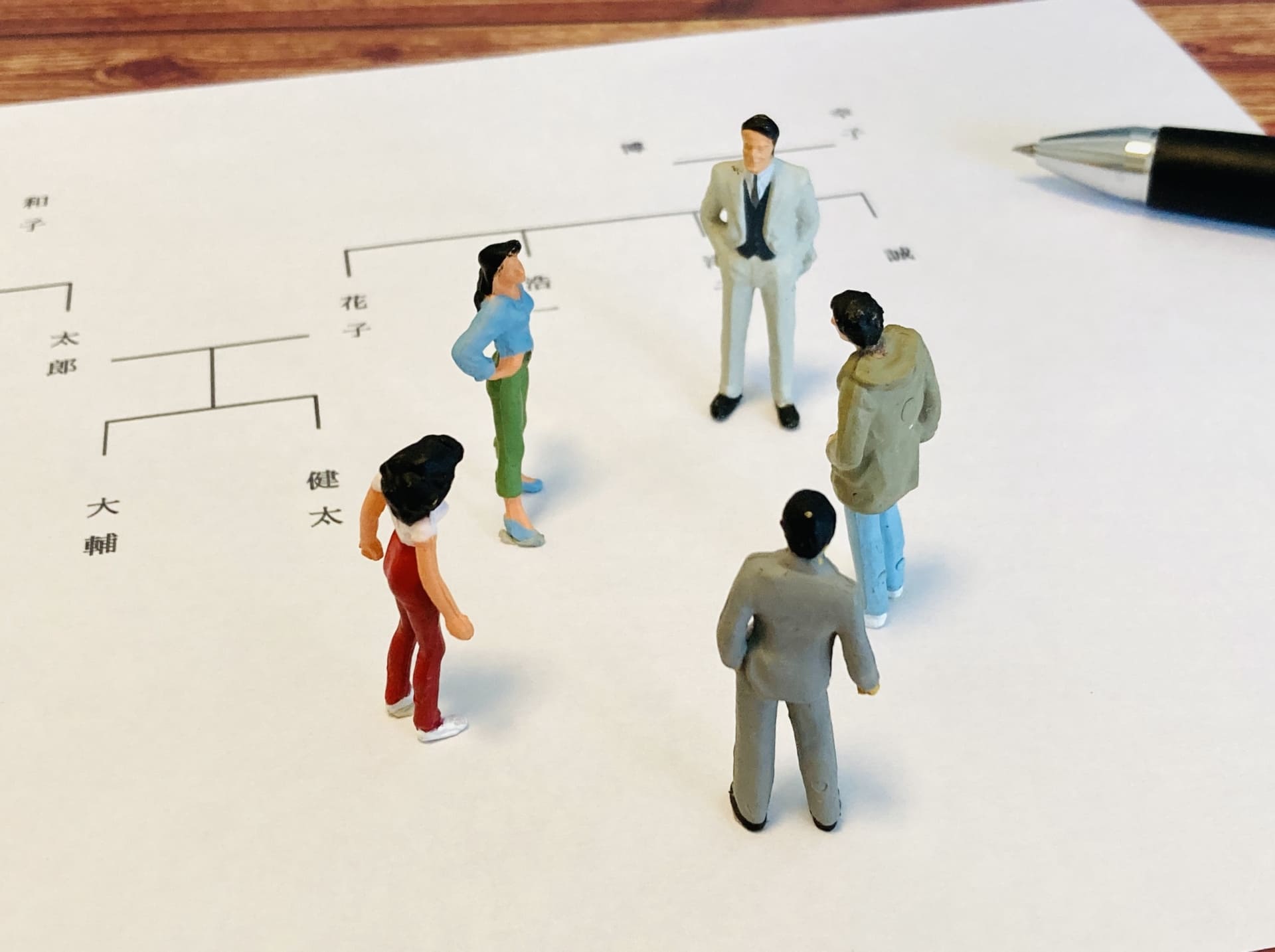この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
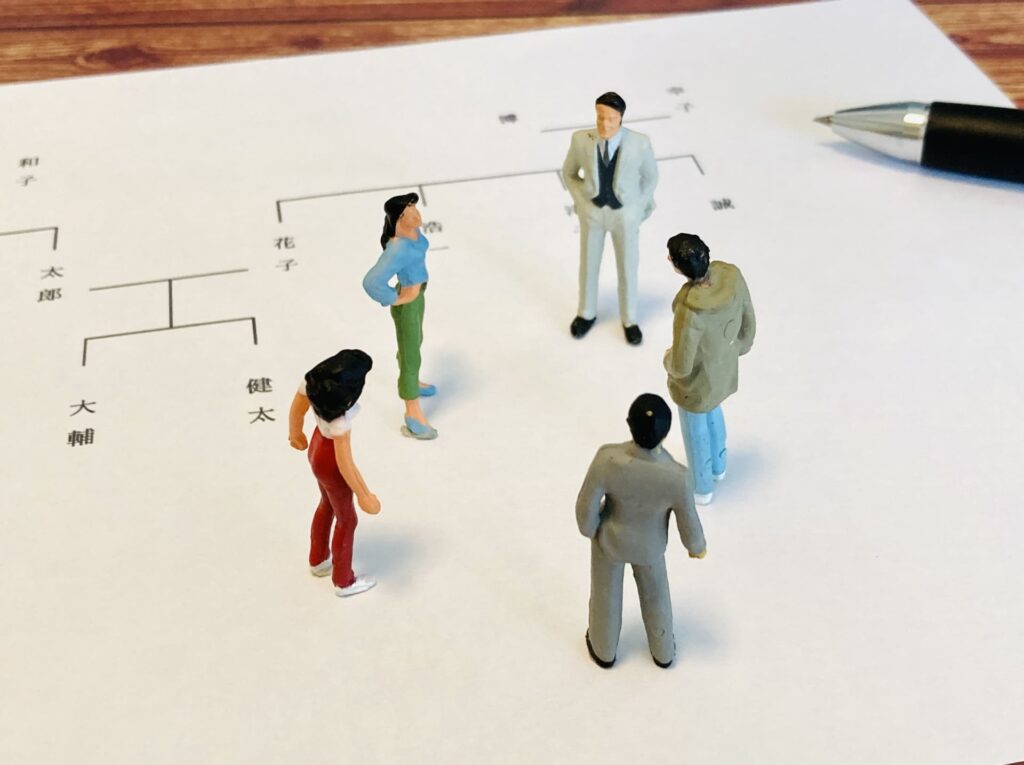
遺言(いごん・ゆいごん)とは,被相続人の最終の意思表示のことです。遺言を作成しておくことにより,相続財産の承継について,被相続人の意思を反映させることが可能となります。
ただし,遺言はただの遺書とは違います。法律で定められた方式で作成されたものでなければ法的効果を生じません。法律で定められた遺言の方式としては,自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言などがあります。
遺言とは?
「遺言」は,一般的には「ゆいごん」と読まれますが,正式に言うと,法律上は「いごん」と読まれます。法的にいうと,遺言とは,被相続人の最終の意思表示のことです。
最終の意思表示といっても,いわゆる「遺書」のように,死の間際にした意思表示という意味ではありません。その遺言をした人(遺言者)が,その人の死に最も時間的に近接した時点でした意思表示という意味です。死の間際である必要はありません。
遺言で意思表示をしておくと、自分の死後に生じることになる財産の処分等の法律行為に対して、自分の意思表示の効力を及ぼすことできます。
この遺言は,被相続人となる方(遺言者)が,相続による遺産(相続財産)の承継について,自身の意思を反映させるためにとることができる唯一といってよい方法です。
自分で築いてきた財産の帰趨を,ある程度,自分の遺志に沿った形で相続人に配分することができるのです。
また,遺言者の意思を遺せるというだけでなく,遺言をしておくことによって,相続人間での,不毛な骨肉の争い(いわゆる遺産争い)を予防しまたは最小限化させることができる意味をもっています。
その意味で,遺言は,被相続人にとって,自身の意思に基づいて遺産の相続をしてもらえるメリットだけでなく,後に残される相続人にとっても,無用な争いを最小限化できるというメリットもあります。
遺言の意義
近代私法の大原則の1つに「私的自治の原則」があります。
私的自治の原則とは,個人間の権利義務・法律関係(私法関係)については,その個人が,その自由意思に基づいて自律的に決定することができるとする原則です。
要するに,自分が私法上の権利を取得したり,それを行使したり,または,私法上の義務を負ったり,義務を履行したりすることは,自分で決めることを認める原則です。
この私的自治の原則から派生する近代私法の原則として,法律行為自由の原則があります。これは,人は,生まれてから死ぬまでの間,自分の意思に基づいて,自由に法律行為をすることができるとする原則です。
この私的自治・法律行為自由の原則は,私法関係において個人の意思・自由を最大限尊重しようというものです。
人は,生前であれば,自由に法律行為をして自分の法律関係を形成することができます。
しかし,人は死亡すれば権利義務の主体でなくなるので,本来であれば,自分の死後に生じる法律関係に影響を及ぼすことはできないはずです。
もっとも,自分が築いてきた財産等についてその死後は何も影響を及ぼすことができないとすると,その人の意思に反する結果となる可能性があり,個人の私有財産を保障する私的自治の原則の趣旨に反することになるおそれがあります。
その趣旨に沿うようにするためには,個人の権利義務に対するその人の意思は,その人の生存中のみならず,死後においても,尊重されるのが望ましいといえます。
そこで,個人の意思を尊重するため,私的自治・法律行為自由の原則を拡張し,その個人の法律関係に関する意思を,その個人の死後においても効果を生ずるようにした制度が,この遺言という制度です。
また,このように個人の死後においても遺言を作成することによって,自由な意思に基づいて,死後の法理関係を形成できることを「遺言自由の原則」と言います。
遺言の効果
前記のとおり,遺言は,個人の意思を,死後においても尊重しようという制度です。したがって,遺言を作成しておけば,自分の死後であっても,その遺言に従って法理関係が形成されることになります。
特に,相続財産は被相続人が築いてきたものですから,この相続財産に対しては,遺言の効力が大きく及びます。
例えば,法定相続分と異なる相続分を指定したり(これを指定相続分といいます。)、法定相続人ではない第三者に相続財産を遺贈したりできます。
具体的にいうと,相続人が複数いる場合に,遺産(相続財産)のうち不動産は配偶者に、預貯金は長男に、自動車は長女に,などのように相続における財産の配分の仕方を決めておくことなどができます。
他方、相続の制度は,公権的な制度としての意味合いも持っています。
したがって,遺言を作成したとはいえ,あらゆる法律関係について定めておくことができるというわけではなく,遺言で定めることができる事項(遺言作成によって法的効果が生ずる事項)には,一定の制限があることも事実です。
例えば、法定相続人(兄弟姉妹を除く)には,遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分として遺留分が保障されています。遺言をしても,遺留分を侵害する内容を定めることはできません(仮にそのような内容を定めても無効となります。)。
また,財産関係については比較的多くのことを遺言によって定めることができますが,財産関係よりも公共性の強い身分関係については,遺言で定めることができる非常に事項は限られています。
例えば、身分関係については,死後認知など一定の場合を除いて,遺言書に記載したとしても法的な効力を生じません。
したがって,遺言を作成する場合には,その遺言に定めようとしている内容が,はたして遺言しておくことで法的な効果を生ずるのかを検討しておく必要があります。
遺言作成の方式
遺言は要式行為です。法律の定めに従った方式で作成しなければ,法的効果を生じません。つまり,単に紙に書き残していたという程度では,法的な効果を生じない無意味なものとなってしまう可能性があるということです。
遺言作成の代表的な方式としては,自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言があります。
遺言を作成する場合には,これらの方式に従って作成しなければ,効力を生じないのが原則です(ただし,若干の例外はあります。)。