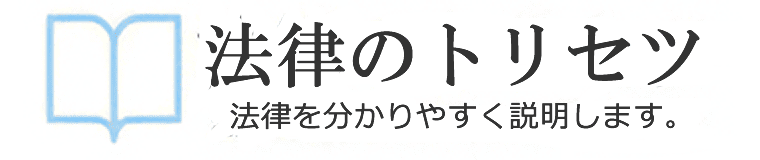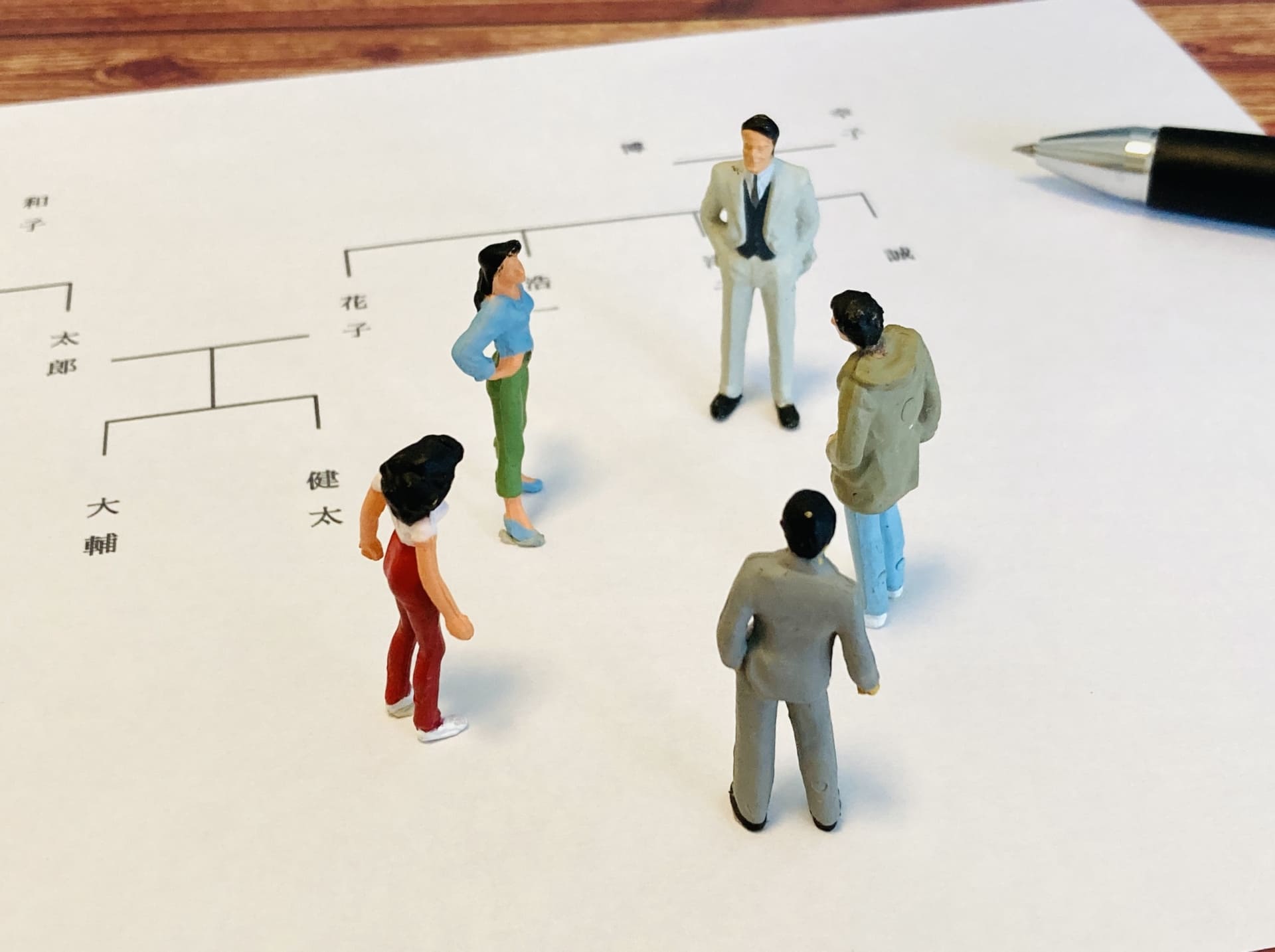この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
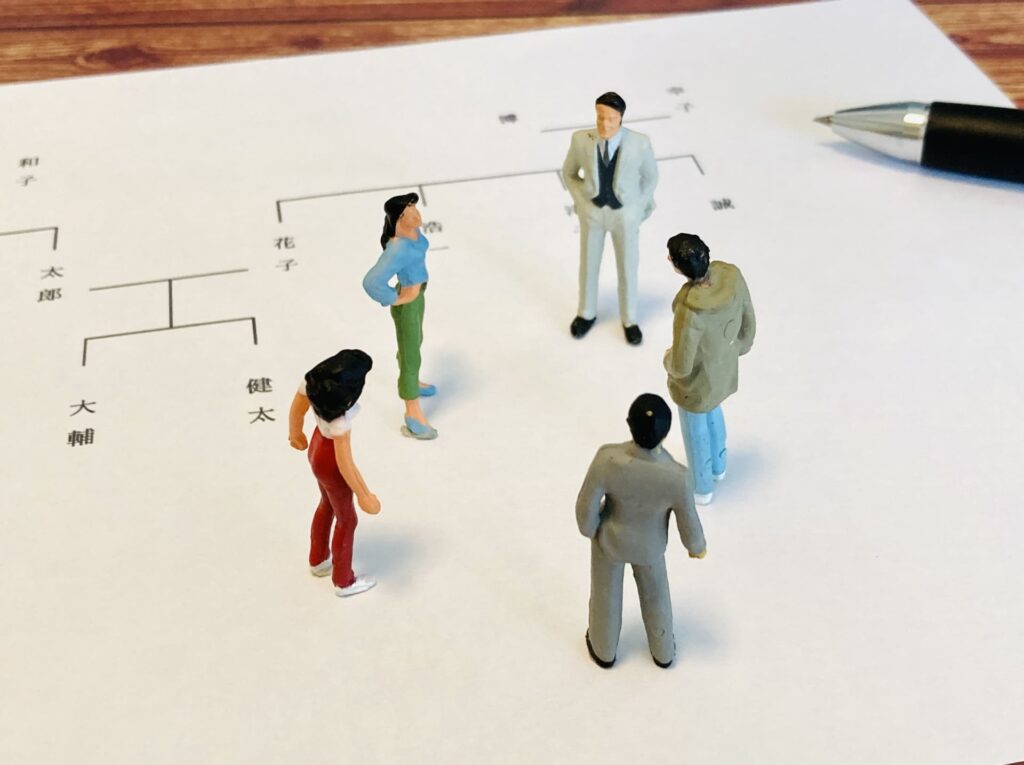
遺留分を有する者を「遺留分権利者」と言います。遺留分権利者になるのは,兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者,子または直系尊属)です。遺留分権利者の代襲相続人も,遺留分権利者となります。
遺留分権利者とは?
遺留分を有する人のことを「遺留分権利者」といいます。
遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合,遺留分権利者は,受遺者または受贈者に対し,遺留分侵害額の支払いを請求できます。
令和元年(2019年)7月1日より前に相続が開始していた場合であれば,遺留分権利者は,受遺者または受贈者に対し,遺留分侵害額請求ではなく,遺留分減殺を請求できます。
他方,遺留分を侵害しているために侵害額請求や減殺請求に応じなければならない受遺者や受贈者のことを「遺留分義務者」といいます。
当然のことながら,誰でも遺留分権利者になれるわけではありません。誰が遺留分権利者となるのかについては,民法で定められています。
民法上,遺留分権利者とされているのは,以下の人です。
兄弟姉妹を除く法定相続人
民法 第1042条
- 第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
- 第1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
- 第2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
- 第2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分は、法定相続人に最低限度の取り分を保障する制度です。したがって,遺留分権利者となるのは,法定相続人です。
もっとも,すべての法定相続人が遺留分権利者となるわけではありません。遺留分権利者となることができるのは,「兄弟姉妹を除く法定相続人(子・直系尊属・配偶者)」だけです(民法1042条1項)。
被相続人の兄弟姉妹は,例え法定相続人になることがあっても,遺留分侵害額の請求等はできない点には注意が必要です。
遺留分制度は,被相続人の財産に依拠してきた相続人の生活を保障すること、相続人は、遺産(相続財産)の形成に貢献していたことから、遺産に対し潜在的な持ち分が認められることなどを制度の根拠としています。
そのため,通常,被相続人と別家庭を有し,被相続人の財産に依拠しているとはいえず,また,遺産形成に貢献しているともいえない兄弟姉妹については,遺留分権利者から外されているのです。
なお,兄弟以外の相続人と言っても,法定相続人には順位がありますから,遺留分権利者となるのは,その順位に従って法定相続人となる人だけです。
したがって,配偶者は常に遺留分権利者となりますが,子がいる場合には子が遺留分権利者となり,直系尊属は遺留分権利者になりません。
相続欠格に該当する場合
民法 第891条
- 次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 第1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 第2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 第3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 第4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 第5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法891条各号に規定された相続欠格事由に該当する場合,被相続人の配偶者・子・直系尊属等であっても,相続権を失います。
そのため,兄弟姉妹を除く法定相続人であっても,この相続欠格に該当する場合には遺留分も失い,遺留分権利者になれません。
相続人から廃除されている場合
民法 第892条
- 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
遺留分を有する推定相続人に,被相続人に対する虐待等の事由があった場合,被相続人はその推定相続人から相続資格を剥奪することを家庭裁判所に請求できます。これを「推定相続人の廃除」と言います(民法892条)。
兄弟姉妹を除く法定相続人であっても,相続人からの廃除が家庭裁判所により決定された場合には遺留分も失い,遺留分権利者になれません。
相続放棄をした場合
民法 第939条
- 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄をすると、その放棄者は、相続の始めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
そのため、子・直系尊属・配偶者であっても、相続放棄した場合、その放棄者は遺留分権利者にななれません。
代襲相続人
前記のとおり,遺留分権利者となるのは,「兄弟姉妹を除く法定相続人」です。さらに、この兄弟姉妹を除く法定相続人の代襲相続人も、遺留分権利者となることができます。
ただし,被代襲者である法定相続人が相続放棄をした場合,代襲相続が発生しませんから,その代襲者となるべき人も,遺留分権利者になることはありません。
また,被代襲者である法定相続人が遺留分を放棄していた場合にも,その代襲者は,遺留分権利者になりません。
もっとも,被代襲者である法定相続人が相続欠格者である場合または相続人から廃除されている場合には代襲相続が発生するので、その代襲者は遺留分権利者になることができます。
遺留分権利者からの承継人
遺留分権利者から権利を承継した人は、遺留分権利者そのものではありませんが、遺留分権利者と同様,承継した権利の範囲内で,遺留分侵害額請求または遺留分減殺請求をすることができます。
この承継人には,遺留分権利者の相続人・包括受遺者・相続分の譲受人などの包括承継人だけでなく,個別的な遺留分侵害額請求権を譲り受けた者などの特定承継人も含まれます。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
民法3(親族法・相続法)第5版
著者:我妻榮ほか 出版:勁草書房
いわゆる「ダットサン」シリーズの復刻版。読みやすいので、初学者でも利用できます。意外と情報量もあるので、資格試験の基本書として利用することも可能でしょう。
資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
民法VI 親族・相続 (LEGAL QUEST)第8版
著者:前田陽一ほか 出版:有斐閣
家族法全体の概説書。条文・判例から書かれているので、学習の早い段階から利用できます。情報量もあるので、資格試験の基本書として十分でしょう。
親族・相続(伊藤真試験対策講座12)第4版
著者:伊藤真 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。