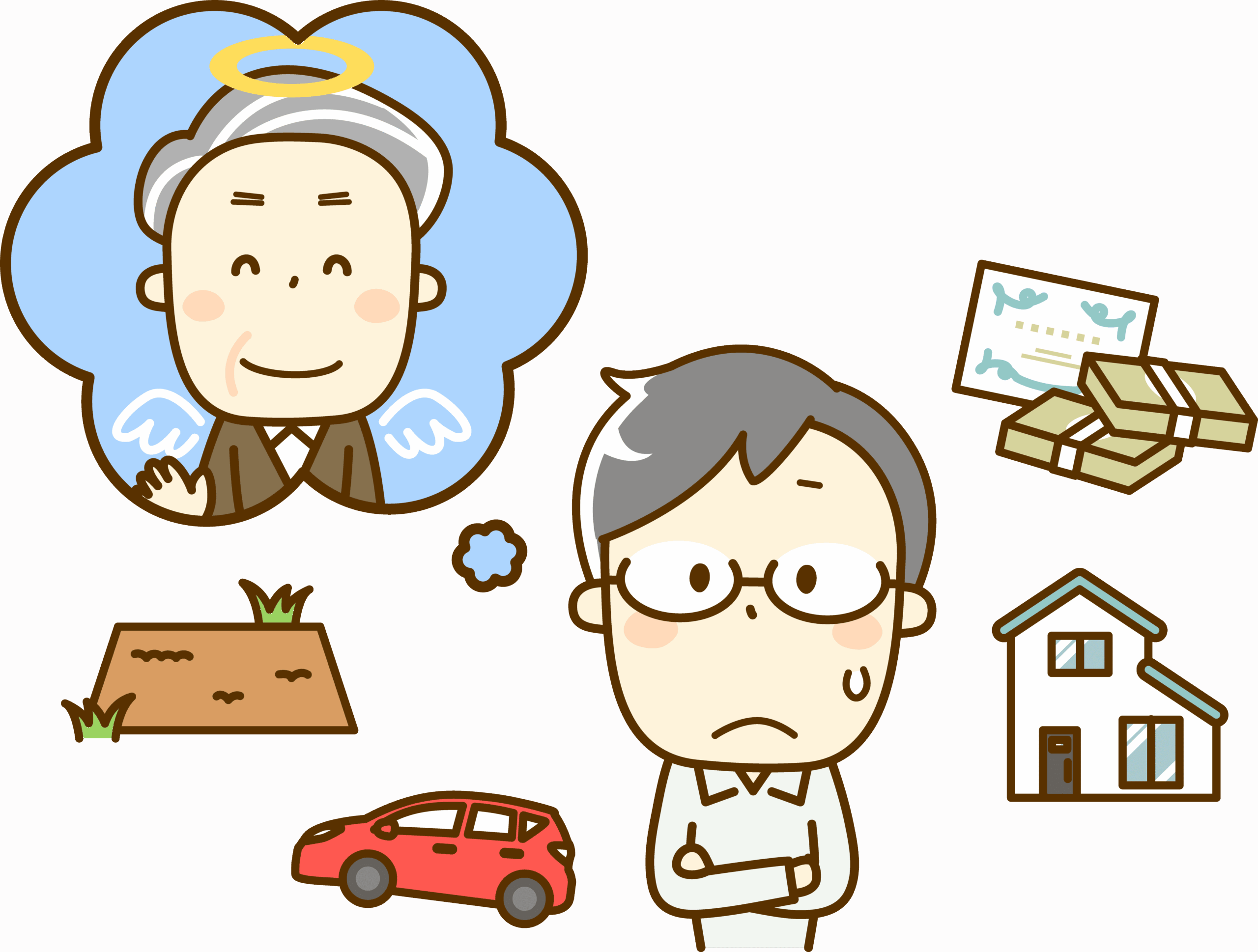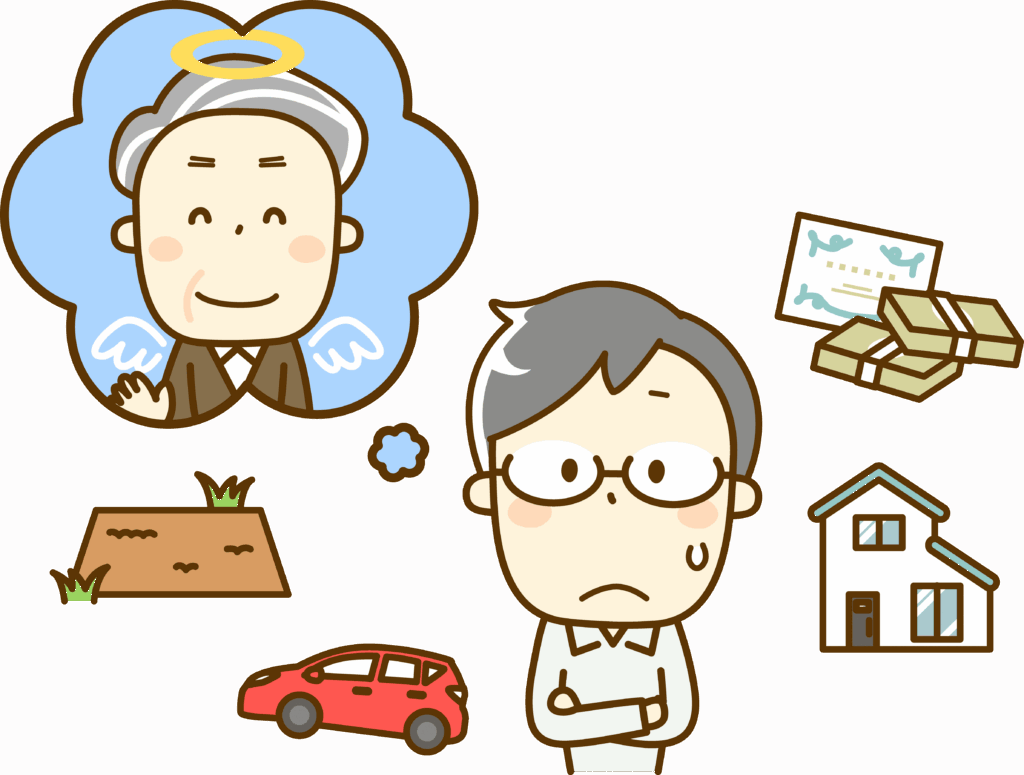
法は,相続人に,相続をするのか,相続をしないのかの選択権を与えています。これを,「相続人の選択権」と呼んでいます。相続することを相続の承認といい、しないことを相続放棄といいます。
相続人の選択権
相続が開始されると,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。
一切の権利義務が承継されるということは,つまり,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も承継されるということです。
したがって,例えば,被相続人に借金があったという場合には,相続によって,相続人がその借金を負担しなければならないということになります。
しかし,負債よりも資産の方が多いとは限りません。それにもかかわらず,無条件に相続人が負債も受け継がなければならないとすると,あまりに相続人に不利益を被らせてしまうおそれがあります。
また,逆に,負債よりも資産の方が多いからといって,必ずしも相続人が相続を受けたいと思うとも限りません。相続を受けることを潔しとしないという人もいないとはいえないでしょう。
それにもかかわらず無条件に相続ということになれば,そのような相続人の意思を無視することにもなります。
そこで,法は,相続人に,相続をするのか,相続をしないのかの選択権を与えています。これを,「相続人の選択権」と呼んでいます。
相続するという選択をする場合(相続の承認)
相続をするという意思表示のことを,「相続の承認」といいます。相続を承認した場合,相続人は,相続財産を包括的に承継することになります。この相続の承認には,単純承認と限定承認があります。
単純承認とは,何らの留保もつけずに相続を受け入れいれるというものです(民法920条)。
他方,限定承認とは,相続財産のうちで,マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多かった場合には,相続を受け入れるという留保付きの承認のことをいいます(民法922条)。
相続しないという選択をする場合(相続の放棄)
相続の承認に対して,相続をしないという意思表示のことを,「相続放棄」といいます。相続放棄をすると,その放棄をした相続人は,相続開始のときから相続人ではなかったものとみなされます。
したがって,相続財産のうちで負債の方が明らかに大きいという場合には,相続放棄をすることになるでしょう。
負債の方が大きいのかが不明であるという場合には,限定承認を選択することになります。
ただし,相続人が,相続財産を処分するなどの一定の行為をした場合には,当然に相続を単純承認したものとみなされてしまう場合があります。これを法定単純承認といいます(民法921条)。
法定単純承認が成立すると,それ以降は,相続放棄や限定承認ができなくなりますので注意が必要です。