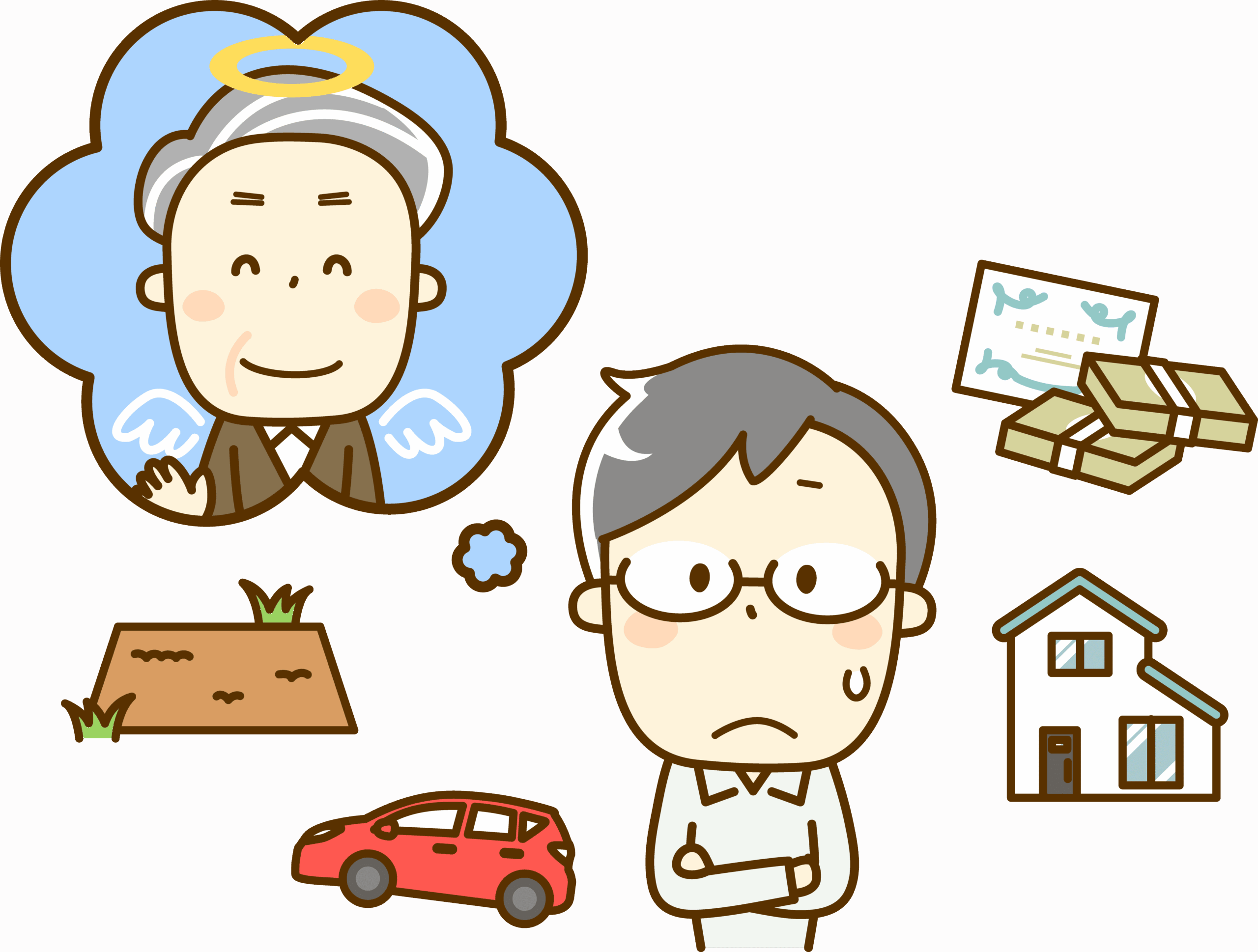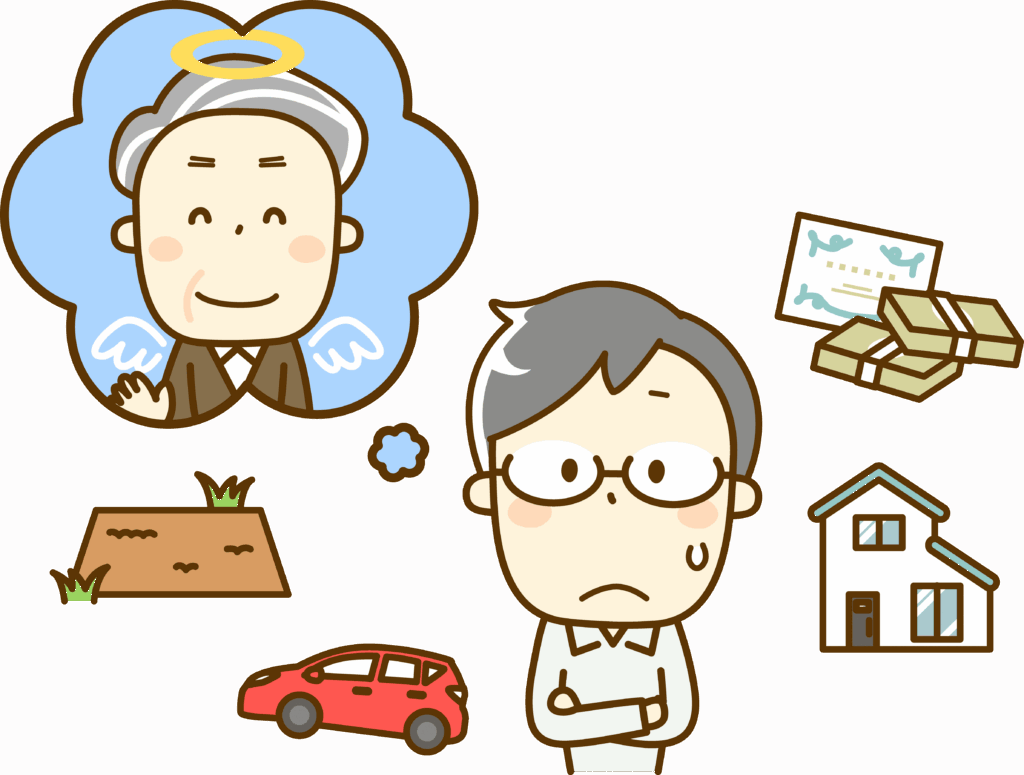
法定単純承認とは、法的安定性の見地から,ある一定の場合には,当然に相続を単純承認したものとして扱うという制度です(民法921条)。法定単純承認が成立すると、以降は、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。
法定単純承認とは?
民法 第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
第1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
第2号 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
第3号 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。民法 第602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
第1号 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
第2号 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
第3号 建物の賃貸借 4年
第4号 動産の賃貸借 6箇月民法 915条 第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人が,被相続人の権利義務を何らの限定なく包括的に承継する旨の意思表示をすることを,相続の単純承認といいます(民法920条)。
単純承認をするということは,被相続人の権利義務を無限定に承継するということですから,被相続人に借金などの債務や負債があった場合には,その借金などの負債や債務もすべて,相続人が引き継いでしまうということです。
もちろん相続をしないという選択肢もあります。相続人は相続放棄をすることもできます。また,負債を弁済してもなお相続財産が残っていれば,その分だけ相続するという限定承認という方法を採ることも可能です。
しかし,法的安定性の見地から,ある一定の場合には,当然に単純承認したものとして扱うという制度があります。それが,「法定単純承認」という制度です。
法定単純承認が成立すると,相続放棄や限定承認をすることができなくなってしまいます。
したがって,被相続人に借金などがあるような場合には,この法定単純承認が成立してしまうかどうかについて,注意をしておかなければなりません。
この法定単純承認は,以下の場合に成立します。
相続財産の処分行為
法定単純承認の事由の1つは,相続財産の一部または全部を処分することです(民法921条1号)。
相続財産を一部であっても処分するということは,相続財産を自分のものとして扱う意思があるということの現れですから,法定単純承認事由となります。
また,資産だけ手に入れて負債だけを相続放棄等によって逃れようという行為ができないようにするという意味もあります。
ただし,相続財産の価値を損なわないようにするための保存行為や,民法602条の短期賃貸借は処分行為に当たらないため,これらの行為をしても法定単純承認は当たらないとされています。
熟慮期間の経過
相続人には相続をするかしないかについての選択権があります。
しかし,いつまでも決めないでいると法的な安定性を害し,他の利害関係人に迷惑を及ぼす可能性もあるため,一定の期間内にどうするのかを決めなければならないとされています。
この一定の期間のことを「熟慮期間」といいます。熟慮期間は,具体的には,相続の開始を知ったときから3か月以内です(民法915条1項本文)。
したがって,相続人は,単純承認となってしまうことを望まない場合には,この熟慮期間の3か月内に,限定承認か相続放棄の手続をとらなければならないということになります。
この熟慮期間内に,相続の放棄も限定承認もしなかった場合には,法定単純承認となってしまいますので,注意をしておく必要があるでしょう(民法921条2号)。
なお,熟慮期間のスタートは,相続開始時ではなく,あくまで相続人が相続開始(被相続人が亡くなったこと)を知った時です。相続開始を知らなければ,熟慮期間は進行しません。
また,この熟慮期間は,借金などがあるかどうかが分からず調査中であるというような場合には,家庭裁判所に対して,熟慮期間の延期を申述できます(民法915条1項ただし書き)。
背信行為
法定単純承認は,相続人が背信行為をした場合にも生じます。具体的にいうと,ここでいう背信行為とは,相続財産の隠匿,消費,相続財産目録への悪意の不記載です(民法921条3号)。
相続財産目録への不記載における悪意とは,「相続債権者を害する意思で」という意味です。積極的に相続債権者を害する意思が必要とされています。過失で書き忘れてしまったりした場合などは,法定単純承認事由には当たりません。
これらの行為は,相続債権者に対する背信行為です。
限定承認や相続放棄は,いってみれば相続債権者よりも相続人の権利を保護しようという制度ですが,上記のような背信行為を行う者まで,相続債権者よりも優位に扱う必要はないことから,法定単純承認となるとされています。
この背信行為については,それが仮に限定承認や相続放棄をした後であっても,法定単純承認となるとされています。つまり,限定承認や相続放棄をしていた場合であっても,それらの効力がなくなってしまうということです。
ただし,相続放棄の場合には,放棄の後に背信行為をした時点で,すでに放棄によって相続人となった人が相続を承認していれば,放棄の効果はなくならないものとされています。