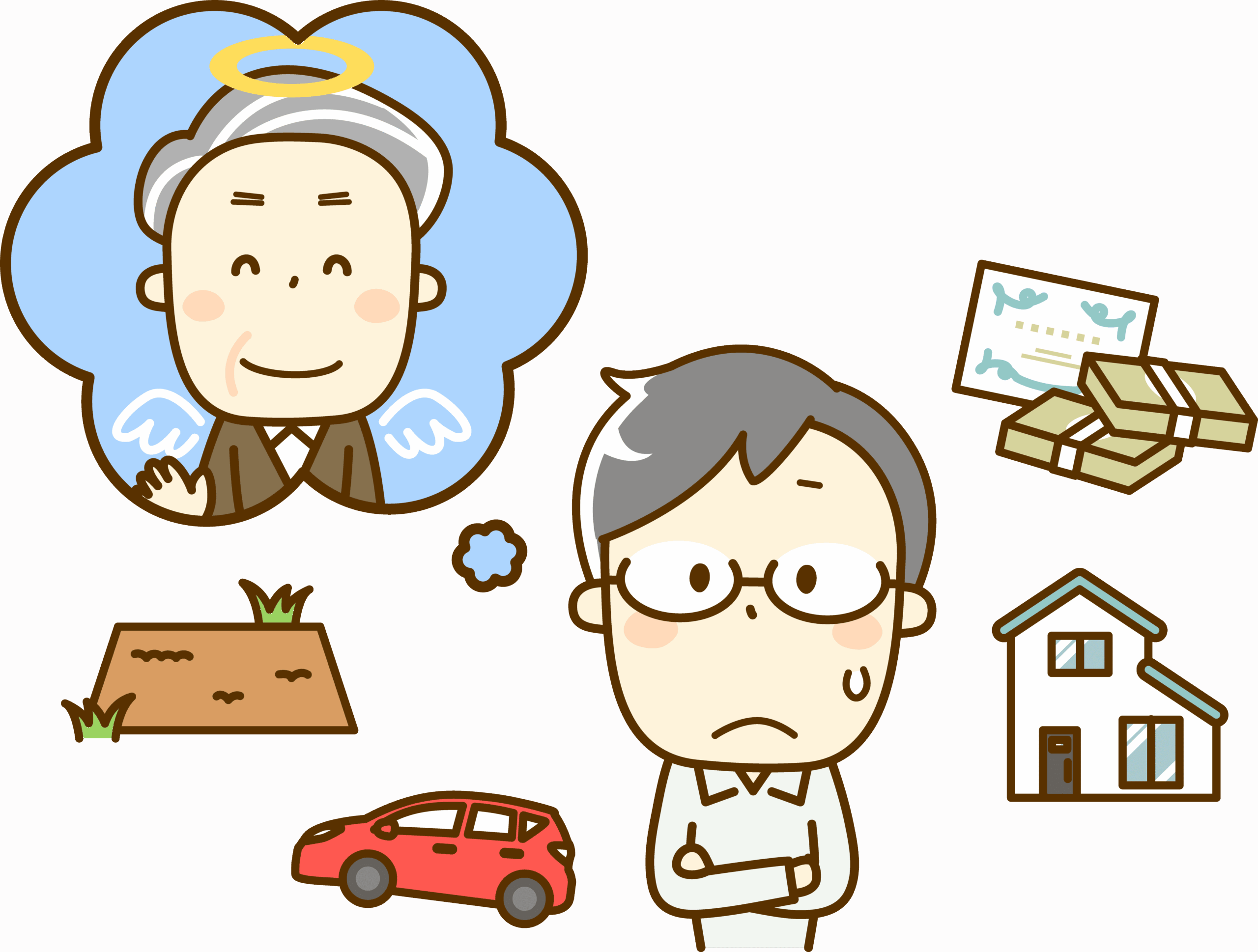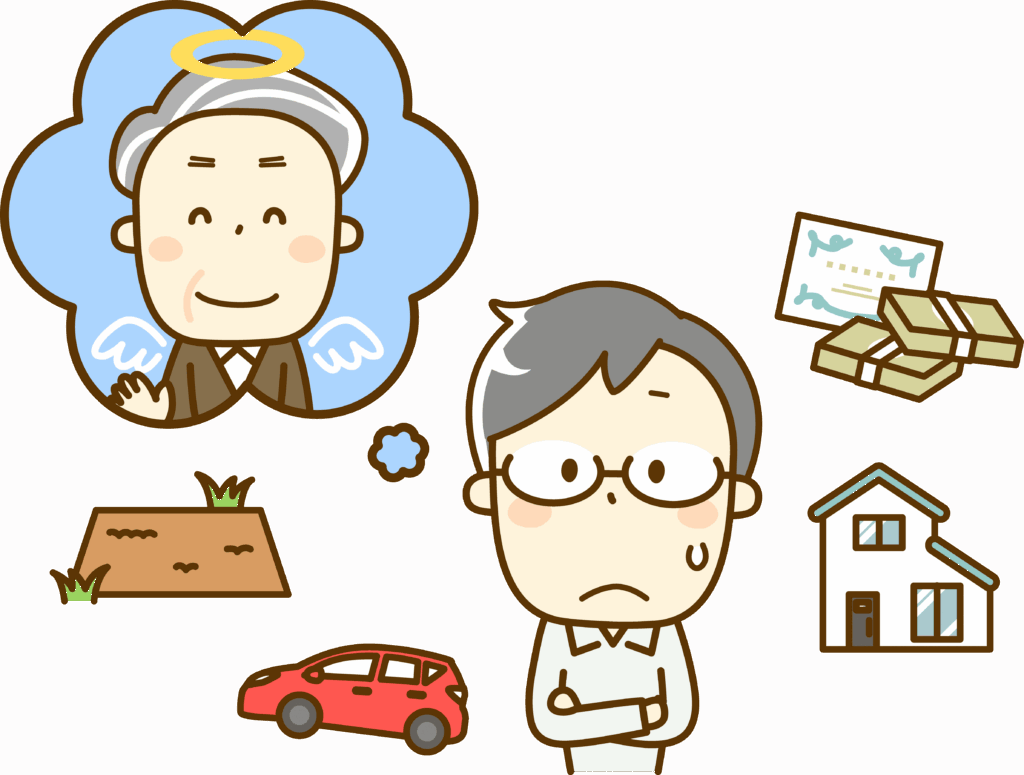
相続放棄や限定承認はいつでもできるわけではありません。相続放棄・限定承認ができる期間は限られています。この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間は、相続の開始を知った時から3か月とされています(民法915条1項)。この熟慮期間を経過すると、法定単純承認が成立してしまい、以降、相続放棄や限定承認はできなくなります(民法921条2号)。
法定単純承認と熟慮期間
民法 第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
第1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
第2号 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
第3号 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。民法 915条 第1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続においては,プラスの財産・資産だけでなく,マイナスの財産・負債も,被相続人から相続人に包括承継されることになります(民法896条)。
もっとも,相続という相続人にとってはコントロールできない事情によって,相続人が大きな負債を抱えることになってしまうことがあるというのでは,あまりに相続人に酷です。
そこで,法は,相続人に対して,相続をするかしないかの選択権を与えています。相続をする旨の相続人の意思表示を相続の承認といい,相続をしない旨の意思表示を相続放棄といいます。
また,相続を承認する場合でも,すべてを無条件に受け入れるという単純承認と,相続財産によって負債を弁済し,それを超える部分だけ相続を承認するという留保付きの限定承認とがあります。
相続財産のうちに負債がある場合には,上記の相続放棄や限定承認などをすることによって,相続人は負債を免れることができるのです。
もっとも,法的安定性を図るため,法は,一定の事由が発生した場合には,単純承認をしたものとみなし,その後に相続放棄や限定承認ができないようにするという制度を設けています。これを「法定単純承認」と呼んでいます(民法921条)。
この法定単純承認となる事由の1つに,熟慮期間という期間制限があります。すなわち,一定期間が経過した場合には,法定単純承認が成立し,それ以降は相続放棄や限定承認ができなくなるというものです(民法915条1項本文、921条2号)。
相続放棄・限定承認ができる期間
前記のとおり,法定単純承認には,熟慮期間という相続放棄や限定承認についての期間制限が設けられています。
具体的には「相続人が相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄又は限定承認の手続をしなかった場合」です。
つまり,相続人が相続開始を知った時から3か月を経過してしまうと,相続放棄や限定承認ができなくなってしまうということです。この3か月という期間が熟慮期間ということになります。
熟慮期間3か月の起算点は,「相続人が相続開始を知った時」です。単に相続が開始したというだけで熟慮期間が進行するわけではありません。あくまで当該相続人が,相続の開始(被相続人の死亡)を知った時から熟慮期間が進行するのです。
したがって,被相続人が亡くなったことを知らないまま3か月を経過してしまったとしても,法定単純承認は成立しません。あくまで,相続開始を知った時から考えるということです。
極端にいえば,被相続人が亡くなったことを知らないまま数年が経過した後に,はじめて被相続人が亡くなったことを知ったという場合には,その知った時から3か月以内であれば,なお相続放棄は可能なのです。
熟慮期間の伸長
前記のとおり,熟慮期間が経過してしまうと,もはや相続放棄や限定承認はできなくなってしまいます。
もっとも,熟慮期間の3か月という期間は,非常に短い期間です。
このわずか3か月の間に相続財産を調査して,相続を承認すべきか,放棄すべきか,または限定承認すべきかを検討しなければならないのは,場合によっては非常に難しいこともあり得るでしょう。
そのため,この熟慮期間は延長することができるとされています。具体的には,家庭裁判所に対して,熟慮期間伸長の申立てをする必要があります(民法915条1項ただし書き)。
そして,家庭裁判所によって熟慮期間の伸長が認めれれば,3か月を経過しても,その伸長された期間内である限り,相続放棄や限定承認が可能となるのです。
ただし,熟慮期間の伸長も裁判ですから,必ず伸長が認められるとは限りません。したがって,やはりできる限り相続開始を知った時から3か月以内に方針を決定できるようにしておくべきでしょう。