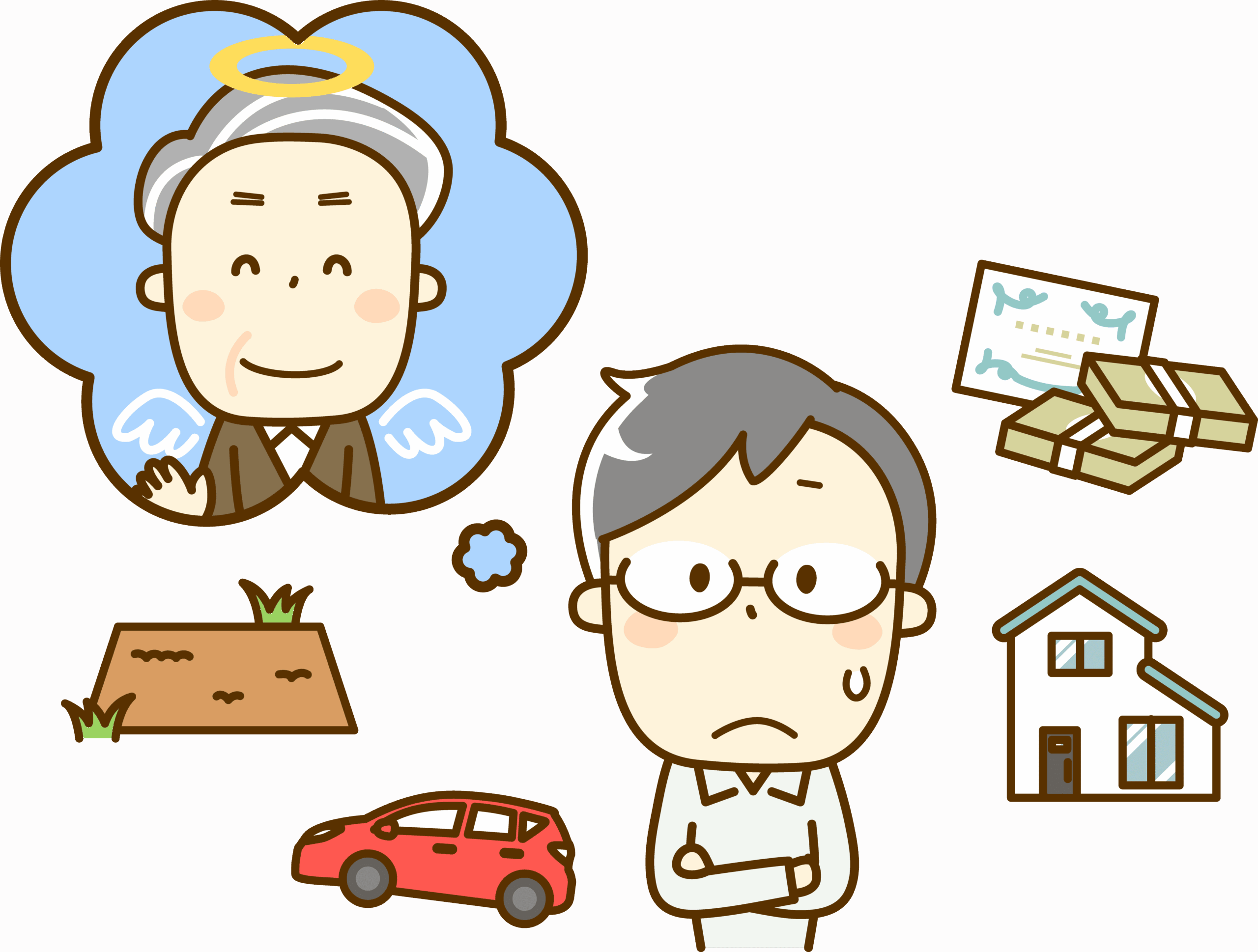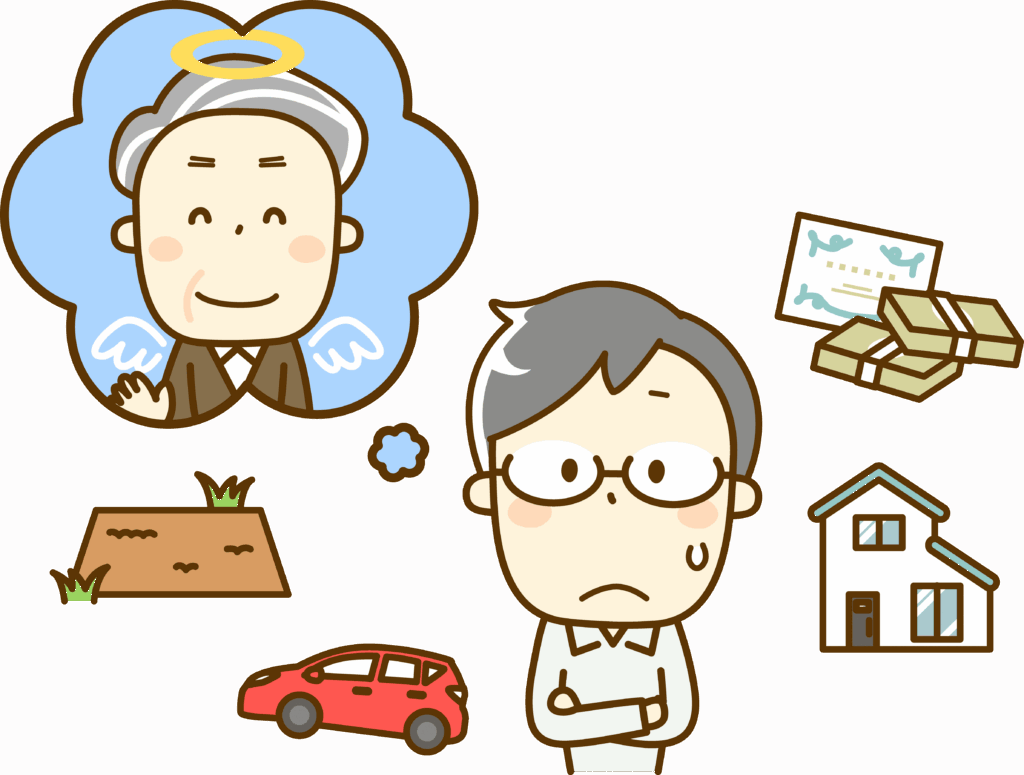
相続財産の全部または一部を処分してしまった場合、法定単純承認が成立し、以降、相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。(民法921条1号)
法定単純承認と相続財産の処分行為
民法 第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
第1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
第2号 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
第3号 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。民法 第602条
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
第1号 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
第2号 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
第3号 建物の賃貸借 4年
第4号 動産の賃貸借 6箇月
相続人には,相続をするかしないかの選択権が認められています。相続をするという選択をする場合を相続の承認といい,相続をしないという選択をする場合を相続放棄といいます。
相続の承認には2種類あります。何らの留保も付けずに相続を承認することを単純承認といい(民法920条)、相続財産によって相続債務を支払い,それでも余りがあれば相続をするという留保付きで相続を承認する場合のことを限定承認といいます(民法922条)。
もっとも,この相続放棄や限定承認は,どのような場合でもできるわけではありません。
あまりに無限定に,いつどのような場合でも相続放棄や限定承認ができるとすると,利害関係人の立場を不安定にし法的安定性を欠くからです。
そこで,民法上,一定の事由が生じた場合には,相続を無条件に受け入れるという単純承認をしたものとみなしてしまうという制度が用意されています。これを「法定単純承認」といいます(民法921条)。
この法定単純承認となる事由の1つに,相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したこと」があります(民法921条1号)。
相続財産処分行為が法定単純承認事由とされる趣旨
相続人がもし相続放棄などをするなどのであれば,相続財産を自由に処分できるはずがありません。
それにもかかわらず,相続人が処分行為をしたということは,その相続財産を自分のものとするという意思があると推認できます。
また,相続人の処分行為をみた第三者は,その相続人は相続放棄などをしないものだと信頼するでしょう。それにもかかわらず,後に相続放棄や限定承認をすると,その第三者の信頼が裏切られるおそれがあります。
このように,相続財産の処分行為という相続放棄や限定承認をすることに矛盾する行為をしたことによって発生した相続債権者等利害関係人の信頼を保護するため,相続財産を処分する行為をしたことが,法定単純承認事由とされているのです(最一小判昭和42年4月27日民集21巻3号741頁など)。
「相続財産」の処分
法定単純承認事由となる処分行為の対象は,あくまで「相続財産」です。相続財産ではない財産を処分したとしても,法定単純承認は成立しません。
例えば,生命保険金や死亡退職金などは,原則として,相続財産ではなく,受取人固有の財産と考えられています。
そのため,被相続人が亡くなって生命保険金が受取人に支払われ,その受取人がその生命保険金を使ってしまったとしても,「相続財産」の処分ではないので,法定単純承認は成立しないということです。
「処分」の意味
法定単純承認となるのは「処分」行為です。
処分行為の内容・範囲
処分行為とは,財産の現状・性質等を変更する行為をいいますが,法定単純承認となる処分行為には,相続財産の売買・贈与など法律上の処分行為だけでなく,相続財産の損壊・破損など事実上の処分行為も含まれます。
この処分行為は,相続放棄・限定承認をする前の処分行為に限られます。
相続放棄などの後に処分をした場合には,法定単純承認の問題ではなく,単に相続財産を取得した他の相続人等に対する権利侵害が問題となります。
保存行為・短期賃貸借
「保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸」は法定単純承認に当たらないとされています(民法921条1号ただし書き)。
保存行為とは,財産の現状や価値を維持する行為です。例えば,相続財産中の債権について消滅時効の更新の措置をとることや,老朽化して倒壊の危険がある建物の修繕等がこれに当たります。
また,民法第602条に定める期間を超えない賃貸借とは,いわゆる「短期賃貸借」ですが,これも処分行為には当たらないとされています。
相続財産による相続債務の弁済
処分行為に当たるか否かで問題となるのは,相続債務を,相続財産から支出して弁済した場合です。
相続債務を相続財産で支払うのですから,財産全体からみれば,財産は減るものの負債も減るので,プラスマイナスはゼロです。したがって,保存行為であるかのようにも思えます。
しかし,相続財産で支払うのですから,相続財産を処分していることは間違いありません。支払いをすることによって,債務を認めたことになり,消滅時効を援用できなくなるなどということも考えられます。
そのため,相続財産(遺産)による相続債務の弁済が処分行為に該当するのかは,一律に決められることではなく,相続財産の内容・金額や相続債務の内容・金額,その他の債権者の有無など事案によって異なるというべきでしょう。
いずれにしろ,相続放棄や限定承認をするかしないかを決める前に,あわてて相続債務を支払うのは避けておいた方が無難です。
相続開始の認識の有無
前記のとおり,相続財産の処分行為をすると,法定単純承認事由に該当することになりますが,処分行為をした時点で,その相続人に,相続が開始しているという認識がなかった場合でも,法定単純承認が成立するのかが問題となります。
民法921条1号には,「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」としか規定されておらず,相続人の認識の有無は問題とされていません。
しかし,法定単純承認は,その相続人が相続放棄・限定承認できなくさせてしまうという非常に強い効果を持っていますから,相続人に対する不意打ちを防止するためにも,相続人に相続開始の認識があったことを要すると考えるべきでしょう。
この点,前記最一小判昭和42年4月27日民集21巻3号741頁も,法定単純承認の規定が適用されるには「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか,または,少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」と判示しています。