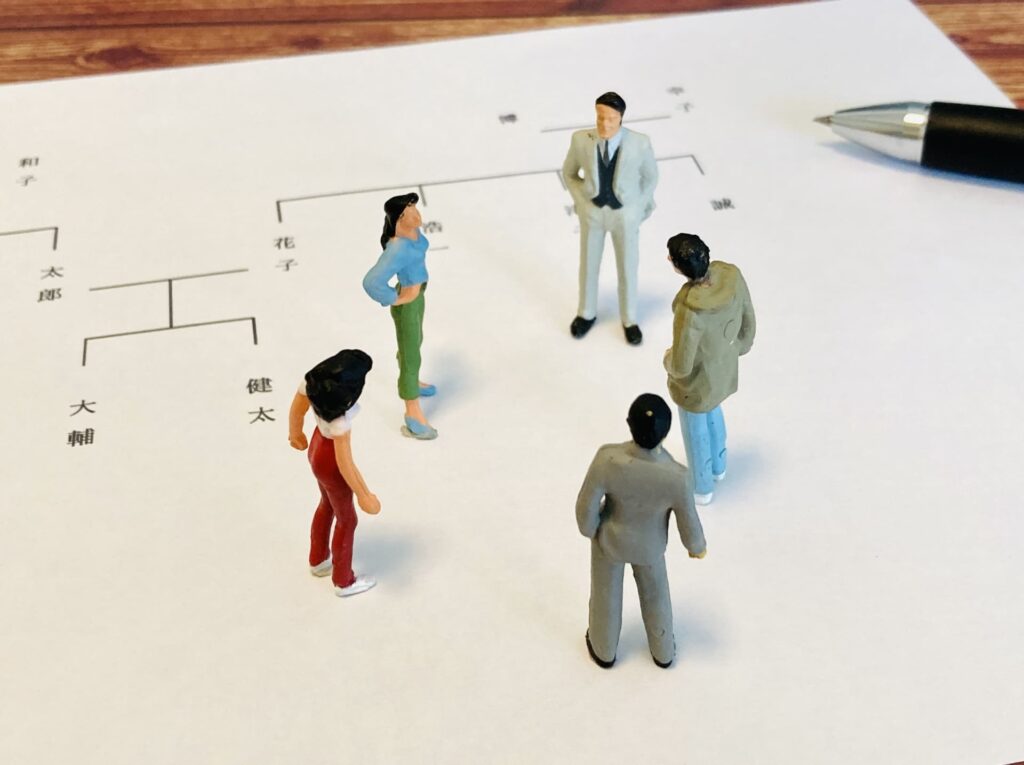
可分債権とは,分けることが可能な債権のことです。典型的なものは金銭債権です。この金銭その他の可分債権は,相続が開始されたとしても,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されることになります。
ただし,預貯金(払戻)債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されています(最大判平成28年12月19日)。
相続財産(遺産)の共有
民法 第898条
第1項 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第2項 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。
相続が開始されると,被相続人の一身に専属していたものを除いて,被相続人が有していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括承継されるのが原則です。
そして,相続人が複数いる場合には,その相続財産(遺産)は,遺産分割によって具体的な相続分が確定するまでの間,共同相続人の各自の相続分に応じて,共同相続人全員による「共有」となります(民法898条)。
可分債権とは
前記のとおり,相続開始後遺産分割による確定までの間,相続財産は共同相続人による共有となるのが原則です。
もっとも,相続財産のうちには共有とならないものもあります。その代表的なものが「可分債権」です。
債権とは,特定人に対して何らかの行為や給付を請求する権利のことをいいます。この債権には,可分債権と不可分債権という区別があります。
可分債権とは,文字どおり,分けることのできる債権です。他方,不可分債権とは,分けることができない債権です。
可分債権の典型的なものは,金銭債権です。たとえば,100万円の請求債権があったとした場合,50万円と50万円の請求権に分けることができます。したがって,金銭債権は可分債権です。
この金銭その他の可分債権については,遺産分割において,後述のとおり,他の財産とは異なる取り扱いがなされます。
可分債権の取扱いに関する各見解
金銭その他の可分債権を,相続においてどのように取扱うのかという点については,2つの考え方があり得るでしょう。
1つは,他の財産と同じように,相続によって,共同相続人全員でその可分債権を共有または合有する状態になるものとし,遺産分割によって具体的な金額を決めていくという考え方です。
「共有説」または「合有説」と呼ばれることがあります。
例えば,100万円の債権があれば,共同相続人全員でその100万円の債権を共有または合有しているという状態になり(したがって,各自単独で債権を自由に行使することはできません。),遺産分割をしてはじめて,個々がどのくらいの債権を有することになるかが確定されるということです。
もう1つは,可分債権については,他の財産と異なり,相続によって,遺産分割をしないでも,直接に,個々の共同相続人に対して,各自の相続分に応じた債権が相続されるという考え方です。
「分割債権説」と呼ばれることがあります。
たとえば,相続財産として100万円の相続財産があり,相続人としてそれぞれ2分の1ずつの法定相続分を持つAとBがいたという場合,相続によって,遺産分割を経ずに,AとBに50万円ずつの債権が相続されるということです。
可分債権に関する実務上の取扱い
民法 第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
前記のとおり,可分債権を相続においてどのように取扱うべきかということについては,共有とする見解・合有とする見解・分割債権とする見解があり得ます。
この点について,最高裁判所は,上記各見解のうちの分割債権説を採用することを明確にしています(最一小判昭和29年4月8日,最三小判昭和30年5月31日,最判平成16年4月20日等)。
したがって,実務上も,金銭その他の可分債権については,遺産分割を経ずに,相続開始によって当然に,各共同相続人にその相続分に応じて承継されるものとして扱われています。
ただし,金銭債権等の可分債権であっても,共同相続人間でそれを遺産分割対象財産に含めるという合意をすれば,遺産分割の対象となります。
預貯金払戻債権の取扱い
前記のとおり,金銭債権などの可分債権は,遺産分割を経ずに,相続開始によって当然に,各共同相続人にその相続分に応じて承継されるものとして扱われています。
ただし,例外があります。それは金融機関に対して預金・貯金の払い戻しを請求する債権(預貯金払戻請求権)です。簡単に言えば,金融機関から被相続人の預金・貯金を引き出すということです。
この預貯金については,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になると解されています(最大判平成28年12月19日)。
つまり,預貯金払戻請求権については,可分債権ではあるものの,遺産分割によって決するということです。
したがって,原則論で言えば,各共同相続人は,遺産分割をしなければ,各自の相続分に応じた預金・貯金の払い戻しをすることができないということになります。
ただし,民法改正(2019年7月1日から施行)により,遺産分割前であっても,各共同相続人は,預貯金払戻請求権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に各共同相続人の相続分を乗じた額(ただし,150万円が上限。)については,それぞれが単独でその払い戻しを請求できるものとされました(民法909条の2第1項)。
なお,2019年7月1日より前に開始した相続についても,上記改正後の民法909条の2第1項は適用されます。


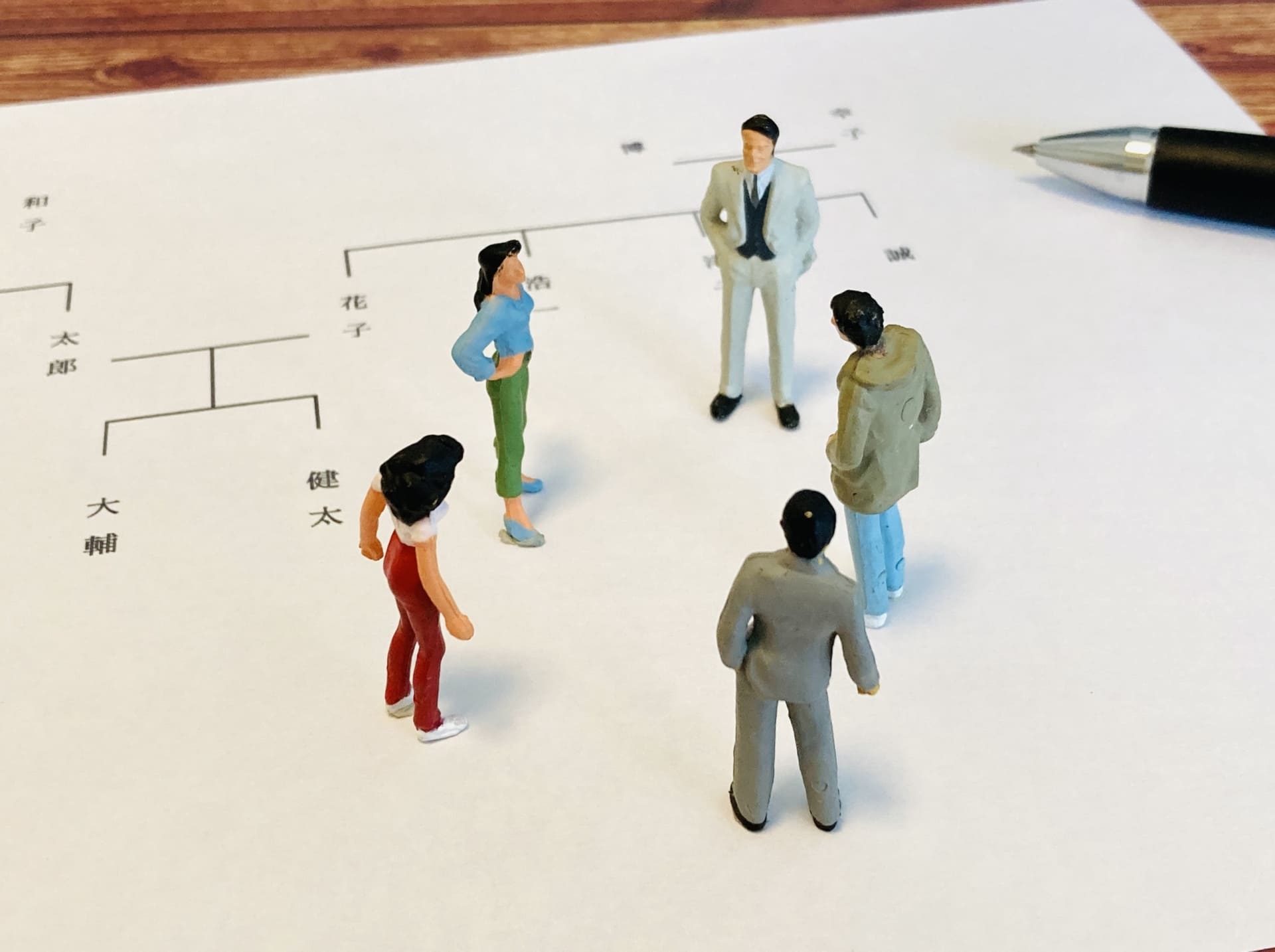




コメント