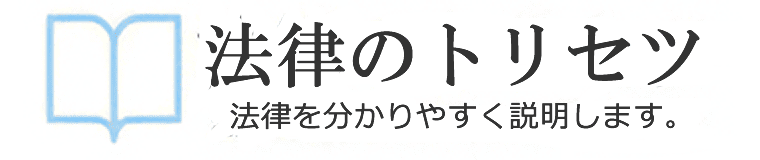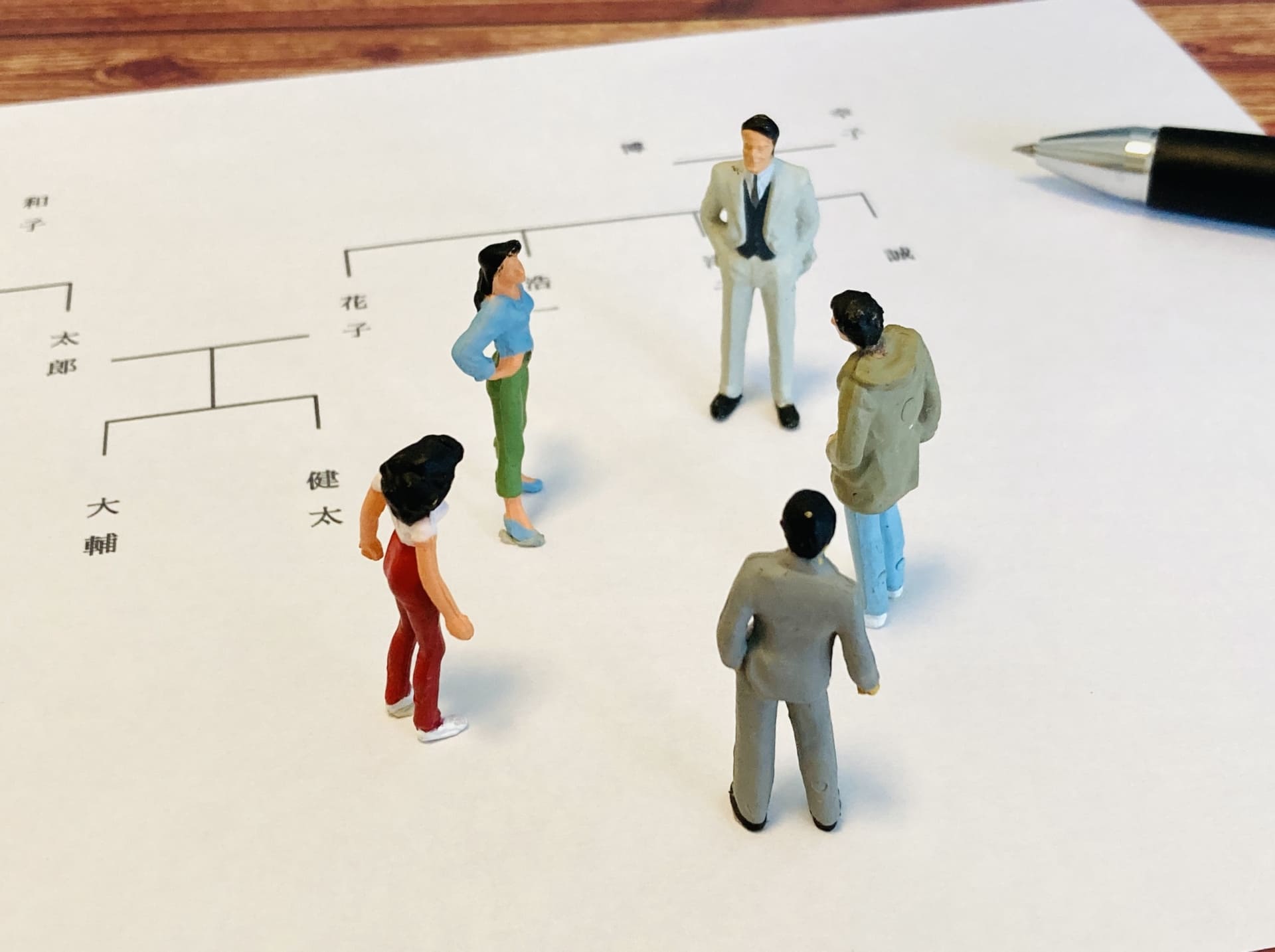この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
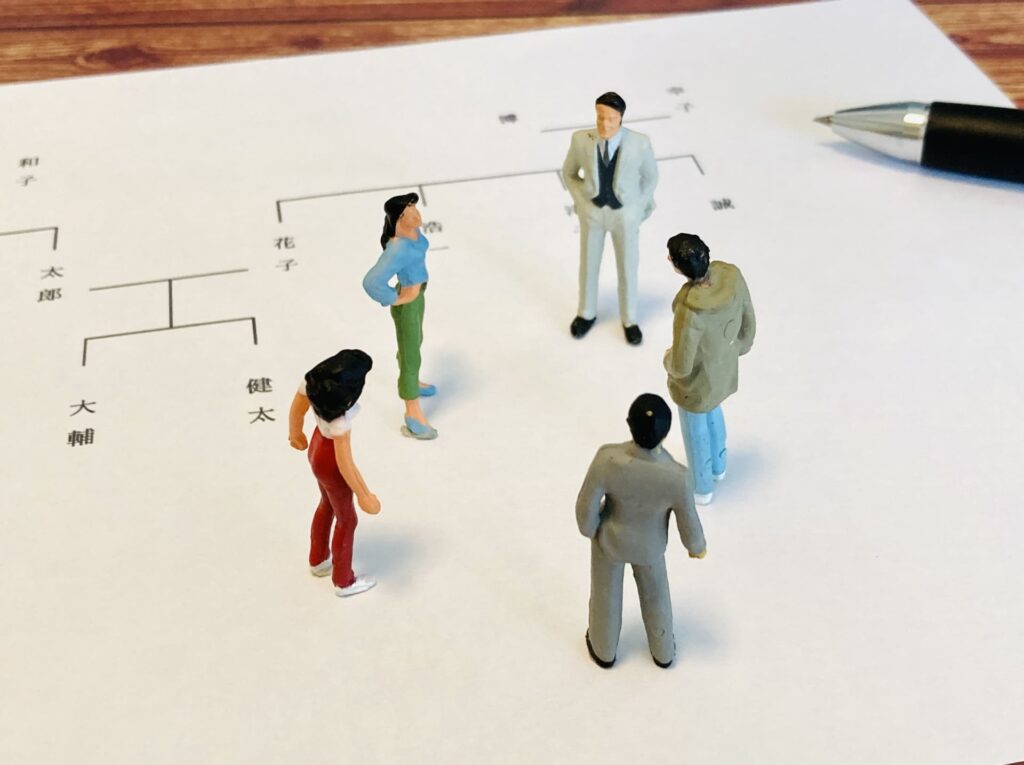
法定相続人となるべき人であっても,一定の事由がある場合には,相続人の資格を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。
法定相続人の資格を失う場合(相続欠格)
相続人となることができるのは,子・直系尊属または兄弟姉妹,それに配偶者です。これらの人は,優先順位は決まっているものの,法定相続人となる資格を取得できる立場にあります(民法887条、889条、890条)。
しかし,これらの人であっても,一定の事由がある人については相続人としての資格がはく奪される場合があります。これを「相続欠格」といいます(民法891条)。
相続欠格事由
民法 第891条
- 次に掲げる者は、相続人となることができない。
- 第1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 第2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 第3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 第4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 第5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
相続欠格が生ずるのは,以下の5つの事由がある場合です(民法891条各号)。
- 故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(第1号)
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。(第2号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者(第3号)
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者(第4号)
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(第5号)
1号と2号は被相続人に対する生命侵害等の行為が、3号から5号までは被相続人の遺言作成等に不当に干渉する行為が、それぞれ相続欠格事由とされています。
民法891条第1号の相続欠格事由
民法891条1号は「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者」は相続人の資格を失うことを規定しています。
故意に死亡するに至らせた場合とは,つまり,殺人罪に当たる行為=殺害行為をしたということです。過失致死等の過失犯は含まれません。また,故意行為に基づくものであっても結果的加重犯である傷害致死罪等も含まれないと解されています。
故意に死亡するに至らせようとした場合とは,殺人未遂罪に当たる行為をしたということです。
対象は,被相続人と先順位または同順位の相続人です。後順位の相続人や第三者に対して殺人または殺人未遂をしたとしても,相続資格に影響はありません。
注意すべきなのは,ただ被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害または殺人未遂行為をしたことによって刑に処せられていることが必要となるということです。
したがって,殺害行為等をしたとしても,捜査や刑事裁判中である場合など,いまだ殺人罪または殺人未遂罪で刑に処せられていない場合には,相続欠格とはなりません。
民法891条第2号の相続欠格事由
民法891条2号は「被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者」は相続人の資格を失うことを規定しています。
この規定は,いってみれば「かたき討ち」的な発想に基づくものです。被相続人が殺されたのにそれを告訴告発しない不届者には相続させる必要はない,というような発想でしょうか。
しかし,現在の法制度では,告訴告発の有無にかかわらず,殺人罪の起訴・不起訴の決定権限は,すべて検察官にあります。相続人が告訴告発しようとしまいと,検察官が起訴するかどうかを決めるということです。
したがって,ほとんど意味のない規定というべきであり,実際にも,この規定によって相続欠格となるという場合はほとんどないと思われます。
被相続人は事故死として扱われているが実は殺されていたということを知りながら,それを告訴告発しないままでいた,というようなごく例外的な場合には,あるいはこの規定の適用があるかもしれません。
ただし,被相続人の殺害について,すでに捜査機関による捜査がなされているときには,告訴・告発をしなくても欠格事由には当たらないと解されています。
なお,この規定は,告訴告発をしなかった推定相続人に是非弁別能力がなかった場合や,その被相続人を殺人した犯人が自分の配偶者や直系血族であった場合には適用されないとされています。
是非弁別能力とは,物事の是非を判断する能力という程度の意味です。例えば,心神喪失の状態にある人などがこれに当たりますが,このような人に告訴告発を強いることはできませんから,適用除外となっています。
また,自分の配偶者や直系血族(例えば,両親や子など)が殺人犯だとしても,かばいたいという気持ちが生まれてしまうのは人情的にやむを得ないことですから,こちらも適用除外となっているのです。
民法891条第3号の相続欠格事由
3号の場合は,被相続人を騙したりまたは強迫したりして、被相続人が遺言を作成・撤回・取消し・変更しようとするのを妨害した場合に相続資格を失うというものです。
民法891条第4号の相続欠格事由
また,3号と同じように,被相続人を騙しまたは脅迫して,相続に関する遺言をさせたり,または撤回・取消し・変更をさせたりした者も,4号により相続資格を失うことになります。
ただし,これらの不当干渉行為というには,これらの行為をするについて故意があるだけでなく,さらに,不当に利益を得ようとする目的もなければならないと考えられています。
民法891条第5号の相続欠格事由
5号は,被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者が相続資格を失うというものです。要するに偽の遺言書を作成したり,すでにある遺言書に勝手に変更を加えたり,または,遺言書を破棄したり隠したりした場合ということです。
これも,前記4号と同じく,不当な利益を得る目的がない場合には,相続欠格事由に該当しないものと解されています。
判例も,不当な利益を得る目的がない場合には,相続欠格事由に該当しないと判断しています(最二小判昭和56年4月3日、最三小判平成9年1月28日等)。
相続欠格の効果
相続欠格事由があった者については,相続資格が失われます。相続資格が失われるとは,つまり,相続人ではなくなるということです。
したがって,相続が開始した場合,その欠格者は相続人でないものとして,相続財産が他の相続人に分配されることになります。ただし,欠格者に子がいる場合には,その子が欠格者に代わって代襲相続することになります。
相続開始前に欠格事由が発覚した場合には,その発覚時から相続資格を失います。相続開始後に欠格事由が発覚した場合には,相続開始の時に遡って相続資格を失うことになります。
すでに,遺産分割がなされてしまっている場合には,他の相続人はその欠格者に対して相続回復請求をすることになります。
なお,相続欠格事由があっても,あらゆる相続資格を失うわけではありません。
特定の被相続人との関係で相続欠格事由がある場合には,その被相続人の相続に関してのみ相続資格を失うだけで,他の被相続人の相続資格が失われることはありません。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現