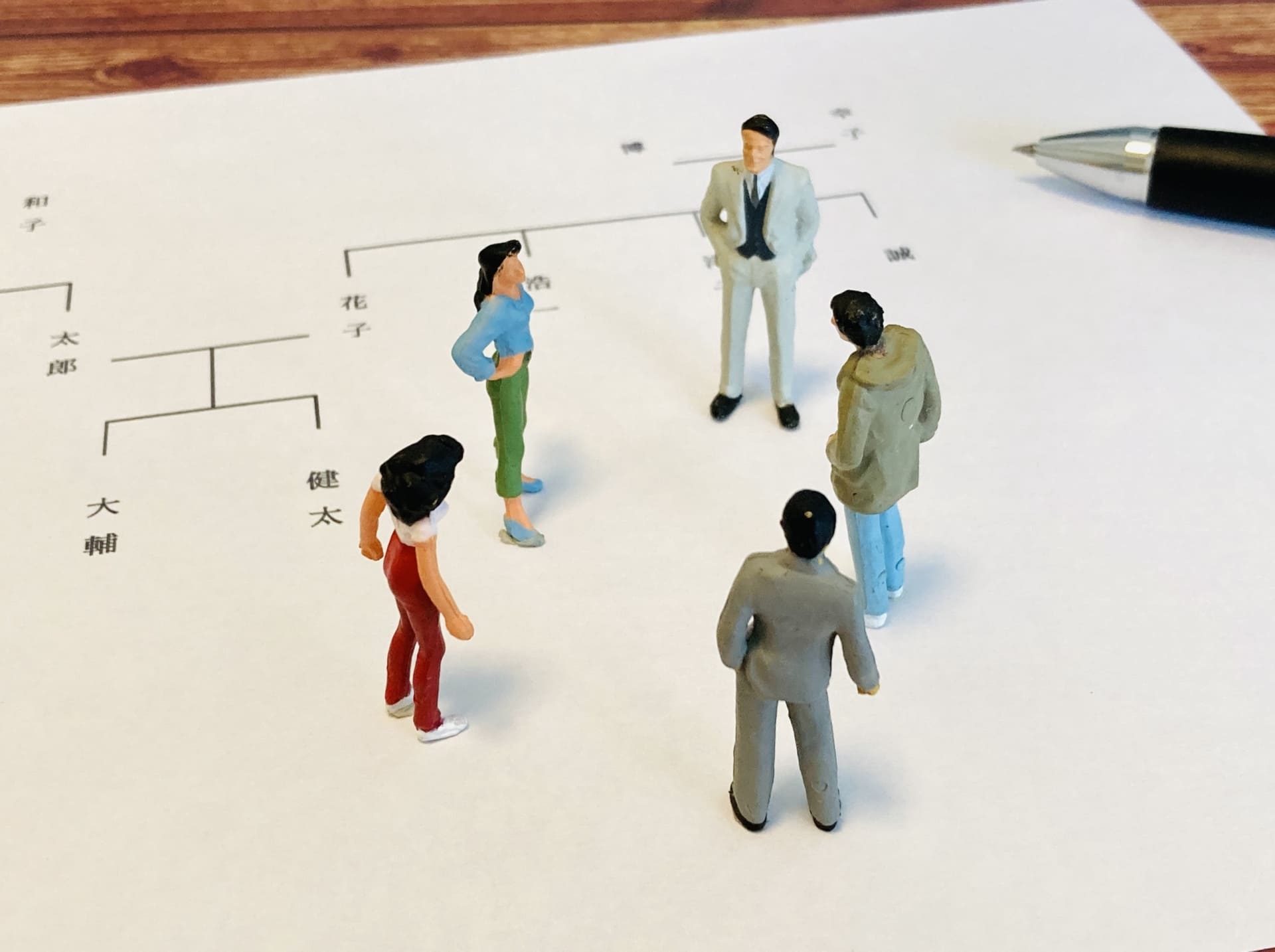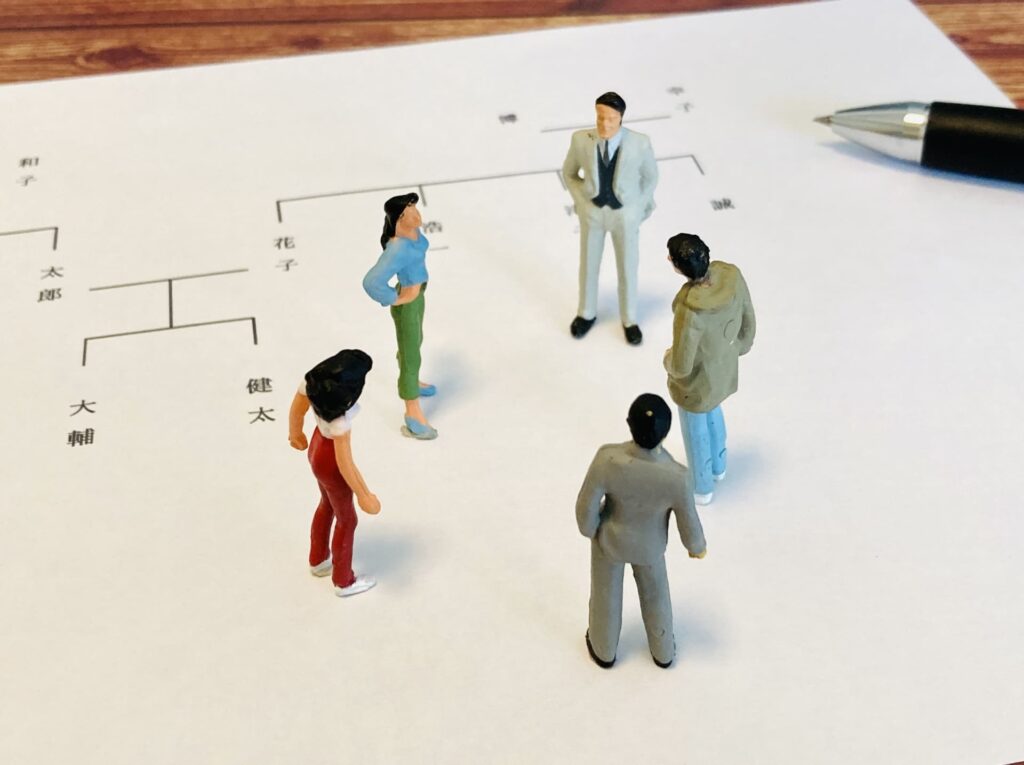
判例では、相続欠格となる遺言作成不当干渉行為の成立には「不当な利益を得る目的」が必要であると判断しています(最高裁判所第二小法廷昭和56年4月3日判決、最高裁判所第三小法廷平成9年1月28日)。
民法891条5号の相続欠格事由
民法 第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
第1号 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
第2号 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
第3号 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
第4号 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
第5号 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法891条3号から5号までは、被相続人の遺言に不当に干渉する行為は相続欠格事由となることを規定しています。
民法891条3号から5号までの条文には,遺言の作成、偽造や変造等の行為が規定されていますから,故意に基づく行為が対象となることは間違いありませんが,それ以上に,「不当な利益を得る目的」が必要となるかどうかについては規定がありません。
そこで,民法891条3号から5号の相続欠格事由に当たるというためには,故意のほかに,不当な利益を得る目的が必要となるのかどうかが問題となってきます。
この問題についての判断を示したのが,以下でご紹介する最高裁判所第二小法廷昭和56年4月3日判決(最二小判昭和56年4月3日)と最高裁判所第三小法廷平成9年1月28日判決(最三小判平成9年1月28日)です。
最二小判昭和56年4月3日の解説
最二小判昭和56年4月3日は,以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
民法891条3号ないし5号の趣旨とするところは遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにあることにかんがみると、相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は、同条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども、相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには、右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。
これを本件の場合についてみるに、原審の適法に確定した事実関係の趣旨とするところによれば、本件自筆遺言証書の遺言者であるD名下の印影及び各訂正箇所の訂正印、一葉目と二葉目との間の各契印は、いずれも同人の死亡当時には押されておらず、その後に被上告人Bがこれらの押印行為をして自筆遺言証書としての方式を整えたのであるが、本件遺言証書は遺言者であるDの自筆によるものであつて、同被上告人は右Dの意思を実現させるべく、その法形式を整えるため右の押印行為をしたものにすぎないというのであるから、同被上告人は同法891条5号所定の相続欠格者にあたらないものというべきである。
引用元:裁判所サイト
この判決の事案は,被相続人が遺言を作成していたましたが,遺言作成の方式に不備があったため,本来であれば遺言としての効力を生じないものでした。
そこで,その相続人が,相続開始後に,被相続人の意思を尊重して遺言を有効なものにしようとして,その無効な遺言の方式を具備するように訂正をしたという事案です。
上記判決は,民法891条3号から5号までの遺言作成等に対する不当干渉行為の趣旨を,「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対し相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするにあること」としています。
そして,上記ような趣旨からすれば,相続人による訂正は遺言書の偽造・変造には形式的に当たるけれども,相続欠格事由にはならないとしてます。
つまり,判決では明示はされてませんが,この事案では相続人が被相続人の意思を尊重しようとして偽造等をしたものであり,「不当な利益を得る目的」がないから,相続欠格とはならないとしたというように解釈できます。
したがって,判例も,民法891条5号については,故意のほかに「不当な利益を得る目的」が必要であるという立場をとっているものと考えられています。
なお,この判決では5号が問題となっているので,5号についてだけ判断されていますが,「民法891条3号ないし5号の趣旨とするところは」として3号・4号も含めて同じ趣旨であると解していることからして,3号・4号の場合についても,5号と同様に,故意のほかに不当な利益を得る目的が必要であると考えているものと思われます。
もっとも,この判決(多数意見)に対しては,遺言に厳格な方式を要求する法の趣旨に反するとして,宮崎裁判官による反対意見(相続欠格に当たるとする意見)もあります。
最三小判平成9年1月28日の解説
最三小判平成9年1月28日は,以下のとおり判示しています(一部抜粋)。
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条5号の趣旨は遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにあるが(最高裁昭和55年(オ)第596号同56年4月3日第二小法廷判決・民集35巻3号431頁参照)、遺言書の破棄又は隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人となる資格を失わせるという厳しい制裁を課することは、同条5号の趣旨に沿わないからである。
引用元:裁判所サイト
最三小判平成9年1月28日は,最二小判昭和56年4月3日を引用しつつ,民法891条5号の趣旨は「遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課そうとするところにある」としています。
最二小判昭和56年4月3日でははっきりとは判示されていませんでしたが,この最三小判平成9年1月28日は,不当な利益の目的が必要であるかどうかについて,「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において,相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは,右相続人は,民法891条5号所定の相続欠格者には当たらない」という結論を明示しています。
つまり,民法891条5号の相続欠格事由については,不当な利益を得る目的が必要となるということです。
なお,この判決では,3号や4号については触れられていませんが,多数説は同様に不当な利益の目的が必要であると解しています。