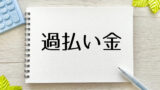個人再生の手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続がありますが,基本的な手続の流れは同じです。
個人再生の場合、裁判所への申立て前に,債権,資産,免責の調査を行った上で,個人再生の申立書(再生手続開始の申立書)を作成し,それを裁判所に提出する方式で個人再生の申立てをします。
申立て後、個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員が選任された場合は、その個人再生委員の監督のもとで手続を進めていくことになります。また、実際に返済可能化を確かめるための履行テストも、多く裁判所で行われています。
このページでは、東京地裁の個人再生を中心に、個人再生手続の流れについて説明します。なお、裁判所では、基本的に弁護士が代理人になることを想定しています。そのため、以下は、弁護士や司法書士に依頼することを想定した流れになっています。
個人再生の申立てまで
弁護士・司法書士との相談・依頼
個人再生は要件や手続に複雑な面があります。そこで,個人再生をお考えの場合,まずは,弁護士等に法律相談をすることをお勧めします。
現在では、個人再生を含めた債務整理の法律相談は、大半の法律事務所等で無料相談になっていますので、まずは相談をしてみて、良い弁護士等が見つかれば依頼をします。
なお、相談や依頼については、事務所によって手続が異なります。
通常は、貸金業者などの債権者,その業者との取引の期間,現在の債務の残高,資産・財産の状況,借入れの原因,家計の状況などを話し,個人再生が可能かどうかを相談することになるでしょう。
▼
受任通知の送付・取引履歴の開示請求
個人再生を行うことになった場合、まずは、弁護士等が、各債権者に対して受任通知(介入通知)を送付します。また、返済は、個人再生が終わるまで停止します。
返済を停止しても、受任通知の送付によって債権者からの直接の取立ては停止されるため、直接取立てを受けることはありません。
通常,受任通知は,委任契約締結の日に送付されます。
また,受任通知の送付と同時に,債権の金額や内容などを届け出てもらうよう請求し,貸金業者に対しては,取引履歴の開示も請求します。
なお,住宅資金特別条項を利用する予定の場合には,住宅ローン債権者にも受任通知を送付しますが,他の貸金業者等への場合と異なり、住宅ローンの支払いは停止しないこと,住宅資金特別条項を利用する予定であることを併せて連絡します。
▼
債権調査・過払い金返還請求
債権者に対して債権の届出を依頼すると,債権者から概ね1~2か月以内に届出がされるのが通常です。そして,債権者から提出された債権届をもとに債権額やその内容を調査します。
貸金業者から取引履歴が開示された場合には,引き直し計算をして利息制限法に従った債権額を確定し,場合によっては,過払金の返還を請求します。
交渉による過払い金の返還が難しい場合には,訴訟を提起し,過払金を回収することになる場合があります。
▼
収支・家計全体の調査
個人再生においては,反復・継続した収入があり,その収入は,再生計画に基づく弁済を行っていけるだけの額でなければなりません。そこで,債権調査と並行して,収入や支出,家計状況を調査します。
これらの調査のために,収入証明(給与明細・源泉徴収票・確定申告書・課税証明書等)や毎月の家計簿などを集めておく必要があります。
▼
財産・資産の調査
個人再生においては,清算価値保障原則があります。したがって,どれだけの資産があるのかは,計画弁済総額に影響してきます。そこで,債権調査・収入等の調査と並行して,財産・資産状況も調査をします。
これらの調査のために,通帳・保険証券・車検証・不動産登記簿謄本・財産の査定書など資産に関する書類や資料を集めておく必要があります。
▼
個人再生の手続の選択
個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類の手続があります。また,住宅ローンの残る自宅を維持したいという場合には,住宅資金特別条項という制度の利用を検討しなければなりません。
前記の債権調査,資産調査,家計状況の調査などの結果に基づき,最終的にどの手続を選択するのか,住宅資金特別条項を利用できるのかということを決定します。
▼
住宅ローン債権者との事前協議
個人再生手続の選択をし,住宅資金特別条項を利用することになった場合には,住宅ローン債権者と事前協議を行います。
通常の場合は,住宅ローンの支払を継続しているため,協議と言っても,何か特別なことをするわけではありません。念のため,個人再生に反対でないか,今後も協力してもらえるか等を確認する程度です。
もっとも,すでに住宅ローンを滞納している場合,保証会社に代位弁済されており巻戻しが必要な場合,競売が開始されている場合などには,返済計画作成依頼などの具体的な協議をしておく必要があります。
▼
個人再生の申立書の作成
個人再生申立てを行うためには,まず第一に,個人再生の申立書を作成しなければなりません。
個人再生を利用する場合には,申立ての際(または開始決定までに)小規模個人再生または給与職者等再生の手続を行うことを求める旨の申述をする必要があります。
具体的には,その旨を申立書に記載しておくことになります。
また,個人再生の申立書には,債権者一覧表,家計簿などの収支に関する資料,財産目録などの資産に関する資料,住宅資金特別条項を利用する場合には住宅や住宅ローンに関する資料を添付する必要があります。債権者一覧表は,債権者数分の副本も添付しなければなりません。
この申立書などの作成は弁護士等が行いますが,添付書類は依頼した人が自ら集めるのが通常でしょう。
▼
個人再生の申立て
個人再生の申立て
管轄の地方裁判所に個人再生の申立書を提出して,個人再生の申立てを行います。
申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります。
▼
個人再生申立ての審査
個人再生委員が選任されない場合
個人再生委員が選任されない場合、申立書を受理した後、裁判所が自らすべてその申立書が要件を満たしているかどうかを審査します。通常は書面審査です。
審査にあたって、不備や不足書類があれば、修正・提出を求められます。
また,その他,個人再生手続開始決定をしてよいかどうかを判断するために必要となる事項の報告などが求められます。
個人再生委員が選任された場合
個人再生事件では、本人申立ての場合や事件内容によっては個人再生委員が選任されることがあります。
東京地裁(本庁・立川支部)では、全件について個人再生委員が選任される運用となっています。
個人再生の申立書が受理され,裁判所による申立書の審査が完了すると,裁判所によって個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任されると,裁判所から誰を個人再生委員に選任したのかについて連絡がきます。
そして,その個人再生委員に申立書の副本を送付するとともに,連絡をとり,個人再生委員・再生債務者本人・再生債務者代理人弁護士等による三者打ち合わせの日程を調整します。
東京地裁本庁の場合,三者打ち合わせは,申立て(または個人再生委員選任決定)から1週間以内の日に打ち合わせをするのが原則とされています。
▼
個人再生委員との打ち合わせ
あらかじめ調整しておいた日程(通常は,申立てから1~2週間程度後)に,個人再生委員と打ち合わせを行います。
申立てをした裁判所の管轄地域に所在する法律事務所所属の弁護士が個人再生委員に選任されることになっています。その個人再生委員の所属する法律事務所に赴いて打ち合わせをするのが通常です。
打ち合わせにおいては,申立書の記載に沿って,債務,資産,家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば,提出を求められます。
また,その他,個人再生手続開始決定をしてよいかどうかを判断するために必要となる事項の聴取などが行われます。
▼
履行テストの開始
個人再生委員が選任されていない場合の履行テスト
個人再生の手続では、再生計画が認可された後に弁済をしていけるかどうかを判断するため、認可までの間、裁判所の指定する方式で、1月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を準備する「履行テスト」が行われるのが一般的です。
裁判所の指定する方式とは、例えば、新たに預金口座を開設し、そこに弁済予定額を毎月振り込んで、その通帳の写しを裁判所に提出する方法や、代理人の口座に振り込んで、代理人がその内容を裁判所に報告する方法などがあります。
履行テストの期間は裁判所ごとに違います。おおむね4か月から6か月ほどでしょう。
個人再生委員が選任されている場合の履行テスト
個人再生委員が選任されている場合、履行テストは、個人再生委員が監督します。
この場合は、個人再生委員が指定した銀行預金口座に1月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を振り込むことになります。
東京地裁の場合は、申立て後1週間以内に振り込むスケジュールとなっていますので,個人再生委員との打ち合わせ前に振り込みをするという場合もあります。
第2回目以降は,個人再生委員の指示に従い,1か月ごとに振り込むことになります。
▼
個人再生手続の開始から再生計画認可または不認可の決定まで
個人再生手続開始決定
裁判所が、申立書の審査や履行テストの開始状況などから、再生手続開始が相当であると判断した場合には、個人再生の手続開始決定がされます。
個人再生委員が選任されている場合には、個人再生委員が、申立書、三者打ち合わせの内容、履行テストの開始状況などから、手続を開始すべきかどうかの意見書を裁判所に提出し、その意見書をもとに、裁判所が判断をして、個人再生の手続開始決定がされます。
▼
債権届出・債権調査
個人再生手続が開始されると,各債権者に対して裁判所から開始決定書等が送付されるとともに,裁判所が指定した期間内に債権を届け出るよう通知がなされます。
これを受けて,債権者は,開始決定から約6週間後くらいに指定される債権届出期限までの間に,裁判所に対して債権の届出をします。
その後,裁判所から再生債務者(または代理人弁護士等)のもとに,提出された債権届出書が送られてきます。
個人再生においては,この債権届出書の管理は,再生債務者が自ら行わなければなりません(弁護士等が代理人となっている場合は代理人が行うのが通常です。)。
▼
債権認否一覧表・報告書の提出
再生手続開始決定の際に、債権認否一覧表・民事再生法125条1項の報告書の提出期限が定められます。その日までに,債権認否一覧表・民事再生法125条1項の報告書の書類を裁判所に提出します。
債権認否一覧表は,債権者から送付されてきた債権届出に記載されている金額をもとに,その再生債権の金額を認めるか認めないかの認否を記載します。
民事再生法125条1項の報告書には,財産状況等について,申立て時点から変更があったかどうかなどを記載します。
なお,債権認否一覧表等は、再生債務者が作成しなければなりませんが、代理人弁護士等がいる場合には、代理人が行うのが通常でしょう。
▼
異議の申述・評価申立て
再生債権の金額について異議がある場合には,一般異議申述期間と呼ばれる期間内に書面で異議を述べることができます。
また,異議を述べられた再生債権の再生債権者は,裁判所に評価申立てをすることができます。
▼
再生計画案の作成
再生債権額が明らかとなったところで,再生債務者は,再生計画案を作成する必要があります。
再生計画案には,弁済総額,弁済の方法,住宅資金特別条項の利用などについて定めることになります。この再生計画案とともに再生計画に基づく返済計画表も作成するのが、一般的です
なお、再生計画案・返済計画表の作成は、代理人弁護士等がいれば、代理人が行うのが通常です。
▼
再生計画案の提出
再生計画案を作成した、再生計画に基づく返済計画表とともに、これを指定された提出期限までに裁判所に提出します。個人再生委員が選任されている場合には、個人再生委員にも提出します。
提出期限までに再生計画案を提出できなかった場合,理由を問わず,再生手続が廃止(打ち切り)されてしまうので注意が必要です。
▼
再生計画案の書面決議等
再生計画案が提出され、裁判所によって、再生債権者の書面決議(給与所得者等再生の場合は意見聴取)に付するかどうか等についての決定がなされます。
個人再生委員が選任されている場合は、個人再生委員が、裁判所に対して、書面決議(または意見聴取)に付するかどうか等に関する意見書が提出し、それに基づいて、裁判所が書面決議(または意見聴取)に付するかどうか等についての決定をします。
書面決議に付する旨の決定または意見聴取に付する旨の決定がなされると,その旨が各債権者に通知されます。
各再生債権者は、指定された期限までに、回答書または意見書を裁判所に提出する方法で再生計画案に対する同意・不同意等の意見を裁判所に提出します。
小規模個人再生の場合,一定数以上の不同意意見が提出されると,再生手続は廃止になってしまいます。
▼
裁判所による再生計画認可・不認可の決定
前記の書面決議や意見聴取の結果、履行テストの状況などをふまえて、裁判所が、再生計画の認可または不認可の決定をします。
個人再生委員が選任されている場合には、個人再生委員が,書面決議や意見聴取の結果や履行テストの状況などをふまえて、再生計画を認可するか不認可とするかについての意見書を裁判所に提出し、これに基づいて、裁判所が再生計画の認可または不認可の決定をします。
裁判所による認可決定書または不認可決定書は、再生債務者(代理人がいる場合は代理人)および再生債権者に送達されます。
▼
再生計画認可・不認可決定の確定
再生計画について認可決定(または不認可決定)がされると,決定日から約2週間後に,その旨が官報公告されます。
その官報公告からさらに2週間が経過すると,その認可決定(または不認可決定)は確定することになります。
▼
再生計画認可決定の確定後
個人再生手続の終了・再生計画に基づく弁済の開始
再生計画認可決定が確定した後,その再生計画に基づく弁済が開始されます。弁済の開始時期は,再生計画において定めることができます。
再生計画において毎月払いを選択していた場合は,再生計画認可決定が確定した日の属する月の翌月から弁済を開始することになります。
3か月に1回払いを選択していた場合は,再生計画認可決定が確定した日の属する月の3か月後から弁済を開始することになります。
弁済の方法は,再生債権者の指定した銀行預金口座に振り込む方法によって支払うのが一般的です。そのため,認可決定後,各債権者に振込口座を聞いておく必要があります。
なお、個人再生委員が選任されていた場合、履行テストのために個人再生委員に振り込んでいた予納金については、個人再生委員の報酬(東京地裁では15万円)を差し引いて返還されることになります。
▼
再生計画の遂行
再生計画に基づく弁済をすべて完了すれば,それ以外の債務をもはや支払う必要はありません。
なお,仮に返済計画の途中で支払ができなくなってしまうと,再生計画が取り消されてしまう場合がありますので注意が必要です。