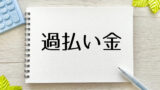任意整理においては,まず,弁護士から各債権者に対して受任通知を発送して取立てを停止させ,あわせて取引履歴の開示を求めます。開示された取引履歴に基づいて引き直し計算を行い,正確な債務額を確定させます。過払金が発生している場合にはその返還を請求します。
その上で,各債権者と交渉して返済条件を決め,和解書(合意書)を取り交わします。その後,和解の内容に従って,返済をしていくことになります。
債務整理共通の手続(債権調査)
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生、過払金返還請求などさまざまな方法があります。これらの手続は、共通する手続として、まず始めに債権の調査を行います。
なお、以下の説明は、弁護士や司法書士に任意整理を依頼する場合の流れを想定しています。
弁護士や司法書士との相談・依頼
任意整理をするためには、法律の専門家に相談・依頼することが必要となってきます。
現在では,ほとんどの法律事務所等で任意整理を含めた債務整理や過払い金に関する無料相談を行っていますので、まずは相談をしてみて、良い弁護士・司法書士が見つかれば依頼をします。
なお、相談や依頼については、事務所によって手続が異なります。
▼
受任通知の送付・支払いおよび取立ての停止
任意整理を行うことになった場合、弁護士等が、まずは各債権者に対して受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を送付します。つまり,弁護士等が債務整理手続の代理人を受任したということの通知です。
もっとも,それだけではなく,今後は話し合いがつくまで支払いを停止することを伝え、さらに、債務者に対して直接取立て行為をするのを停止するように求めます。
貸金業者や債権回収会社などの場合には,受任通知を受領したら直接の取立てを停止しなければならないことが,貸金業法等の法律によって規定されています。
通常,この受任通知は,委任契約締結の日に送付します。また,受任通知の送付と同時に,取引履歴の開示も請求します。
▼
引き直し計算
貸金業者から取引履歴の開示を受けた後,それをもとにして引き直し計算をし,正確な借金の総額を確認します。場合によっては,過払いとなっていることもあるでしょう。
取引履歴の開示までの時間は,貸金業者によって異なります。遅いところだと2か月近くかかる場合もあります。
なお,開示がなされなかった場合には,再度開示を請求するか,または,その他の資料に基づいて推定計算を行うことになります。
▼
過払い金の返還請求
引き直し計算によって,過払金が発生していることが判明した場合,当該債権者に対して過払い金の返還請求をすることになります。
まずは交渉によって過払金の返還を請求しますが,話がつかない場合には,訴訟を提起して回収することもあるでしょう。
回収した過払い金は,弁護士等の費用等を差し引いて,他の各債権者に対する弁済に使われることになります(なお、この点は依頼した弁護士等によって異なるので、確認が必要です。)。
▼
任意整理固有の手続
弁済原資金の積立ての開始
任意整理の受任通知を送付したことによって,債権者からの直接の取立ては停止しますが,だからといって返済がなくなったわけではありません。
そのため、将来の弁済に備え、一定の金額を毎月弁護士等に送金することにより、弁済原資金を積み立てておくという場合が多いでしょう。
積み立てられた弁済原資金は,弁護士等の費用等を差し引いて,各債権者に対する弁済金に使われることになります。
▼
和解案の作成・送付
前記までの手続で,ある程度の弁済原資金が積み立てられ,また過払い金の回収が済んだ段階で(それ以前に行う場合もあります。),任意整理における返済条件を定める和解案を作成します。
通常は36回以上の分割払い,利息のカットなどを定めることになります。作成した和解案は,各債権者に送付します。
▼
和解交渉
作成・送付した和解案をもとに,各債権者と交渉します。
分割払いの回数や利息のカットにどこまで応じてくれるかは,相手方がどこの貸金業者等なのかによって異なります。
▼
特定調停
あまりに交渉が上手くいかない場合には,裁判所の特定調停手続を利用するという方法もあります。
特定調停も話し合いが基本ですが,ある程度の和解案を示せば,裁判所がその和解案に沿った決定を裁判所が出してくれることがあります。
▼
和解契約の締結
債権者との間で話がついた場合は,その債権者との間で和解契約を締結します。
和解契約は口頭でも成立する諾成契約ですが,後に言った言わないの紛争になってしまうおそれがあるので,和解書(合意書)を取り交わしておくことになります。
和解書を取り交わしておくことによって,任意整理に決定的な法的効力を持たせることができることになります。
要するに,約束に違反した場合は,約束を守るように請求したり,または契約違反の責任(債務不履行責任)を問うことができるようになるということです。
債権者が任意整理の約束を破って一括での支払いを求めてきたとすると,債務者は,上記の和解契約を盾にしてこれを拒否できます。つまり,分割でなければ払わないと言えるようになるのです。
他方,債務者が任意整理の約束を破って分割払いをしなければ,債権者は,契約違反を主張して裁判を起こしたり,その裁判の判決を使って強制執行したりすることができるということになります。
▼
和解に基づく返済
和解契約が成立したならば,その後は,その和解契約の内容に基づいて返済をしていくことになります。
なお,通常の場合は,まず弁護士等の費用等を完全に支払い終わってから債権者への支払いが始まることになります。
支払先は債権者が指定してくるので、その指定された銀行口座に振り込む形で返済をしていくことになるのが通常です。
支払方法については、債務者が自分で支払っていく方法と弁護士等が代理して支払っていく方法とがあります。これも事務所によって異なるので、確認が必要です。