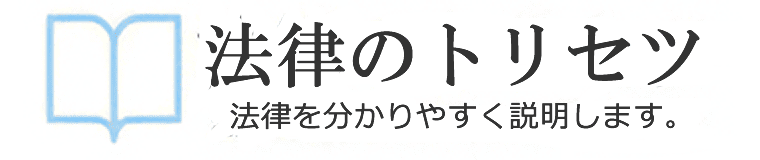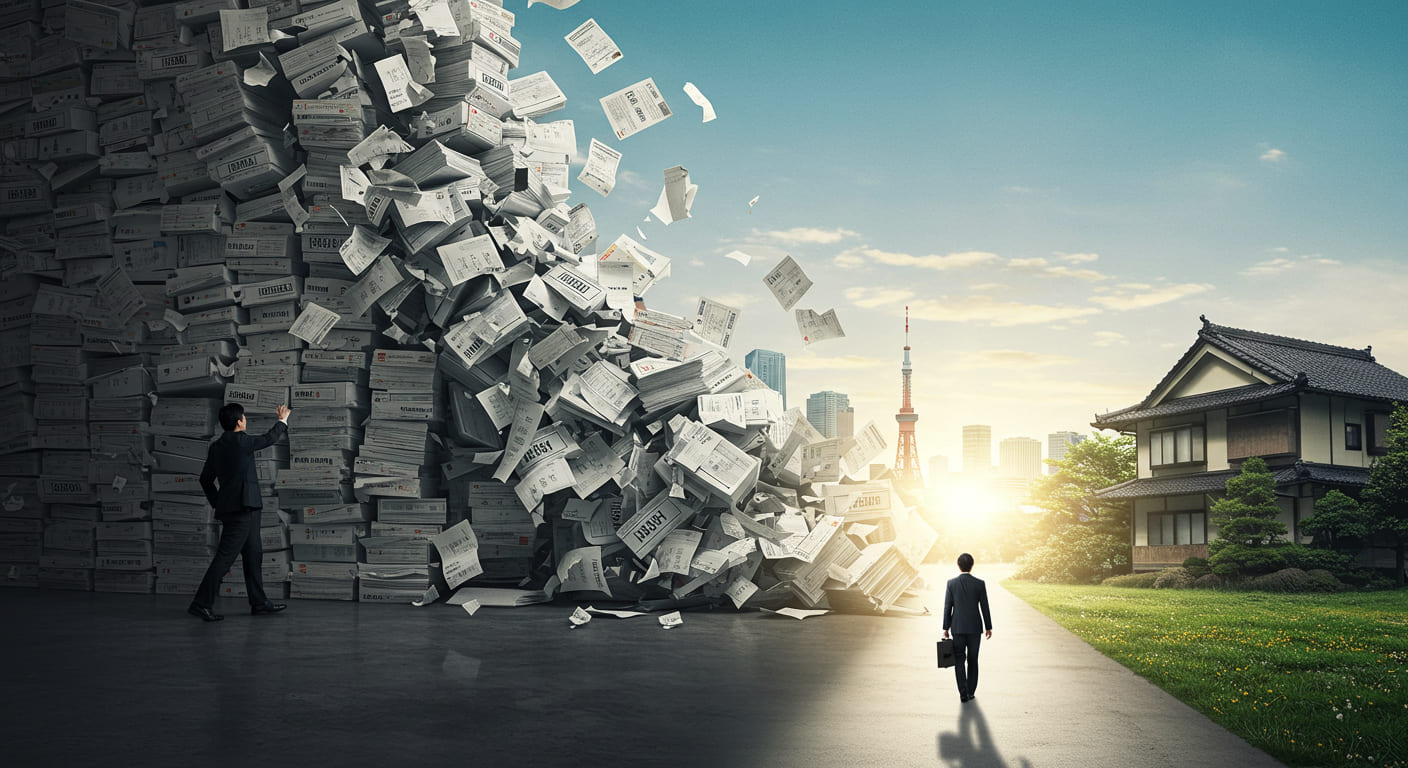この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
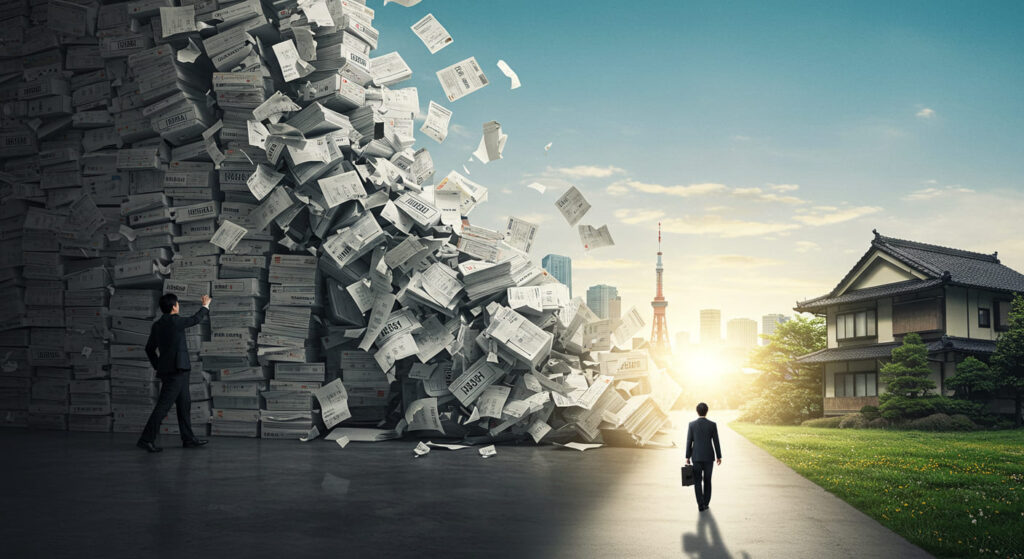
過払金(過払い金)とは,利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息を支払い続け,その制限超過利息を借入金元本に充当した結果,計算上,借入金元本が完済となった後に,さらに支払った金銭のことをいいます。
過払金が発生した場合,借主は,貸金業者等に対し,不当利得返還請求権に基づいて,過払金の返還を請求することができます。
過払金(過払い金)とは
「過払金(過払い金・かばらいきん)」という言葉は,どこかで聞いたことがあるという方もいるかもしれません。
テレビやラジオで流れている法律事務所等のCMなどで聞いたことがあるという人もいるかと思います。それだけ世間一般認知されてきた用語であるということでしょう。
利息制限法の制限利率を超える利率の利息を支払い続けていた場合,貸金業者等に対して金銭を支払いすぎている状態になることがあります。
そして,この支払いすぎになっている金銭は,貸金業者等から返してもらえる場合があります。この貸金業者等から返してもらえる払い過ぎた金銭のことを「過払金(過払い金)」と呼んでいるのです。
過払金が発生する仕組み
前記のとおり,利息制限法所定の制限利率を超える利率の利息(制限超過利息)の受領は無効です。
この無効な制限超過利息は,まず,借入金の元本に充当されます(最大判昭和39年11月18日。ただし,利息制限法内の借入金利息や遅延損害金などが発生していればそちらから先に充当されます。)。
借入金元本に充当されるというのは,要するに,制限超過利息で借金の元本を返済したものとして扱われるということです。
制限超過利率の下で返済を続けていくと,返済をする度に,つぎつぎと制限超過利息が借入金元本に充当され,借金の元本も減っていきます。
そして,さらに返済を続けていくと,最終的に元本全額に充当される場合があります。要するに,借金がなくなるというわけです。
ところが,制限超過部分の元本充当により借金がなくなった後も,そのことを知らずに(むしろ,知らないのが通常だと思いますが)さらに返済を続けていってしまう場合があります。
すでに借金はないのですから,返済はもう必要なくなっているのに返済を続けていることになります。つまり,払い過ぎているわけです。
この制限超過部分の元本充当により借金がなくなった後も,返済を支払い続けたことにより払い過ぎてしまった金銭が「過払金」なのです。
借金が無い以上,貸金業者等は,その過払い金を受領する正当な理由もないのに,不当にその過払金を受領していることになります。
そこで,払い過ぎた借主は,貸金業者等に対して,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき,過払金の返還を請求できるのです。
過払金返還請求が認められるようになった経緯
今では当たり前に過払い金返還を請求できるようになりましたが,かつては,過払金返還請求は認められていませんでした。それどころか,制限超過利息を借金の元本に充当することも認められていませんでした。
制限超過利息を借金の元本に充当することを最初に認めた最高裁判所の判例は,最高裁判所大法廷昭和39年11月18日判決です。
さらに,最高裁判所第三小法廷昭和43年10月29日では,制限超過利息の充当指定特約も無効とされました。
もっとも,これらの判例では,過払金返還請求できることまでは認めていませんでした。過払金返還請求が最高裁判所によって認められたのは,最高裁判所大法廷昭和43年11月13日判決です。
この昭和43年11月13日の大法廷判決によって過払金返還請求が認められるようになったのです。ただし,過払金返還請求が認められたと言っても,今ほど容易に請求ができたわけではありません。
昭和43年11月13日の大法廷判決後も,過払金返還請求については次々と争点が生じ,非常に多くの最高裁判例が出されています。それらの積み重ねによって,現在のように過払金返還請求が認められやすくなっていったのです。
過払金として返還される範囲
前記のとおり,制限超過利息は,まず,借金の元本に充当されます。この元本充当により借金が完済になった後に支払いをした金銭が,過払金として返還を請求できる部分です。
したがって,支払ったすべての制限超過利息を返してもらえるというわけではありません。その点は注意しておく必要があるでしょう。
ただし、過払金として返還できるほどに払い過ぎがなかった場合でも、制限超過部分は元本に充当されるので、借金の額は減額されます。
過払金が発生する取引期間の長さ
どのくらいの期間,貸金業者との間で取引を継続していれば,この過払い金が発生するのかというのは,一概にはいえません。
それこそ,取引の内容,借入金額,返済金額,回数,支払い方によって異なってくるからです。
利息制限法を超える利息で,ずっと継続的に借入れや返済を繰り返していたという場合,一般的には,5年~10年以上の期間,取引を継続していた場合には,過払い金が発生している可能性が高いといえるでしょう。
ただし,現在では貸金業法等の改正によって,平成20年頃から,ほとんどの貸金業者が利息制限法所定の制限利率内でしか取引をしなくなりました。
したがって,過払金が発生しているのは,平成20~22年頃よりも以前から取引をしていた場合に限られてくるでしょう。平成22年以降に取引を始めた場合、過払金が発生している可能性は低いでしょう。
過払金返還請求の期限
過払い金の返還請求は,すでに完済して取引を終了した後でもすることができます。実際,完済後に過払金返還請求する人も少なくありません。
もっとも,過払金返還請求権も債権ですから,時効によって消滅してしまう場合があります。過払金返還請求権の消滅時効期間は、以下のとおりです。
- 令和2年(2020年)4月1日以降に完済した場合:「取引終了時から10年間」または「過払金返還請求できることを知った時から5年間」のいずれか時期の早い方(民法166条1項)
- 令和2年(2020年)3月31日以前に完済した場合:取引終了時から10年間
上記のとおり、いつ借金を完済したか、いつ取引を終了したかによって、消滅時効期間は異なってきます。もっとも、最長でも完済から10年間が限度です。したがって,過払金返還請求をお考えの場合には、早めに行動を起こす必要があるでしょう。
過払金返還請求における争点
過払金返還請求には,前記の消滅時効のほかにも,非常に多くの争点があります。そのうちのいくつかは,最高裁判所の判例や法改正により決着がついたものもありますが,現在でも,過払金返還請求において争われているものは少なくありません。
例えば,以下のような争点があります。
- 過払金の利息(悪意の受益者性)
- 過払金返還請求権の消滅時効
- 取引の個数・一連充当計算
- 過払金返還債務の承継
- 推定計算・残高ゼロ計算
- 貸付停止措置がある場合の充当計算
- 和解・特定調停後の過払金返還請求
- 相続人による過払金返還請求
過払金返還請求をする場合には,これらの争点についてもあらかじめ検討しておく必要があります。また、その争点ごとに重要は最高裁判例があります。それらの判例も知っておいた方がよいでしょう。
過払金返還請求のメリットとデメリット
過払金返還請求をすれば,その取引の借金はなくなり,過払金として一定の金銭が返ってきますから,メリットがあることは言うまでもないでしょう。
実際に回収できた過払い金を他の借金等の返済に充てたり,あるいは,それまでの返済によって苦しくなっていた生活を立て直すことも可能です。債務整理としてのメリットもあります。
また,過払金返還請求をしたことによって,信用情報に事故情報(ブラックリスト)として登録されることもありません。
したがって,過払金返還請求をすることには,ほとんどデメリットは無いと言ってもよいくらいです。
強いて挙げるならば,過払金返還請求の相手方である貸金業者から新たに借入れをしたり,その業者のクレジットカードを使うことができなくなる可能性があるということでしょう(なお,この場合,他の貸金業者には影響ありません。)。
なお,先に過払い金だけ回収した後,自己破産や個人再生を申し立てた場合,その自己破産や個人再生の手続において否認権や財産の不利益処分などの問題が生じる可能性があることには注意が必要でしょう。
過払金返還を請求できる場合
前記のとおり,過払金は,利息制限法の制限を超える利率の利息を支払い続けていた場合に発生します。
平成22年の貸金業法改正によって,大半の貸金業者が利息制限法に違反する利率での取引をしなくなったため,利息制限法の制限利率を超える取引をしていたのは,平成22年より前となるでしょう。
また,消滅時効が完成していると,過払金返還請求は原則としてできません。
そうすると、過払金返還請求ができるのは、以下のような状況にある場合になってきます。
- 借金の利率が、利息制限法の制限利率(15~20パーセント)を超えていた
- 5年以上、継続的に、借入れと返済を繰り返していた(ただし、必ずしも5年とは限りません。あくまで概ねの目安です。)
- 平成22年より前に取引をしていた
- 取引が終了してから10年を経過していない(令和2年4月1日以降に完済した場合には、過払金返還請求できることを知ってから5年を経過していない場合と比較して、いずれか早い方の期間を経過していない)
条件にあてはまる場合には、過払金返還請求できる可能性があるでしょう。
ただし、数年前は、裁判所の訴訟期日の大半が過払金返還請求訴訟になっていたくらい、過払金返還請求が行われていましたが、最近ではかなり減っています。実際、過払金返還請求できる人もかなり減っているでしょう。