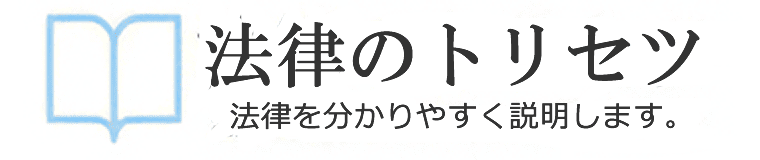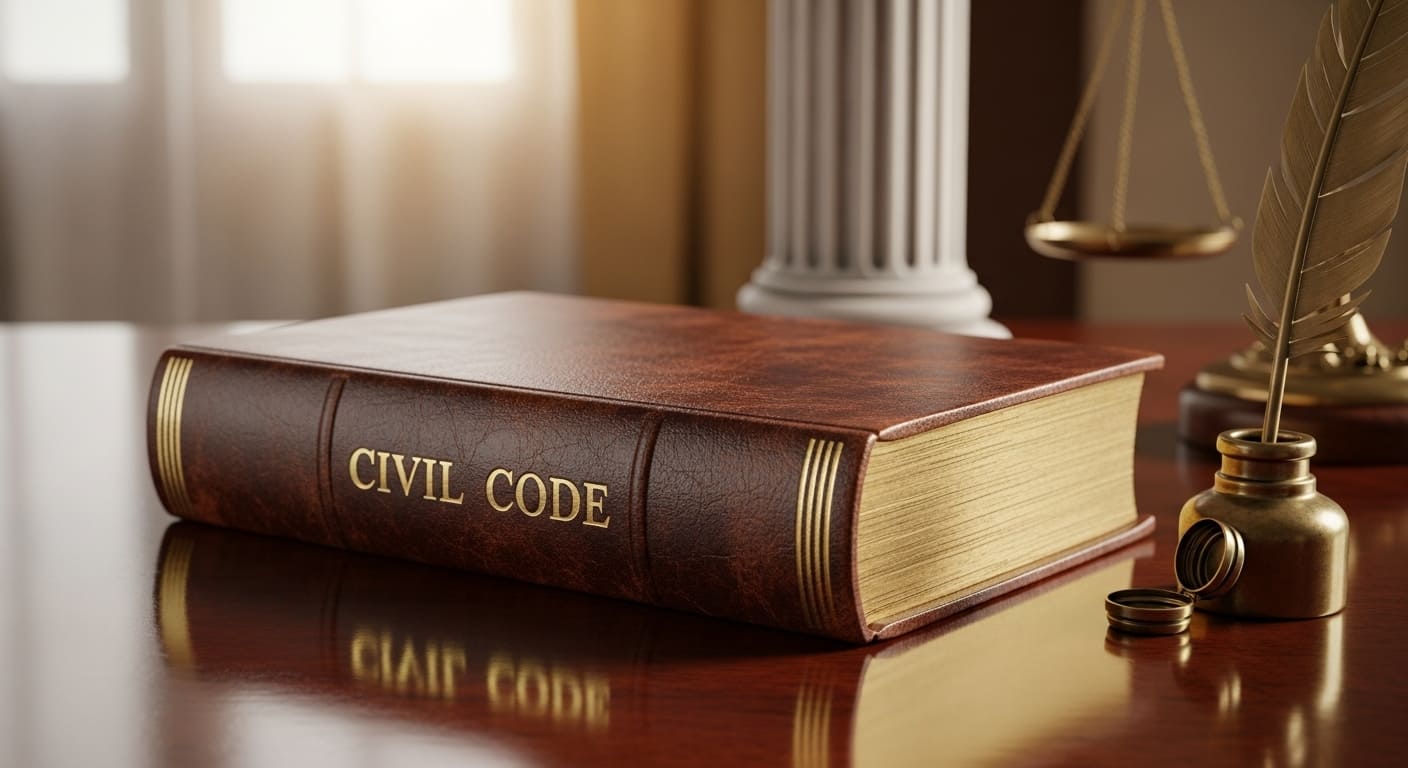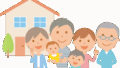この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
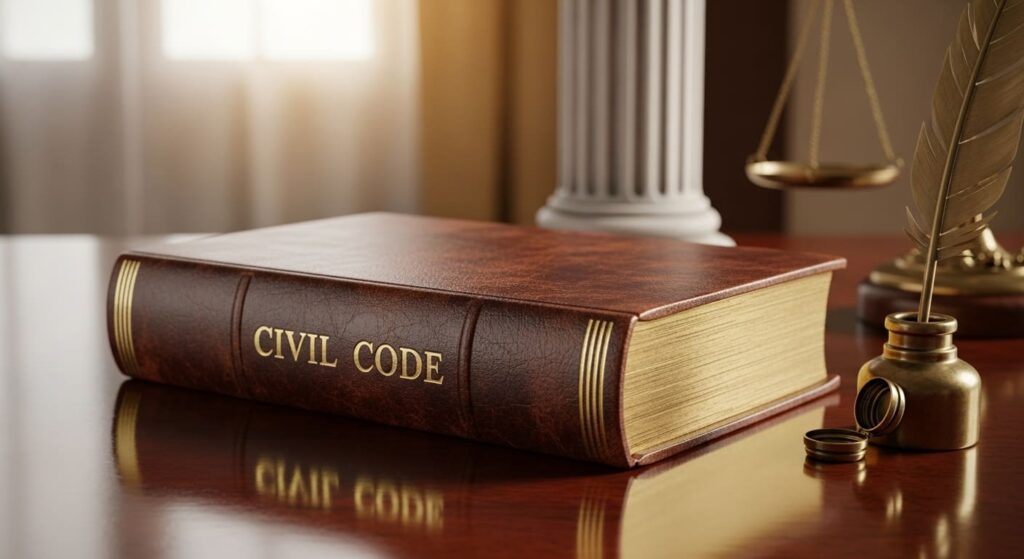
契約は法的な拘束力を持った約束ですから,容易に解消することはできません。もっとも,一定の場合には,契約を解除(解約)して契約関係を解消することが可能な場合があります。
契約の解除とは、当事者の一方による契約を解消させる旨の意思表示のことです。契約が解除されると、原則としてその契約は遡及的に消滅し、契約成立以前の状態に戻ります。
契約の解除とは
契約は,一方当事者の申込みの意思表示と他方の当事者の承諾の意思表示が合致した場合に成立する法律行為です。そして,契約が成立すると法的な拘束力が発生します。
そのため、いったん契約が成立すると、簡単には解消できなくなります。
ただし、契約を「解除」することにより、契約を解消することができます。この契約の解除とは,当事者の一方による契約を解消させる旨の意思表示です。
例えば、売買契約を締結し、代金を支払ったものの、目的物が滅失して履行不能となってしまった場合、契約を存続しておくことは無意味です。買主としては、契約を解消して、支払った代金を返してもらいたいと考えるでしょう。
このような場合に利用できる制度が、契約解除です。契約を解除することによって契約を解消し、支払った代金を返してもらうことができます。
契約解除の効果:遡及効と将来効
契約の解除にはさまざまな類型がありますが、原則的な効果は、契約を遡及的に消滅させることです。また、それに伴い、契約締結前の法律関係に戻すため、当事者には原状回復請求権が認められます。
もっとも、契約解除には、遡及的に契約を消滅させるのではなく、将来に向かって契約を消滅させる効果を生じるものもあります。
契約の遡及的消滅
前記のとおり、契約解除の原則的な効果は、契約を遡及的に消滅させることです。
遡及的に消滅するとは、契約の締結時にさかのぼって無かったことになります。そのため、契約が解除されると、契約の当事者は、契約の拘束力から免れることができます。過去の一時点までさかのぼって効力を生じることを遡及効といいます。
契約が遡及的に消滅するので、まだ履行していない債務(未履行債務)は、もはや履行しなくてよいことになります。
また、契約が解除されると、契約は遡及的に消滅し、法律関係は契約の締結前の状態に回復することになります(民法545条1項)。
そのため、契約解除をしても契約締結前の状態に戻っていない法律関係が残っている場合、契約の当事者は、お互いに契約締結前の状態に戻すよう請求できます。これを原状回復請求といいます。
原状回復請求をすることによって、当事者は、すでに履行済みの債務(既履行債務)をもとに戻すように請求できます。例えば、前記の例で言うと、支払い済みの売買代金を返還するよう請求できることになります。
既履行債務の原状回復を請求する場合、金銭債務であった場合には利息を付けて、金銭以外の債務であった場合には受領時以降に生じた果実も含めて返還しなければいけません(民法545条2項、3項)。
契約が将来に向かって消滅する場合
契約解除の効果の原則は、契約の遡及的な消滅です。もっとも、契約によっては、解除をしても遡及的に消滅するのではなく、将来に向かってのみ契約が消滅する場合もあります。将来に向かって効力を生じることを将来効といいます。
「将来に向かってのみ契約が消滅する」とは、契約を解除しても契約締結時にさかのぼって消滅するわけではなく、解除するまでの契約に基づく法律関係は消滅せず、解除した以降の法律関係だけが消滅するということです。
継続的契約の解除の場合は、遡及効ではなく将来効が生じます。例えば、賃貸借契約を解除した場合は、将来に向かってのみ解除の効力が生じます(民法620条)。
将来効の場合、解除以降に発生する予定だった債務の履行は不要となります。ただし、既履行債務の原状回復を請求することはできません。
契約解除の手続:解除の意思表示
民法 第540条
- 第1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
- 第2項 前項の意思表示は、撤回することができない。
契約解除は、当事者の一方による意思表示です(民法540条1項)。
つまり、当事者のどちらかが、契約を解除するという意思表示をし、それが他方に到達すれば、契約解除の効力が発生することになります。
具体的には、配達証明付きの内容証明郵便で契約を解除する旨の意思表示をするのが一般的でしょう。それでも,解除について当事者間に争いが生じた場合には,裁判手続を利用することになります。
なお、解除権者が複数人いる場合、その解除権者全員で解除の意思表示をする必要があります。他方、解除権者の相手方が複数人いる場合は、その全員に対して解除の意思表示をしなければなりません(解除権の不可分性。民法544条1項)。
契約を解除できる場合(解除権の発生原因)
前記のとおり、契約の解除は当事者の一方の意思表示をすれば足りますが、もちろんこれは、その当事者が契約解除権を持っている場合です。
契約は法的な約束ですから、容易には解消できません。したがって,一定の場合にしか、契約の解除はできないのです。
契約解除できる場合は、以下の4つに分類できます。
- 法定解除:法律の定めにより契約解除権が認められている場合
- 約定解除:当事者間で契約解除権が留保されている場合
- 手付解除:契約において当事者の一方が解約手付を交付していた場合
- 合意解除:当事者間で契約を解除することを合意した場合
法定解除
契約解除ができる場合の1つは、法律に定めがある場合です。これを「法定解除」といいます。法定解除については、民法540条以下に基本原則が定められています。
法定解除の場合には,法律で定められた要件を満たしている場合のみ,解除することができます。
法定解除は、民法だけでなく、特別法でも定められています。例えば、消費者契約法などで定められているクーリングオフ制度も、法定解除の一種です。
約定解除
第2は,当事者間で解除権が留保されている場合です。簡単にいえば,法定解除の要件がない場合でも一定の場合には解除できるということを,当事者間で取り決めていたという場合です。「約定解除」と呼ばれます。
約定解除の場合は,約定で決めた条件を満たせば解除できるということになります。
手付解除
約定解除には「手付解除」の場合もあります。これは,契約の際に当事者の一方が解約手付を交付していた場合に認められる解除です。
基本的には売買契約で認められるものです。手付解除は、以下の場合に認められます。
- 売主が手付解除する場合:受領した手付にさらに同額の金銭を加えた金額(要するに手付金の倍額)を買主に交付する(手付倍返し)
- 買主が手付解除する場合:手付金の返還請求権を放棄する(手付の放棄)
合意解除
また、「合意解除」もあります。これは、当事者間で契約を解除することに合意することです。当事者が解除に合意している以上、特に制限なく解除が認められます。
法定解除事由や約定解除事由がない場合だけでなく、これらがある場合でも、合意解除することは可能です。
民法541条・542条に基づく契約解除の要件
前記のとおり、契約の解除には、さまざまな種類があります。そのうちの法定解除も、契約によって解除の要件が異なる場合もあります。また、民法だけでなく、他の特別法に特殊な契約解除が定められていることもあります。
もっとも、これら契約解除の原則的形態といえるものは、民法541条および542条に定められている債務不履行に基づく解除です。
民法541条は催告による解除(催告解除)を定め、民法542条は催告によらない解除(無催告解除)を定めています。
催告解除の要件(民法541条)
民法 第541条
- 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法541条は、催告による解除(催告解除)について定めています。催告解除とは、相手方に履行の催告をしてからでないと解除できないとするものです。
この催告解除の要件は、以下のとおりです。
- 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと(債務不履行)
- 債権者が債務者に対して相当の期間を定めて催告をしたこと
- 催告期間を経過しても履行しないこと
- 債務不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
- 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないこと(民法543条)
無催告解除の要件(民法542条)
民法542条は、催告によらない解除(無催告解除)について定めています。無催告解除とは、相手方に催告をせずに契約を解除できるとするものです。
無催告解除の要件は、以下のとおりです。
- 以下の場合であること
- 履行不能の場合
- 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
- 一部履行不能または一部履行拒絶意思の明確表示の場合において、残存部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
- 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
- 上記のほか、債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
- 債務不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
- 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないこと(民法543条)
解除権の消滅
前記のとおり、契約解除権は、法律の規定、当事者間の約定や合意によって発生します。もっとも、いったん発生すれば消滅することがないわけではありません。
例えば、以下の場合には、解除権が消滅することがあります(民法以外の法律で別の解除権消滅原因が定められていることもあります。)。解除権が消滅すると、当然、契約の解除はできなくなります。
- 消滅時効による消滅(民法166条1項)
- 約定の解除権行使期間の経過による消滅
- 催告による消滅(民法547条)
- 故意・過失による目的物の損傷などによる消滅(民法548条)
- 他の解除権者の解除権消滅による消滅(民法544条2項)
消滅時効による消滅
民法 第166条
- 第1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
- 第1号 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
- 第2号 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
- 第2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
解除権も財産権です。そのため、時効により消滅することがあります。
この解除権は、形成権です。形成権とは、当事者の単独の意思表示により、権利の発生・消滅・変更などの法律効果を生じさせることのできる権利です。
通常の債権とは異なりますが、判例では「債権に準ずるものとして」債権の消滅時効の規定が適用されると判示されています(最一小判昭和62年10月8日)。この判例は民法改正前のものですが、現行民法でも妥当するでしょう。
したがって、解除権の時効期間は、解除権を行使できることを知った時から5年間または解除権を行使できる時から10年間のいずれか早い方となります(民法166条1項)。この時効期間経過後に、解除の相手方が消滅時効を援用すると、解除権は消滅します。
約定の解除権行使期間の経過による消滅
解除権を行使できる期間は、当事者間の約定で定めることができます。この期間を経過しても解除権が行使されなかった場合には、解除権は消滅します。
催告による解除権の消滅
民法 第547条
- 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
解除権の行使について期間の定めがない場合、解除の相手方は、解除権者に対して、相当の期間を定めてその期間内に契約を解除するかどうかを確答するよう催告できます(民法547条前段)。
この催告期間内に、解除権者が解除の通知をしなかった場合、解除権は消滅します(民法547条後段)。
故意・過失による目的物の損傷などによる消滅
民法 第548条
- 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。
解除権者が、解除権を有することを知りながら、以下の行為をした場合などには、解除権が消滅します(民法548条)。
- 契約の目的物を著しく損傷した場合
- 契約の目的物を返還することができなくなった場合
- 加工・改造によって契約の目的物を他の種類の物に変えた場合
他の解除権者の解除権消滅による消滅
民法 第544条
- 第1項 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
- 第2項 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
解除権者が複数人いる場合、そのうちの1人について解除権が消滅したときは、解除権の不可分性により、他の解除権者の解除権も消滅します(民法544条)。
例えば、複数人いる解除権者のうちの1人が、目的物を著しく損傷したことにより解除権を失った場合、他の解除権者は、何も解除権が消滅するようなことをしていなくても、全員の解除権が消滅してしまうということです。
解除と他の制度の違い
これまで述べてきたとおり、契約の解除は、契約を解消するための制度です。もっとも、契約の解消を意味する用語には、いろいろなものがあります。似たような用語もあり、混同しやすいので、注意を要します。
以下では、契約解除とこれに類似する用語や制度の違いについて説明します。
解除と解約の違い
契約の解除と似た用語として「解約」があります。
講学上、解除が契約を遡及的に無効にするものであるのに対し、解約は将来に向かって契約の効力を失わせるもの(将来効)であると解されています。
そのため、解除の場合には、契約ははじめから効力のないものとして扱われますが、解約の場合には、解約するまでは有効であり、解約した以降だけ効力がないものとして扱われるという違いがあります。
解除は、売買契約のような一回的契約で用いられます。他方、解約は、賃貸借契約のような継続的契約で用いられます。継続的契約を途中で解消することを途中解約と呼ぶことがありますが、これがまさに「解約」の例です。
もっとも、法律の条文などでは、講学上は解約にあたるものを「解除」と規定していることもあります。例えば、民法620条は、賃貸借契約の「解除」と規定しているものの、その内容は講学上の解約です。
そのため、解除と解約という用語自体をあまり厳密に捉える必要はないでしょう。いずれの用語であったとしても、大事なことは、その解除または解約の効果が、遡及効なのか将来効なのかという点です。
解除と取消しの違い
解除と同じように、契約を解消する制度として「取消し」があります。
この取消しがされた場合も、契約は遡及的に無効(消滅)となります。解除と同じ効果を持っているのです。
ただし、解除は、法定解除の場合には法律で定められた場合に限定されるものの、当事者間で解除の約定を定めたり、合意によって解除することが可能です。
しかし、取消しは、法律で定められた場合しか認められません。当事者間で取消しの約定を定めたり、合意によって契約を取り消すことはできないのです。
解除と撤回の違い
解除とニュアンスの近い用語として「撤回」があります。この撤回も、解除と混同されがちな用語です。
講学上、撤回とは、意思表示を将来に向かって消滅させることです。
将来に向かって効力を消滅させる点では、解除(解約)に近いところがあります。しかし、撤回の対象は「意思表示」です。法律行為である「契約」を対象とする解除と異なります。
意思表示を将来に向かって消滅させるものが撤回であり、契約を将来に向かって消滅させるものが解除(解約)であるという違いがあるのです。
例えば、契約の申込みや承諾の意思表示を消滅させる場合は、撤回です。しかし、いったん申込みと承諾が合致して契約が成立した場合、これを消滅させるには、撤回ではなく解除(解約)が必要となります。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権各論上巻(民法講義Ⅴ1)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内10(契約総論)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
契約法(新版)
著者:中田裕康 出版:有斐閣
契約法の概説書です。債権法の改正にも対応しています。説明は分かりやすく、情報量も十分ですので、基本書として使えます。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか 出版:新世社
債権各論全般に関する概説書。どちらかと言えば初学者向けなので、読みやすい。情報量が多いわけではないので、他でカバーする必要はあるかもしれません。
債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。