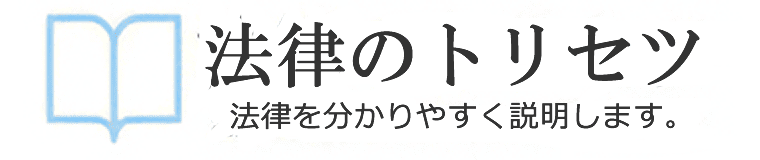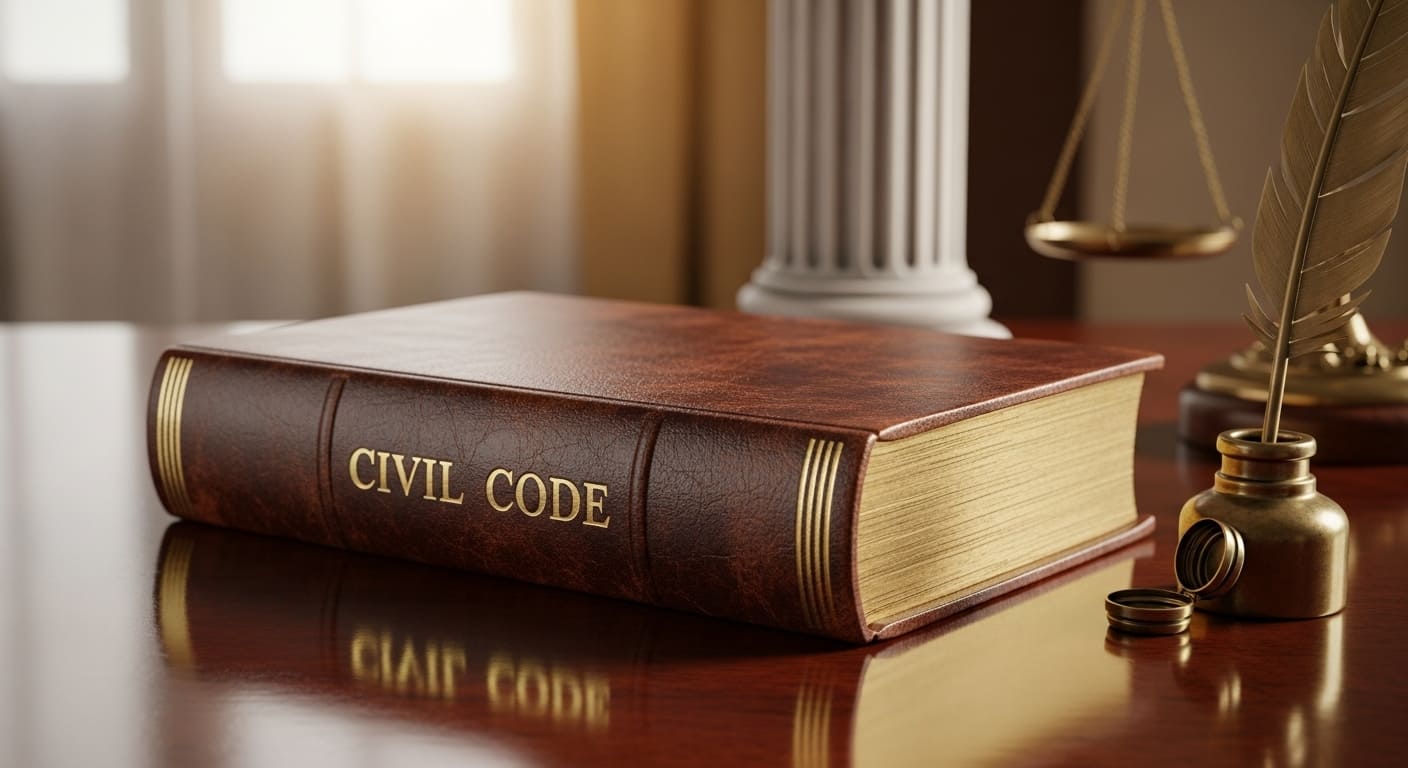この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
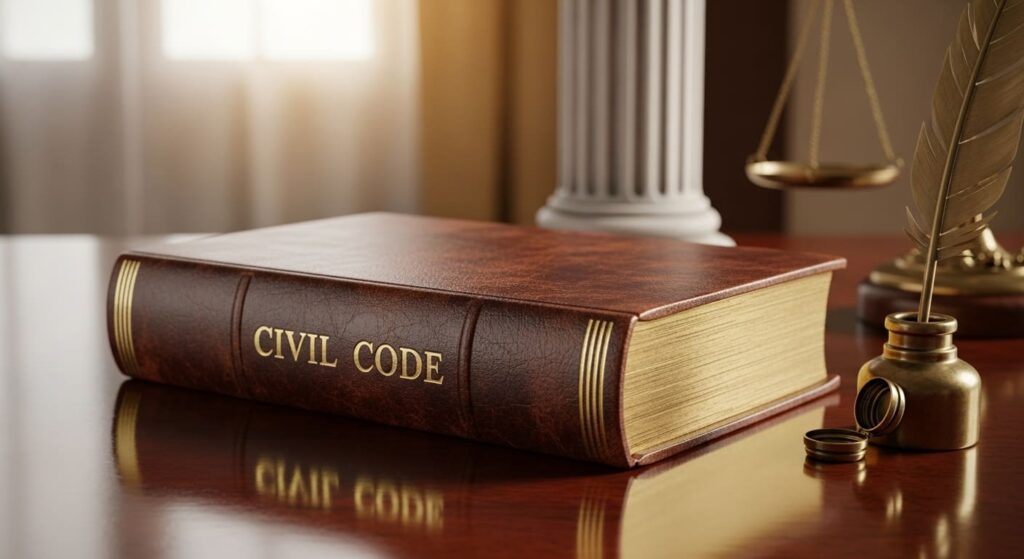
賃貸借契約の終了原因の1つに賃貸借契約の解除があります。賃貸借契約を解除できる場合としては、当事者間の合意による場合(合意解除)、当事者が合意により定めた約定違反による場合(約定解除)、法律の定めがある場合(法定解除)に分けられます。
賃貸借契約の解除とは
契約の解除とは、当事者の一方の意思表示によって、契約を消滅させることをいいます。
しかし、契約には法的拘束力があります。簡単になかったことにはできないからこそ契約なのです。そのため、契約を解除することができる場合は、非常に限られてきます。
賃貸借契約も契約ですから、簡単に解除できるものではありません。
賃貸借契約を解除できるのは、当事者間で合意がある場合か法律で定められている場合に限られます。具体的に言うと、賃貸借契約を解除できる場合は、以下の3つの場合です。
- 合意解除
- 約定解除
- 法定解除
賃貸借契約が解除された場合の効力
民法 第620条
- 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
契約が解除された場合、契約の締結時にさかのぼって効力を失うと考えるのが一般的です。過去の一時点にさかのぼって効力を発生するため、遡及効と呼ばれます。
もっとも、賃貸借契約が解除された場合は、契約締結時にさかのぼるのではなく、将来に向かってのみ契約が消滅します(民法620条)。契約締結から契約解除するまでの間の取引は、消滅しないのです。
賃貸借契約のような継続的契約を遡及的に消滅させてしまうと、それまで継続していた取引がすべて覆ってしまうことになり、法律関係が複雑になるだけでなく、解除前に利害関係を持った第三者の取引の安全を害することにもなりかねません。
そのため、通常の契約解除の場合と異なり、遡及効ではなく、将来に向かってのみ解除の効力が発生するものとしているのです。このように将来に向かってのみ効力を生じることを、将来効と呼んでいます。
解除と解約の違い
上記の賃貸借契約の解除の効力に関連して、「解除」と「解約」の違いの問題があります。解除と解約は同じ意味のように使われていますが、講学上は区別があります。
講学上、解除が遡及的に契約を消滅させるものであるのに対し、解約は将来に向かってのみ契約を消滅させるものであるとされています。
民法620条は賃貸借契約の「解除」と定めていますが、この民法620条は、解除の効力が将来に向かってのみ生じると定めているので、講学上の定義からすると、これは賃貸借契約の「解約」に該当します。
あくまで講学上の区別であり、上記のとおり民法でも厳密に解除と解約を区別していません。そのため、用語の別にあまりこだわる必要はないでしょう。大事なことは、遡及効なのか将来効なのかという点です。
信頼関係破壊の理論(法理)
賃貸借契約の解除を考える際には、信頼関係破壊の理論(法理)について理解しておく必要があります。
信頼関係破壊の理論とは、賃貸借契約のような当事者間の高度な信頼関係を基礎とする継続的契約においては、当事者間の信頼関係を破壊したといえる程度の債務不履行や約定違反がなければ契約を解除することはできないとする理論です。
賃貸借契約は、売買契約などの一回的な契約と違い,賃貸人と賃借人の間の信頼関係に基づく継続的な契約関係です。
そのため、約定違反や債務不履行があっただけで契約を解除できるとするのは、契約を継続させようとする当事者の合理的に意思に反する場合があります。
そこで、賃貸借契約のような継続的契約においては、明文はないものの、解釈上、賃貸借契約を解除する場合の要件と考えられています。
したがって、賃貸借契約を解除するためには、単に約定解除や法定解除の要件を満たしているだけでは足りず、信頼関係を破壊したといえるだけの事情があるかどうかも考えておかなければなりません。
賃貸借契約の合意解除(解約)
賃貸借契約を解除できる場合(解除原因)の1つは、当事者間で契約を解除する合意をした場合です。「合意解除」「合意解約」と呼ばれます。
前記のとおり,契約を解除できる場合は限られています。しかし,それは、契約を締結した当事者の意思を無意味なものにしないようにするためです。
しかし、当事者が契約を解除する合意をしたならば,解除を認めても当事者の意思に反することにはなりません。むしろ、当事者の新たな意思に沿うといえます。
そのため、合意解除・合意解約は、特に制限なく認められます。また、合意解除の場合には、信頼関係破壊の理論の適用はありません。
賃貸借契約の約定解除(解約)
約定解除とは、当事者の合意によって当事者の一方または双方に契約解除権を付与し、その解除権に基づいて当事者の一方が契約を解除する場合です。
賃貸借契約では、一定の場合には賃貸人または賃借人が契約を解除できると定めた解除条項が入れられているのが一般的です。その解除条項に基づいて解除する場合が、約定解除です。
この約定解除は、もちろん有効です。しかし、約定解除事由に該当すればただちに解除できるわけではありません。
前記のとおり、賃貸借契約には、信頼関係破壊の理論が適用されます。約定解除の場合も、この信頼関係破壊の理論は適用されると解されています。
そのため、約定違反があっても、軽微な契約違反だけでは、賃貸借契約を解除することは難しいでしょう。
賃貸借契約の法定解除
法定解除とは、法律で定められている契約解除の原因がある場合に、それを理由として解除をすることをいいます。
賃貸借契約の場合、以下の法定解除事由があります。
- 賃借人の意思に反する保存行為により賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる場合の賃借人による解除(民法607条)
- 耕作・牧畜を目的とする土地賃貸借において、賃借人の収益が不可抗力によって2年以上引き続いて賃料より少ない場合の賃借人による解除(民法610条)
- 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用・収益をできなくなり、残存部分のみでは賃借をした目的を達することができない場合の賃借人による解除(民法611条2項)
- 賃借人が賃貸人の承諾なしに賃借権譲渡・転貸した場合の賃貸人による解除(民法612条2項)
- その他当事者に債務不履行があった場合の解除(民法541条、民法542条)
賃借人の意思に反する保存行為によって目的を達せられなくなった場合の賃借人による解除
民法 第606条
- 第1項 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
- 第2項 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
民法 第607条
- 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
賃貸人は、賃借物の修繕義務を負うだけでなく、賃借物の保存行為をする権利を有しています。保存行為とは、賃借物の現状を維持する行為です。賃貸人が保存行為をする場合、賃借人はこれを拒むことはできません(民法606条2項)。
しかし、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をすることによって、賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる場合があります。
例えば、建物賃貸借において、保存行為として居住空間を長期間占拠する大規模修繕工事を行うような場合が考えられます。
このような場合でも、保存行為である以上、賃借した目的を達せられないとしても賃借人は保存行為を拒めません。しかし、それではあまりに賃借人に酷です。
そこで、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をすることによって、賃借人が賃借をした目的を達することができなくなる場合、賃借人は契約を解除できるとされています(民法607条)。
- 賃貸人が保存行為をしようとすること
- その保存行為が賃借人の意思に反するものであること
- 賃借人が賃借をした目的を達することができなくなること
耕作・牧畜を目的とする土地賃貸借において減収した場合の賃借人による解除
民法 第609条
- 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
民法 第610条
- 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
耕作・牧畜を目的とする土地賃貸借において、不可抗力によって収益が賃料より少なくなった場合、賃借人は、その少なくなった収益の額に至るまで賃料の減額を請求できます(民法609条)。
例えば、賃料が20万円であった場合、不可抗力によって収益が10万円になってしまったときは、10万円まで賃料を減額するよう請求できるということです。
さらに、この不可抗力による収入が賃料より少なくなる減収が2年以上続いた場合には、賃料減額請求にとどまらず、契約を解除できるとされています(民法610条)。
- 耕作・牧畜を目的とする土地賃貸借であること
- 不可抗力によって収益が賃料額より少なくなったこと
- 上記減収が2年以上続いたこと
賃借物の一部滅失などにより使用収益できなくなった場合の賃借人による解除
民法 第611条
- 第1項 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
- 第2項 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
賃借物の全部が滅失するなどして全部の使用収益ができなくなった場合、賃貸借契約は終了します(民法616条の2)。
それでは、全部ではなく一部の滅失等などによって使用収益の一部ができなくなった場合はどうかというと、この場合は、その滅失などが賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、使用収益できなくなった部分の割合に応じて賃料が減額されます(民法611条1項)。
さらに、この一部の使用収益ができなくなった場合に、残存部分だけでは賃借した目的を達せられないときは、賃借人は賃貸借契約を解除できます(民法611条2項)。
例えば、店舗として建物を賃借した場合に、火事によって事務所部分は残ったものの店舗部分が滅失してしまったとすると、もはや店舗として利用できず賃借した目的を果たせないため、賃借人は契約を解除できます。
- 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益できなくなったこと
- 残存部分のみでは賃借人が賃借した目的を達することができないこと
無断転貸・無断賃借権譲渡による賃貸人の解除
民法 第612条
- 第1項 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
- 第2項 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
賃貸借契約は,賃貸人と賃借人との信頼関係に基づく契約です。つまり,賃貸人は,その賃借人だからこそ貸しているという信頼関係が根底にあります。
それにもかかわらず,賃借人が,賃貸人に無断で,誰とも知らない人に勝手に目的物を利用させてしまうというのは,信頼関係に反する背信的な行為といえます。
そのため、賃借人が賃借権の譲渡や転貸をするには、賃貸人の承諾が必要です(民法612条1項)。
これに違反して、賃借人が、賃貸人に無断で賃借権の譲渡や転貸をしてしまった場合、賃貸人は、賃貸借契約を解除できるとされています(民法612条2項)。
ただし、この無断賃借権譲渡・無断転貸による賃貸人の解除の場合にも、信頼関係破壊の理論が適用されます。
したがって、民法612条2項による賃貸借契約の解除が認められるのは、単に無断賃借権譲渡・無断転貸をしただけでは足りず、賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊したといえるような事情がある場合に限られることになります。
債務不履行による解除
賃貸借契約が成立すると、賃貸人は賃借物を使用収益させる義務などを負い、他方、賃借人は賃料を支払う義務などを負うことになります。
当事者がこれらの義務に違反して債務の本旨に従った履行をしなかった場合、その違反者(債務者)の相手方である当事者(債権者)は、債務不履行を理由として契約を解除できます。
催告による解除
民法 第541条
- 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
債務不履行により契約を解除する場合、債権者である当事者は、違反者である当事者に対して相当の期間を定めてその履行の催告をする必要があります。その期間内に履行がないときに限り、契約を解除できます(民法541条)。
ただし、債務不履行による賃貸借契約の解除には「信頼関係破壊の法理」が適用されます。
したがって,賃貸借契約の債務不履行解除が認められるのは,単に契約違反があったというだけで足りず,賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊したといえるほどの契約違反がある場合に限られることになります。
例えば,賃料滞納の場合で言うと,賃借人が1か月賃料を滞納したというだけでは賃貸人は契約を解除することはできず,数か月賃料を滞納した場合にはじめて,賃料滞納を理由として契約を解除できます。
- 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと(債務不履行)
- 債権者が債務者に対して相当の期間を定めて催告をしたこと
- 催告期間を経過しても履行しないこと
- 債務不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
- 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないこと(民法543条)
催告によらない解除(無催告解除)
民法 第542条
- 第1項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
- 第1号 債務の全部の履行が不能であるとき。
- 第2号 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
- 第3号 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
- 第4号 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
- 第5号 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
- 第2項 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
- 第1号 債務の一部の履行が不能であるとき。
- 第2号 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
前記のとおり、債務不履行による契約解除は、催告をすることが必要とされるのが原則です。もっとも、以下の場合には、催告をせずに、契約を解除できます(民法542条)。
- 以下の場合であること
- 履行不能の場合
- 債務者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
- 一部履行不能または一部履行拒絶意思の明確表示の場合において、残存部分のみでは契約をした目的を達することができないとき
- 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき
- 上記のほか、債務者が債務の履行をせず、債権者が催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合
- 債務不履行が契約および取引上の社会通念に照らして軽微でないこと
- 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものでないこと(民法543条)
解約の申し入れによる解約
民法 第617条
- 第1項 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
- 第1号 土地の賃貸借 1年
- 第2号 建物の賃貸借 3箇月
- 第3号 動産及び貸席の賃貸借 1日
- 第2項 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
民法 第618条
- 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
これまで説明してきた強制的な一方的解除とは異なりますが、期間の定めのない賃貸借契約は、当事者からの解約申入れによっても終了します(民法617条1項)。
ただし、すぐに解約になるわけではなく、解約申入れ日から以下の期間を経過した時に賃貸借契約が終了します。
期間の定めがある賃貸借契約の場合は、原則として解約申入れはできません。ただし、契約で解約申入れできることを定めていた場合は、期間の定めがある賃貸借契約であっても、解約申入れが可能です(民法618条)。
ただし、建物賃貸借(借家)や建物所有を目的とする土地賃貸借(借地)については、民法ではなく、借地借家法が適用されます。
借地契約における借地借家法の修正
建物所有を目的とする土地賃貸借(借地)契約は、期間を定めなかったとしても、存続期間は30年になり、この期間内は解約申入れできません(借地借家法9条)。
なお、期間の定めがある借地契約は、解約申入れできることを約定で定めていない限り、解約申入れできません。
借家契約における借地借家法の修正
期間の定めがない借家契約は、解約申入れが可能です。期間が1年未満の借家契約も、期間の定めがないものとして扱われるので、解約申入れできます。
この解約申入れを賃借人(借家人)が行うときは、特に制限がありません。民法の規定どおり、解約申入れから3か月で借家契約は終了します。
しかし、賃貸人が解約申入れをするには、正当な事由がなければいけません(借地借家法28条)。正当事由がある解約申入れがされると、解約申入れ日から6か月経過後に借家契約が終了します(借地借家法27条1項)。
この記事は、法トリ(元弁護士)が書いています。
この記事が参考になれば幸いです。
民法と資格試験
民法は、私法の基本法です。我々の生活に最も身近な法律です。
そのため、例えば、司法試験(本試験)、司法試験予備試験、司法書士試験、行政書士試験、宅建試験、マンション管理士試験・・・など、実に多くの資格試験の試験科目になっています。
これら法律系資格の合格を目指すなら、民法を攻略することは必須条件です。
とは言え、民法は範囲も膨大です。メリハリを付けないと、いくら時間があっても合格にはたどり着けません。効率的に試験対策をするには、予備校や通信講座などを利用するのもひとつの方法でしょう。
STUDYing(スタディング)
・司法試験・予備試験も対応
・スマホ・PC・タブレットで学べるオンライン講座
・有料受講者数20万人以上・低価格を実現
参考書籍
本サイトでも民法について解説していますが、より深く知りたい方や資格試験勉強中の方のために、民法の参考書籍を紹介します。
新訂債権各論中巻一(民法講義Ⅴ2)
著者:我妻榮 出版:岩波書店
民法の神様が書いた古典的名著。古い本なので、実務や受験にすぐ使えるわけではありませんが、民法を勉強するのであれば、いつかは必ず読んでおいた方がよい本です。ちなみに、我妻先生の著書として、入門書である「民法案内11(契約各論上)」や「ダットサン民法2 債権法(第4版)」などもありますが、いずれも良著です。
我妻・有泉コンメンタール民法(第8版)
著書:我妻榮ほか 出版:日本評論社
財産法についての逐条解説書。現在も改訂されています。家族法がないのが残念ですが、1冊で財産法全体についてかなりカバーできます。辞書代わりに持っていると便利です。
契約法(新版)
著者:中田裕康 出版:有斐閣
契約法の概説書です。債権法の改正にも対応しています。説明は分かりやすく、情報量も十分ですので、基本書として使えます。
司法試験・予備試験など資格試験向けの参考書籍としては、以下のものがあります。
民法(全)(第3版補訂版)
著者:潮見佳男 出版:有斐閣
1冊で民法総則から家族法まで収録されています。基本書というより入門書に近いでしょう。民法全体を把握するのにはちょうど良い本です。
基本講義 債権各論Ⅰ(契約法・事務管理・不当利得)第4版補訂版
著者:潮見佳男ほか 出版:新世社
債権各論全般に関する概説書。どちらかと言えば初学者向けなので、読みやすい。情報量が多いわけではないので、他でカバーする必要はあるかもしれません。
債権各論(第4版)伊藤真試験対策講座4
著者:伊藤塾 出版:弘文堂
いわゆる予備校本。予備校本だけあって、実際の出題傾向に沿って内容が絞られており、分かりやすくまとまっています。民法は範囲が膨大なので、学習のスタートは、予備校本から始めてもよいのではないでしょうか。